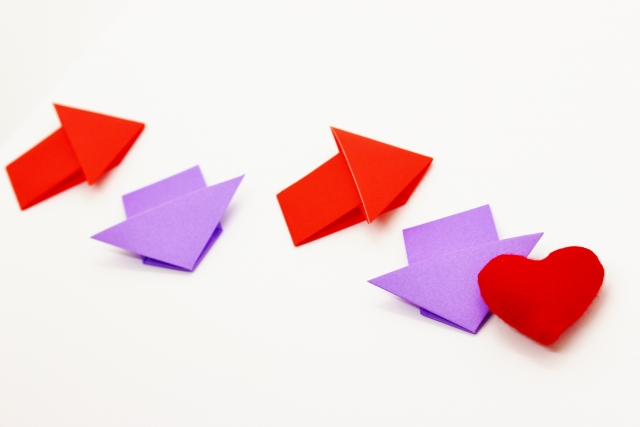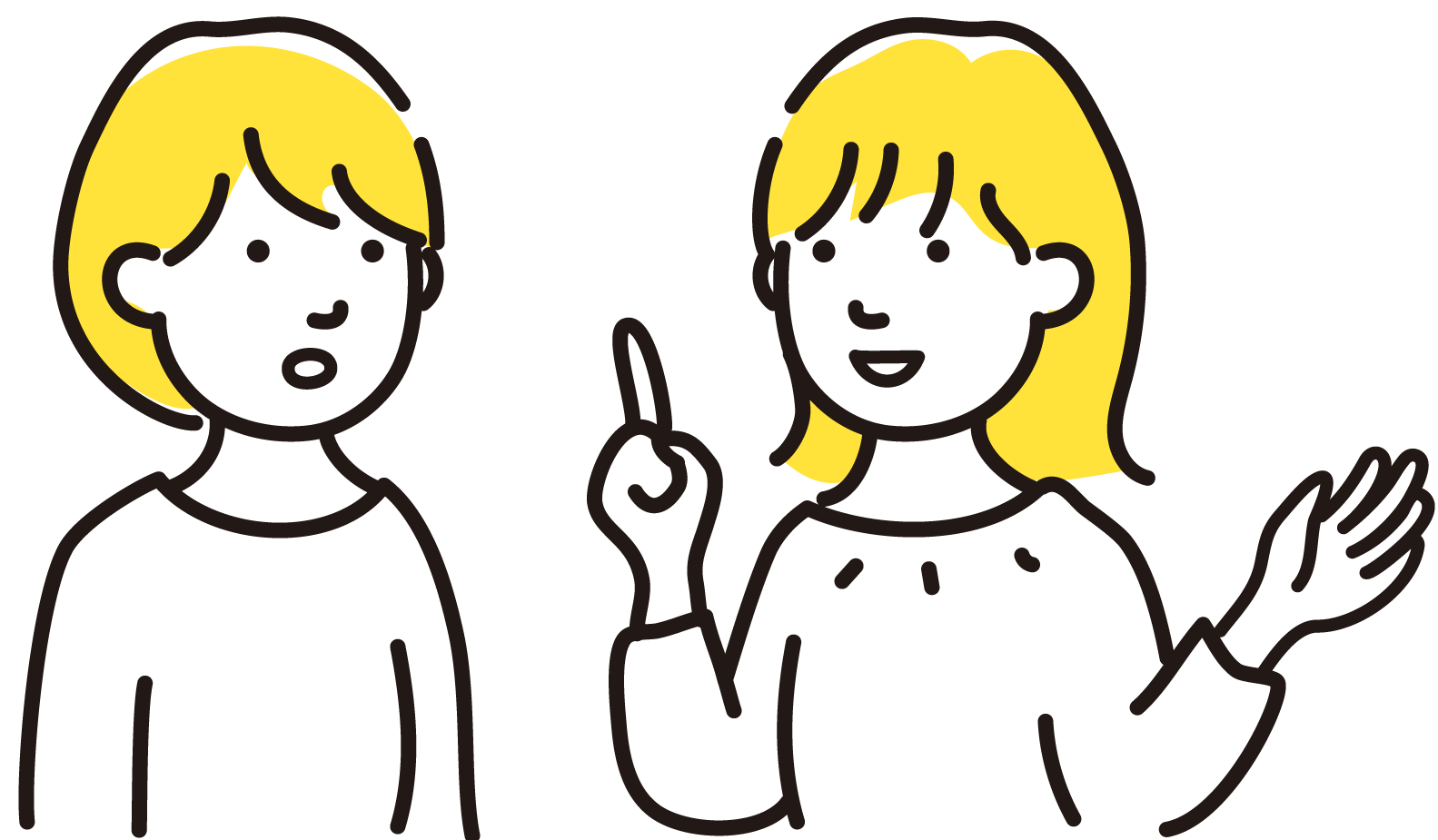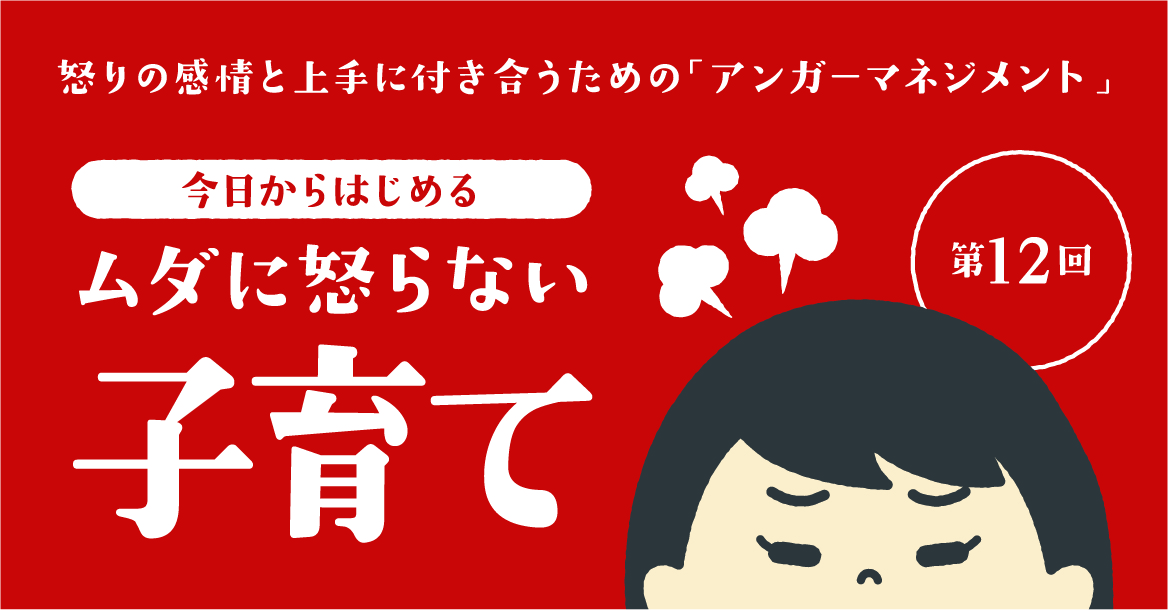【セルフチェック】エンパスとは?特徴やHSPとの違い、共感疲れがしんどいときの対処法

「人付き合いが苦手で、心が不安定」「人と会った後、体調が悪くなる」それはあなたが「エンパス」で他者の感情への高い共感力を持つからかもしれません。エンパスとは、どのような特徴・体質の人なのか、HSPとの違い、生きにくさや悩みを解決する方法について、公認心理士である近江亜佳里さんにお話を伺いました。
目次
エンパスとは?
はじめに、エンパスについて概要を紹介します。
エンパスの定義
「エンパス(empath)」とは、「共感」の意味を表す英単語「empath」を語源とし、「エンパシー(empathy)=共感する力、感情移入の力」の強い人を指します。一般論ですが、世界中の5人に1人はエンパスであるといわれています。
エンパスは医療用語ではなく、また病名などでもありません。病院で診断や治療ができるものではなく、あくまでも人の性質や体質を指す語です。「他人の感情を、まるで自分の感情のように感じてしまう」体質の人を指します。「人の感情から、過剰に影響を受けやすい人」とも言えるでしょう。
エンパスについての著書もあるロサンゼルスの精神科医であるジュディス・オルロフ医師は、著書『LAの人気精神科医が教える 共感力が高すぎて疲れてしまう人がなくなる本』(SBクリエイティブ)の中で、エンパスを下記のように定義しています。
エンパスとは、神経系が極端に敏感で、反応する力が人よりも強い人たちのこと。一般的に人は、他者の行動や感情から影響を受け過ぎないように、外からの刺激をある程度ブロックできるようになっているのだが、エンパスはその防御力が極端に弱い。その結果、周りのポジティブなエネルギーも、ストレスの大きいエネルギーも、すべて吸収してしまう。
引用元:『LAの人気精神科医が教える 共感力が高すぎて疲れてしまう人がなくなる本』(SBクリエイティブ)
エンパスの6つのタイプ
人の行動や感情から影響を受けやすい性質を持つとされるエンパスですが、そのなかには6つのタイプがあると言われています。
1.身体合一(ワンネス)型
相手の体に起きていることを、自分も同化して自分の体で起きているように感じたり、その症状が出たりする。
2.身体直感型
相手の体に起きていることが直感的に理解できる。
3.感情合一(ワンネス)型
相手の感情を、自分の感情のように感じる。無意識に相手と感情の部分で同化する。
4.感情直感型
相手の感情が直感的に理解できる。
5.知的自己変容型
他人の考えに合わせて行動してしまう。相手の知的能力を自分に取り込むことができる。
6.霊的合一(ワンネス)型
相手のスピリットや、スピリチュアルな存在と同化することができる。
エンパスの特徴
エンパスは、生まれながらの気質とされています。またエンパスであることで、以下のような特徴があるといわれます。
エンパスの特徴とされる一例
- 人の悩みを聞いていると、自分ごとのように感じてしまい、その悩みに共感してしまう
- 体調不良の人の苦しみを、一緒にいると同じように苦しく感じ、同じ部位に痛みやつらさを感じる気がする
- 他人の嘘や裏の意図がなんとなくわかるような気がする。言われていない他人の気持ちをくんで、それに沿って行動してしまうことがある
- 残酷なニュース、甚大な災害や戦争の映像などは、つらくなってしまって見られない
- 悪し様な言葉、悪いことを予感させるような言葉に影響をうけ、聞いただけで具合が悪くなったり不安になったりする
- 人が怒られているのを聞いていると、自分が怒られているように感じて苦しくなる。また人が失敗していることを見ているだけで自分が失敗したように苦しくなる
- 土地や場所などの悪いエネルギーを、なんとなく感じるような気がする
- 人混み(満員電車や都会の雑踏、混雑したイベント現場など)が苦手
また、エンパスとされる人は日常において次のようなことが起こりやすいそうです。
- 疲れやすい
- 心が不安定で、依存症になりやすい
- 問題のあるパートナーを選びやすい
- 子育ての責任に押しつぶれされやすい
- 仕事環境に気分や体調が左右されやすい
- 特殊な知覚能力をもちやすい
共感できる人も多いのではないでしょうか。特に、「子育ての責任に押しつぶされやすい」理由は、エンパスの場合、子どもの感情や苦痛を自分のことのように感じてしまうからなのだそうです。
ジュディス・オルロフ医師は、「子育てはエンパスにとって大きな脅威である」としながら、同著の中でストレスを軽減するための対策として、「過干渉(ヘリコプターペアレント)にならない」「子どもに対しての境界線を決める」などのアドバイスをしています。
<ヘリコプターペアレントについての記事はこちら>
ヘリコプターペアレントとは?特徴と事例、予防策を解説
エンパスとHSPの違い
繊細で敏感な気質といえば、HSP(Highly Sensitive Person)を思い浮かべる人もいるかもしれません。HSPは心理学的概念で、「感受性が非常に強い、繊細な性質の人」を指します。なおHSPもエンパスと同じように、他者の感情への反応の強さも特徴として挙げられています。
前出のジュディス・オルロフ医師は、同著の中で、エンパスとHSPは共通している点が多く、両方の性質が重なっている人もいるとしながらも下記のように書いています。
エンパスはHSPをさらに敏感にした人たちだ。~中略~ エンパスはよく、他者の不快感と、自分の不快感の区別がつかなくなる。
引用元:『LAの人気精神科医が教える 共感力が高すぎて疲れてしまう人がなくなる本』(SBクリエイティブ)
明確な違いがあるというわけではなく、「エンパスのほうが周囲の影響をより受けやすい人」といえるようです。
なお、子どものHSPともいえるHSC(Highly Sensitive Child)という体質もあります。以下の記事をご参照ください。
<HSP/HSCについての関連記事はこちら>
HSCの10の特徴を知れば、接し方や対応が理解しやすくなる
人の影響を受け過ぎて疲れやすい人とは?
「自分がエンパスかどうか分からないけれど、人といることで心身の調子が悪くなる、エネルギーを消耗する」と感じている人もいるのではないでしょうか。ここからはエンパスかもしれない人、特に共感し過ぎて疲れやすい(以下、「共感疲れ」とします)タイプの人について、公認心理師でカウンセラーの近江亜佳里さんのお話から探っていきましょう。
「自分の気持ちよりも周りの人の気持ちを優先したり、嫌な気持ちになっていないかと気遣ったりする人は共感力が高いといえるでしょう。
ただそれ以上に、相手の話に対して『何とかしてあげたい』『全力で受け止めてあげたい』と思いすぎてしまう人は、結果的に受け止めきれることができなかった場合に余計に疲れてしまう(共感疲れをする)傾向があると思います」
共感する気持ちの根本にあるのは、「相手への優しさ」ですが、その思いがうまく機能しないことが“共感疲れ”につながっているのかもしれませんね。
エンパスの語源「共感力」をセルフチェックしよう
近江さんのお話をもとに、エンパスの一端ともいえる”共感疲れ”を起こしやすい人の特徴をチェックリストにしてみました。当てはまる部分が多い人は、共感疲れをしやすい傾向にあります。チェックしてみてくださいね。
共感疲れチェックリスト
- 自分の気持ちより他人の気持ちを優先してしまう
- 一緒にいる人が嫌な思いをしていないか非常に気になる
- 人がストレスを感じていると何とかしてあげたいと思う
- 相談してくれる人には全力で応えたい
- コンプレックスが強い
- 小説やマンガなどの創作物にも感情移入しやすい
- SNSなどで見た他人の経験を自分の事のように感じてしまう
- 過去のこと(人の言動など)をよく覚えている
- 協調性が高すぎる
- 探究心が強すぎる
- ガマンすることに慣れている
- 頑張り屋さんで生真面目
上記の特徴は、それぞれが切り離されたものではありません。以下は一例ですが、このような経験にあてはまる人もいるのではないでしょうか。
- コンプレックスが強い人:小説やマンガなどの創作物やSNS上の他人の経験に自分のネガティブな思い出や感情を載せてしまいすぎることもある
- 記憶力が良く過去のことを細かく覚えている人:相手に共感する要素が人よりも多くなり身体も心も疲れやすくなる
- 自分に期待される役割をキチンと果たそうという気持ちがある生真面目な性格の人:自分の気持ちを押し殺して(ガマンをして)でも周囲の気持ちや目的を優先させるので結果的に疲弊してしまう
エンパスが抱えやすい悩み
エンパスの人は、疲れていることが非常に多いです。その理由は、自分と他人の感情の境界線が薄いこと、自分と他人の感情の境界線がエンパスではない人に比べて薄いが故に、他人に影響されやすく感情に振り回されながら生きていることにあります。
そのため常にストレスにさらされている状態であり、胃痛などの消化器症状や、睡眠障害、アレルギー症状など様々なストレス症状や不調を抱えている人が多いです。その症状が強くなり、うつの診断を受けている人も多くいるはずです。
あなたの悩み・つらさをカウンセラーに相談できます
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上でカウンセラーに悩みを相談できます。
相談相手を探してみる
エンパス体質で共感疲れしないための4つの対処法
エンパスの概念は幅広く、出てくる症状もさまざまです。しかし、強すぎる感受性のせいで日々疲れているとどんどん消耗してしまいますよね。もともと共感力が高すぎる人でも疲れないためにできることはあります。ここでは共感疲れしないために普段の生活の中でできる方法を紹介します。まずは次の4つを意識して行ってみてはいかがでしょうか。
【方法①】他人を丸ごと受けとめようとしない
普段は、カウンセラーとしてさまざまな親子と向き合っている近江さんですが、自身もクライエントの感情や事情に振り回されてしまった経験があるそうです。
「やはり、どんな人間でも他人の人生を丸ごと受け止めて、一緒に歩んでいくことはできないんですよね。自分の役割や許容範囲を超えてまで、『どうにかしてあげたい』という気持ちが強すぎると、つらくなってしまいます。自分ができることとできないことは分けて考えなければいけません」
「相手のことを100%分かることはできない、他人を背負うこともできない」という割り切りは必要のようです。
【方法②】体調に合わせてスケジュールをずらす
前述の通り、共感疲れにはその日のコンディションが大きく影響します。そのため、「今日はネガティブ思考に陥りそうだな」「自分にゆとりがないな」と感じたときは、予定を変えるのも一つの方法です。
「(近江さん談)共感力が高い人は、自分よりも相手を大切にしやすい傾向があるので、難しいことかもしれません。でもそこを敢えて意識して、「お互いにとっていいことだ」と考え、自分のコンディションにも気を配ってくださいね」
例えば、LINEなどで突発的に重い話を打ち明けられたとき。その場合も、返信することでネガティブ思考に陥りそうであれば、「今、手が離せないことがあるのだけど、きちんと返信したいから、改めて返信するね」など、真摯に気持ちを伝えながら、タイミングを調整するのもいいですね。
<ママ友づきあいについての関連記事はこちら>
ママ友がいないとダメ?子どもに影響はある?小学校でのママ友の作り方
【方法③】自分の気持ちを紙に書き出す
「人と会ったり、話を聞いたりして疲れたな、落ち込んでいるなというときはあえて、自分の気持ちと向き合い考える時間を作りましょう」
例えば、つらい気持ちを紙に書き出してみて、「なぜそう感じているのか」など、過去の経験なども紐づかせながら考えていくと、気持ちを整理しやすくなるそうです。
「(近江さん)もし、考えるのもつらいなら、目を閉じて横になるなど、意識して自分を休ませる時間をつくってください。もし、そのまま眠れるなら寝てください。睡眠や栄養は心を整えるために必要なものです。実際に睡眠時間をたっぷりとって、朝、日光をいっぱい浴びるだけでも気持ちは変わります。
また、寝ている間に脳は記憶を整理するので、起きた時にちょっとスッキリしているはず。もし、昨日の話についてもう1回考えたかったら考えればいいし、忘れてしまえるのであれば考えなくていいですよ」
【方法④】スイッチをオフにする行動を
眠ること以外にも、お風呂に入ったり、好きなものを食べたりなど、気持ちを切りかえる行動をするのもいいそう。
「疲れているときやしんどいときは、自分を休ませて、甘やかしていいんです。ストレスや感情はコップの中の水のようなもので、増えすぎて溢れかえってしまうと疲れてしまいます。常にコップの水が低い位置でキープできていれば、人と会ったり話を聞いたりしたストレスで水が注ぎ込まれても溢れることはありません。
だからこそ、つらいとき、しんどいときだけでなく、自分を整えるためにスイッチをオフにする行動は常日頃から重要ですよ。頑張り過ぎないでくださいね」
特に、他人への共感であれば、会わない時間も多いので切りかえやすいですが、家族への共感となるとそうはいきません。長期戦で向き合わねばならない人間関係なので、スイッチをこまめにオフにする行動を意識的にとり、心を休ませることが重要になるそうです。
あなたの悩み・つらさをカウンセラーに相談できます
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上でカウンセラーに悩みを相談できます。
相談相手を探してみる
共感疲れには体調管理も重要
ここまで、エンパスかもしれない人、特に「共感疲れを起こしやすい人」のタイプについて説明してきましたが、近江さんは、「人に共感すること自体は悪いことではありません」と話します。
「共感する点がポジティブなことなら、共感しても疲れることはないと思います。むしろ、元気をもらえることでしょう。ですが、ネガティブなことに共感していると、相手や周囲が抱えているストレスも一緒に吸収をしてしまうことで疲れてしまうのです」
では、ポジティブな話にだけ気を配るようにすればいいかというと、そうではないとのこと。
「例えば、ママ友と話しているとします。相手ママにとっては『うちの子にこんなに良いことがあってね』というポジティブな話でも、聞く側のママが『相手の子は良いのに、うちの子はダメだ』と比べて苦しくなるなど、自分の中のネガティブな感情や思い出を引っ張ってきてしまうと疲れてしまいますよね。共感しているように見えて、相手の話を自分の話にすり替えてしまって疲れているパターンです」
共感疲れの原因は、自分の中にあるのかもしれません。では、どうすればいいのでしょうか。
「ネガティブな気持ちや思い出を載せてしまうのは、本人の性格や気質だけによるものではありません。その日の天候や体調、ホルモンバランスの変化など、自分ではコントロールしにくい要素も関わっています。元々、共感力が高過ぎる人の中でも、『今日は疲れてしまうけれど明日は大丈夫』など、疲れる度合いの差はあると思います」

エンパスであること、共感できることはひとつの才能
今回の記事では、今回の記事ではエンパスと共感力について、エンパスの定義、特徴、共感力が強すぎる人の悩みの解決方法などについて解説しました。
共感することでつらくなることもあるエンパス。共感力がネガティブに捉えられがちですが、近江さんは「他人のことを大切に思い、共感することができるのは、誰にでもできることではありません。すごいことですよ」と話します。
「例えば、相手のネガティブな話を聞いて、相手のつらさをイメージできる人は、その背景に自身のつらい思い出や経験があるからだと思います。そうやって他人に寄り添うことや、周りの人の話を聞いて疲れ過ぎる自分をダメだなんて思う必要は、まったくありません。共感できることはあなたの良さ、強みなんだと思ってくださいね」
共感しすぎてつらいときは、今回の記事で紹介したような対策方法を試してみたり、必要があれば誰かに相談したりして、”共感できる才能”とうまく付き合えるよう、意識してみましょう。
「相談相手には、私たちのようなカウンセラーもいます。気持ちのコントロール法を一緒に考えるだけでなく、抱えている気持ちや考えがうまく話せなくて、『とにかくしんどいです』という段階からお話を聞いていくこともできます。せひ、気軽に相談してくださいね」
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

エディター、ライター、環境アレルギーアドバイザー。新聞社勤務を経て、女性のライフスタイルや医療、金融、教育、福祉関連の書籍・雑誌・Webサイト記事の編集・執筆を手掛ける。プライベートでは2児の母。