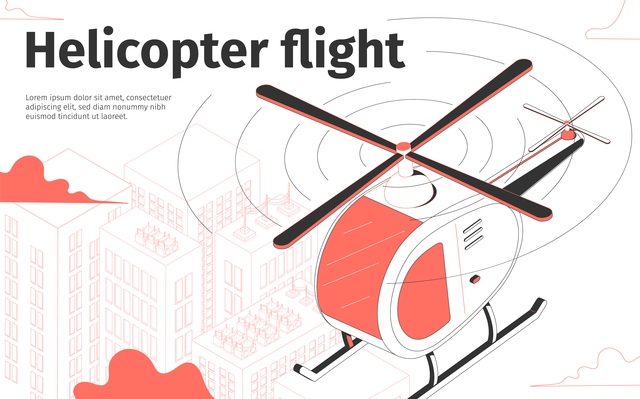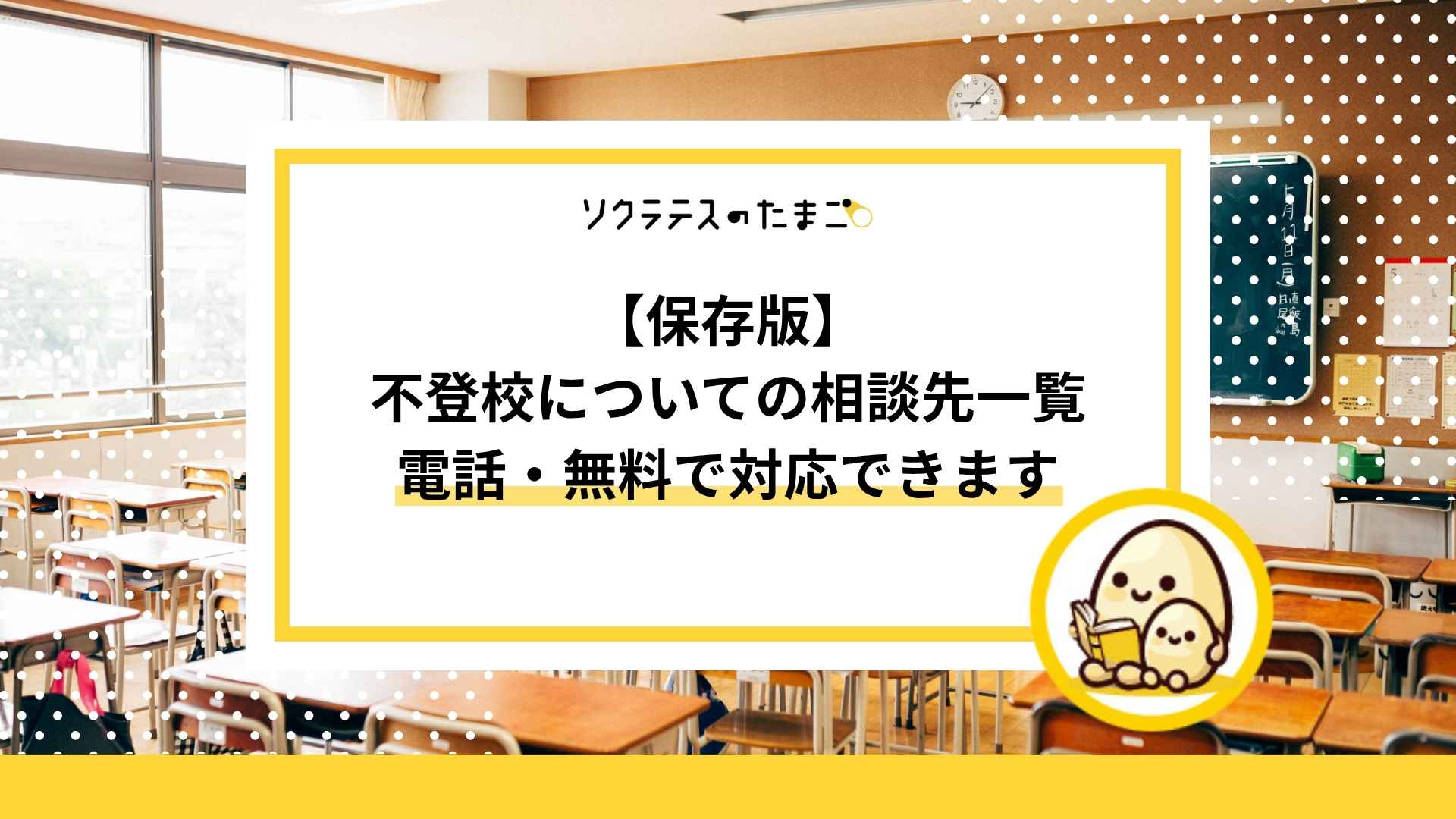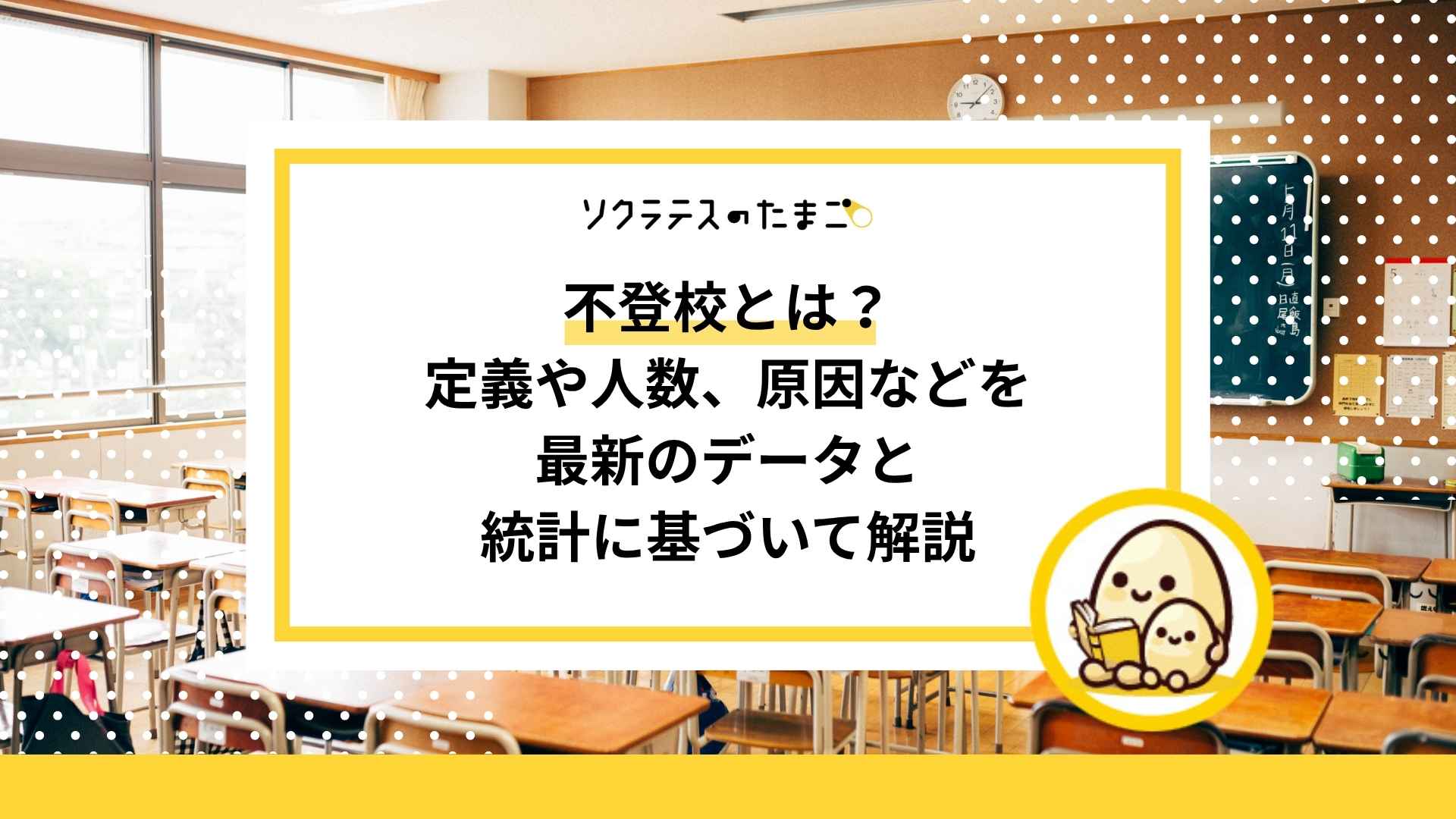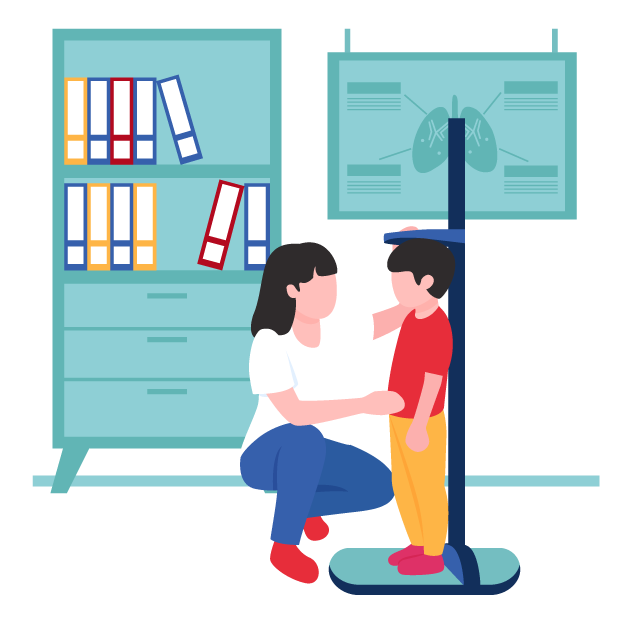母子分離不安とは?原因は母親のせい?子どもが抱く『不安』の年齢別の特徴や行動例、対処法も解説

母子分離不安とは、母親(=愛着対象、母親に限定されません)と離れることに対し不安を感じることです。どんな時に、どうして不安になるの?母子分離不安になるのは母親のせい?発達障がいとは関係ある?公認心理士の鈴木こずえさんが、母子分離不安を含めた子どもの『不安』に関して、原因や年齢別の特徴、子どもを傷つけずに状況を改善していく対応について解説します。
<今回の悩み相談>
元々、親子仲はいいほうなのですが、小学6年生の息子が最近、特に甘えてくるようになりました。抱き着いてくることがあれば、「一緒に寝たい」「一緒にお風呂に入りたい」と言ってきます。思春期の男子の言動として違和感があり、ネットで調べてみると「母子分離不安」という言葉が気になりました。
不登校の原因にもなるようで、このまま息子の言うまま甘えさせてよいものか悩んでいます。そもそも息子が「母子分離不安」になったのは、私の愛情が足りなかったり、過干渉過ぎたりしたからなのでしょうか?(小6男子の母)
目次
高学年や中学生でも母子分離不安はある
「おもに乳幼児期から小学校低学年までの子どもに多いといわれている母子分離不安ですが、高学年や中学生でも分離時に不安を感じたり、母親に対して依存的な態度をとったりすることがあります」と話すのは、公認心理士の鈴木こずえさん。自治体の教育相談センターで子育て・発達相談などを行っており、母子分離不安の親子にもたくさん出会ってきました。
「そもそも、母子分離不安とは、一番身近な存在である親から離れることに不安を感じることで、小さなお子さんであれば、どんなお子さんでも持つ自然な感情です。でもそれが非常に強くなると、日常生活に支障をきたしたり、苦痛を感じたりするようになり、下記のような状態や、時には赤ちゃん返りのような行動を取ることもあります」(鈴木さん、以下略)
母子分離不安の子どもの行動例
母子分離不安は、子どものどのような行動や症状として表れるのでしょうか。まずは具体的な子どもの行動についてチェックリスト形式で見てみましょう。
わが子をチェック!母子分離不安の行動例
- 親と離れたり、離れる場面を想像したりすると強い不安に襲われ、登園登校、外出、友達との遊び、留守番、就寝などの行動をひとりで行えなくなる
- 親と離れたり、離れる場面を想像したりすると強い不安に襲われ、継続すると体の不調を訴え、頭痛・腹痛・嘔吐などの身体症状が出る
- 母親や父親に対して年齢に合わない過度なスキンシップを求める
例:親へ抱きつく、親と一緒に入浴する、同じ布団で寝るなど
「このような行動や症状が現れるのは、その強い不安を和らげるため、乳児期の頃のように、お母さんのそばで安心感を得ようとしているからです。そして、実際に安心感が得られることもありますが、様々な要因から得られないこともあり、そうするとますますお母さんから離れられなくなり、上記のような行動が持続します」
また、母子分離不安が強く出たり、状態が悪化したりするのは、新しい場面や状況に直面しストレスを受けたときが多く、入園や小学校入学時、学年の変わり目、下の子の誕生、転居、ペットの死など、環境に変化があったときに出やすいそうです。ただ、一か月程で落ち着いてくる一過性のことがあれば、長く続く場合もあるとのこと。
「相談者の方も、お子さんがそのような言動をとったときを思い出してみてください。環境の変化からお子さんが不安を感じるような状況だったのであれば、安心感を求めて母子分離不安のような症状が出ていたことが分かります」
あなたも鈴木こずえさんに相談してみませんか?
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、鈴木さんにあなたの悩みを直接相談できます(秘密厳守)。
鈴木こずえさんへの相談はこちらから
母子分離不安は母親のせい?発達障がい?原因を解説

しかし、新しい場面や環境で不安を感じる人は少なくありません。不安を感じやすい子には、ほかにも要因があるのでしょうか。
1.子どもの性格や体質
「情緒性・社会性・活動性はお子さんのもともとの気質が関係していると言われています。情緒の安定性の低さやストレス耐性の低さ、刺激への弱さなど、不安を感じやすいタイプのお子さんです。環境の変化や母親との関係がほかの子と同じようであっても、強い不安を感じるため、母子分離不安になりやすい傾向があるでしょう」
「たとえば乳幼児の場合、1歳半健診では、初めての場所で知らない人に会わなければなりません。泣きながら入室しても、玩具にすぐに気付き遊び始める子、お母さんに抱っこされながら少し周りの様子を見て、それからお母さんから離れて遊ぶ子、退出までお母さんから離れられず元気よく泣き続ける子などさまざまです」
「ほかにも、お子さんによっては暗いところから急に明るい所に移った時、温かい場所から急に冷たい場所に移った時など、感覚刺激の変化に不安や恐れが生じることもあります(発達特性のあるお子さんの中にも感覚的過敏過鈍があります)」
2.子どもの発達障がいの特性
ほかにもASD傾向がある子どもの中には、見通しが持ちにくかったり、記憶が薄れなかったりすることで、不安になりやすいという特性がある子もいるそうです。
「誰でも一度は”失敗”をした経験があるのではないでしょうか。多くの人はそのときは傷ついても、その後、記憶が薄れていきます。しかし、ASDの特性のひとつに、失敗経験の記憶が薄れずに鮮明によみがえり、似たような場面になると強い不安が呼び起こされるというものがあります」
「誰からもフォローがなく失敗体験を繰り返してしまうと、「また何か失敗するのではないか」という不安だけが強くなり、自己肯定感が下がり自信を失くし、ひとりでの活動・外出などができなくなっていくこともあります」
「不安は放置するとどんどん大きくなっていきます。早い段階で、適切に対処する方法を学び、不安をコントロールできるようになることが大切です」
3.母親の愛情不足や過干渉
母親の過干渉や甘やかし、母親自身の不安になりやすい性格などが、母親と子どもの関係に影響を与え、依存的傾向を生み、母子分離不安を強くする場合もあるようです。
「原因が、過干渉や甘やかしだとしても、『じゃあ、子どもと距離置けばいい』という単純な話ではありません。『なぜ甘やかしてしまうのか』といった母親の中にある原因を考えましょう。
例えば、過去に自分が強制的に自立させられた経験があるなど、母親が育ってきた環境や実家との関係が影響していることもあります」
このような場合は、専門家が母親にカウンセリングを行い、一緒に考えていくのがよいそう。
「また、子どもの不安が強い場合、心配し過ぎて母親が子どもから離れることができず“共依存”のような関係になり、母子分離不安の状態を悪化させてしまうこともあります。その場合、母子がそれぞれカウンセリングを受け、関係を改善していく必要があります。母親の接し方が変わっていけば子どもの要求が変わっていくケースも少なくありませんよ」
あなたも鈴木こずえさんに相談してみませんか?
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、鈴木さんにあなたの悩みを直接相談できます(秘密厳守)。
鈴木こずえさんへの相談はこちらから
年齢別に見る発達と不安の特徴
子どもの年齢によって、不安の原因や表れる行動に違いはあるのでしょうか。年齢別の発達段階の特徴と合わせて教えていただきました。
乳児期の特徴
「1歳後半から2歳前半にかけて「恐れ(怖いという感情)」が増大します。自我が誕生し大人からの働きかけによって自我を拡大させていく過程で、様々な新しい物事に出会い、挑戦していく時期です。その時に不安や恐れを感じるのです」
「また記憶に関して、前に会った人や行った場所を思い出せるのは、1歳後半で2~3週間、2歳前半では2~3か月の期間と言われています。一度行ったことがあるから”大丈夫”ではないのです。お子さんによって不安を感じる強さは違いますが、心理的な不安定さや防衛的機制が強まる時期であること知っておくとよいでしょう」
乳児期の行動特徴
お母さんへのしがみつき、泣き続ける、夜泣きなどがあります。
幼児期の特徴
「保育園や幼稚園に通い始め、初めて家族から離れて集団生活を送る時期です。自我が充実し自己主張が強くなります。それと同時に他者受容もできるようになり、そのバランスをとることの難しさも学びます。自制心の基礎が作られる時期でもあり、自制心が生まれると相手の気持ちに気づくようになります」
「お母さんや先生の期待にうまく応えられない自分に傷つき、すねたり癇癪を起こしたりすることがあります。幼児期は、上手くできなかった気持ちを受け止め、気持ちを立て直すきっかけを与え、温かく応援する配慮が特に必要な時期です」
幼児期の行動特徴
不安の強い子どもの中には、外で話さなくなることがあります(場面緘黙など)。心配になるかもしれませんが、焦らずに安心できる人や場所を増やし、小さな成功体験を積んでいくことが大切です。
小学校低学年の特徴
「入学により環境の大きな変化に直面します。集団の規模も大きくなることが多いでしょう。そのような中で母親と離れて過ごす時間が増えて、不安な気持ちが強くなることがあるでしょう」
小学校低学年の行動特徴
入学式にお母さん(お父さん)から離れられず出席できない、一人で教室に入れない、初めての行事(小学校で初めて行われるものを含む、例:運動会など)に参加できない、などがあります。
小学校中学年~高学年の特徴
「母親とは離れて、友達と協力して多くの問題解決に取り組まなければならない時期です。人前で上手く話せない、発言や発表時に過度に緊張してしまう、など困りごとが増え、それを避けてしまうことで益々不安が強くなっていきます。不安対処スキルを身につけていくことが大切な時期です」
小学校中学年~高学年の行動特徴
朝起きられなくなる、暗闇・面前など特定の場面を怖がる、などがあげられます。頭痛、腹痛、嘔吐など身体症状にでることも多いです。
中学生の特徴
「思春期になり、自己を正しく理解する難しさに直面する時期です。過大、過小評価がみられがちです。自分の所属する集団の中で仲間意識を強め、そこで安心感を得てアイデンティティを形成していきます。対人面での躓きや、そこでの関係修正が難しくなると、集団に入ったり相手と関ったりすることに恐怖を抱くようになり、逆に家族(母親など特定の人)との密着度が増すことがあります」
「また中学に入り、活動スピードが上がり、やらなければならないことが増えストレスが高くなることも原因の一つと言われています。夜眠れない、食欲がないなど、今までと違った様子が見られないか注意が必要です。強迫症、社交不安症などは医療機関との連携が必要になります。専門家に相談できるとよいでしょう」
中学生の行動特徴
人目が怖い、人と話すことが怖い、家族と一緒でないと外出できない等の訴えが多くなります。
親ができる母子分離不安や不安への対処法

それでは、今回の相談のように子どもに母子分離不安のような症状がある場合、どのように対応していけばよいのでしょうか。
「ひとことで母子分離不安といっても、背景にあるものによって適切な対応は変わっていきます。ですが、下記のようなことはどの子に対しても心がけたい対応です」
母子分離不安の子への対応
- 子どもの不安をあおらない
- 子どもの気持ちを想像し理解する
- 子どもが安心できる時間、場所を作る
- 母親・父親など(養育者)が協力し、子どもに一貫した分かりやすい態度で接する
何度も「大丈夫?」と聞いてしまったり、無理やり突き放したりするのはNG。また、「いい加減にして」と言って突き放すなど、感情的に接して子どもを傷つけないようにしましょう。今回の相談にある「一緒に入浴したがる」などの年齢にそぐわない要求には「〇〇生だから別に入ろうね」と優しい口調で、でもはっきりと伝えましょう。
「ただし、要求を断るときは、『あなたのことが嫌いだから断るわけではない』ということを伝え、子どもの気持ちを傷つけないことが前提です」
子どもの要求のすべてを拒否するのではなく「一緒の布団で寝たい」という場合は、「同じ布団ではなく、一緒の部屋では寝るのはどう?」など、子どもの気持ちに歩み寄った上で線引きをするのもいいそう。
行き渋りや不登校なら学校との連携も必要
母子分離不安がある子の中には、学校へ行き渋ったり、不登校になったりする子もいます。
「母子分離不安で学校に行けないような場合、まずは母子分離不安があることを学校側に伝えて、”最初は母子で登校して母親が廊下から見守る”などの対応ができないかを相談をしてみてください」
<母子登校に関する記事はこちら>
母子登校はいつまで続く?「やめたい」と言えない親の負担を軽くする方法
最初は母親がいるという安心感が支えになっていますが、徐々に学校やクラスの中に安心できる人(友達や教師など)、安心できる場所(保健室や図書室など)が見つかっていくと、不安が軽減されていき、ひとりで学校生活が行えるようになっていくことが多いそう。
「時間はかかるかもしれませんが、少しずつスモールステップで行うことが大切です。行き来戻りつ、といった状態が続くこともありますが、達成感や自尊感情を育むことができるように長い目で成長を見守っていきましょう。また、お母さん自身を支える存在として、スクールカウンセラーも活用してくださいね」
「スクールカウンセラーは、子どもの状況やそのときの状態、変化を把握する上でも欠かせない存在」と鈴木さんは続けます。
「今回の相談にある子どもは小学生ですが、中学生になると不安があってもスクールカウンセラーに相談することをためらう子がほとんどです。人目のない時間に初回の面談は母子同席でなど、相談できるような配慮をしてもらい、子どもが安心して相談できる環境作りをお願いしてみるのもいいですね」

母子分離不安を相談できる専門家とは
学校以外にも相談できる場所や専門家がいます。
「先ほどもお伝えしたように、母子分離不安とは長期的に向き合っていく必要があります。スクールカウンセター以外に継続的なカウンセリングを考えているなら、教育相談センターや療育・発達相談センターなど、自治体が設置している相談機関を利用してみてください」
頭痛、腹痛、嘔吐などの身体的な症状もあれば、医療機関(心療内科、児童精神科など)の受診も検討してみる必要もあるそう。
「医療の必要性があるかは、カウンセラーに相談してみてもいいですね」
また、教育センターや医療機関では、母子並行のカウンセリングが可能。子どもに対しては、プレイセラピーや認知行動療法を行い、保護者向けのカウンセリングでは、不安や苦しい思いに対して共感的に話を聞いて、子どもの自立(不安をコントロールする)、保護者の自立を支えていく(子どもの自立を喜べるように、子どもの手を離せるように)ためのサポートを行ってくれるそう。
「母子分離不安で辛いのは、今後の方針や見通しが立たないことだと思います。専門家に相談することで子どもの状態を正確に見立てることができれば、今後の方針が立てられ、見通しがつきます。ぜひ、相談をしてみてください。
もし、どんな風に相談すればいいのか分からない、自治体へ相談に躊躇するという場合、一度『ソクたま相談室』を経由して相談をしてくれれば、個別のアドバイスもさせていただきます」
あなたも鈴木こずえさんに相談してみませんか?
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、鈴木さんにあなたの悩みを直接相談できます(秘密厳守)。
鈴木こずえさんへの相談はこちらから
母子分離不安は家庭で抱え込まないで
「赤ちゃんの頃から育ててきた母親が子どもを心配に思うことも『守りたい』と思うことも自然なことです。相談者さんのように『過保護』『甘やかしすぎ』と自分を責めてしまうかもしれませんが、父親の高圧的な態度が子どもの不安を強めて、母親との密着度を高くしている場合もあります。母親だけが悪いということはないのです」
「状況が改善していくまでには時間がかかるかもしれません。ですが、少しでも早く子どもと向き合うことで未来は変わっていきます。”子どもを自分から引き離す”のではなく、”子どもの自信を育てていき不安をコントロールできる子になる”ように、専門家と一緒にがんばっていきましょう」
あなたも鈴木こずえさんに相談してみませんか?
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、鈴木さんにあなたの悩みを直接相談できます(秘密厳守)。
鈴木こずえさんへの相談はこちらから
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

エディター、ライター、環境アレルギーアドバイザー。新聞社勤務を経て、女性のライフスタイルや医療、金融、教育、福祉関連の書籍・雑誌・Webサイト記事の編集・執筆を手掛ける。プライベートでは2児の母。