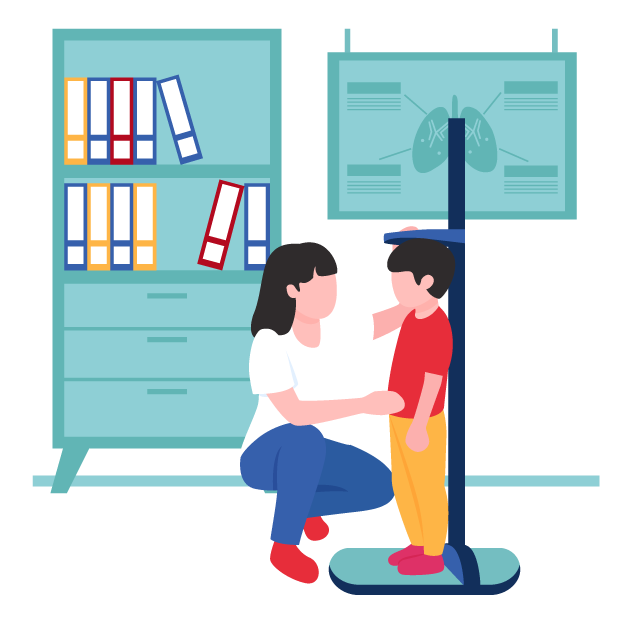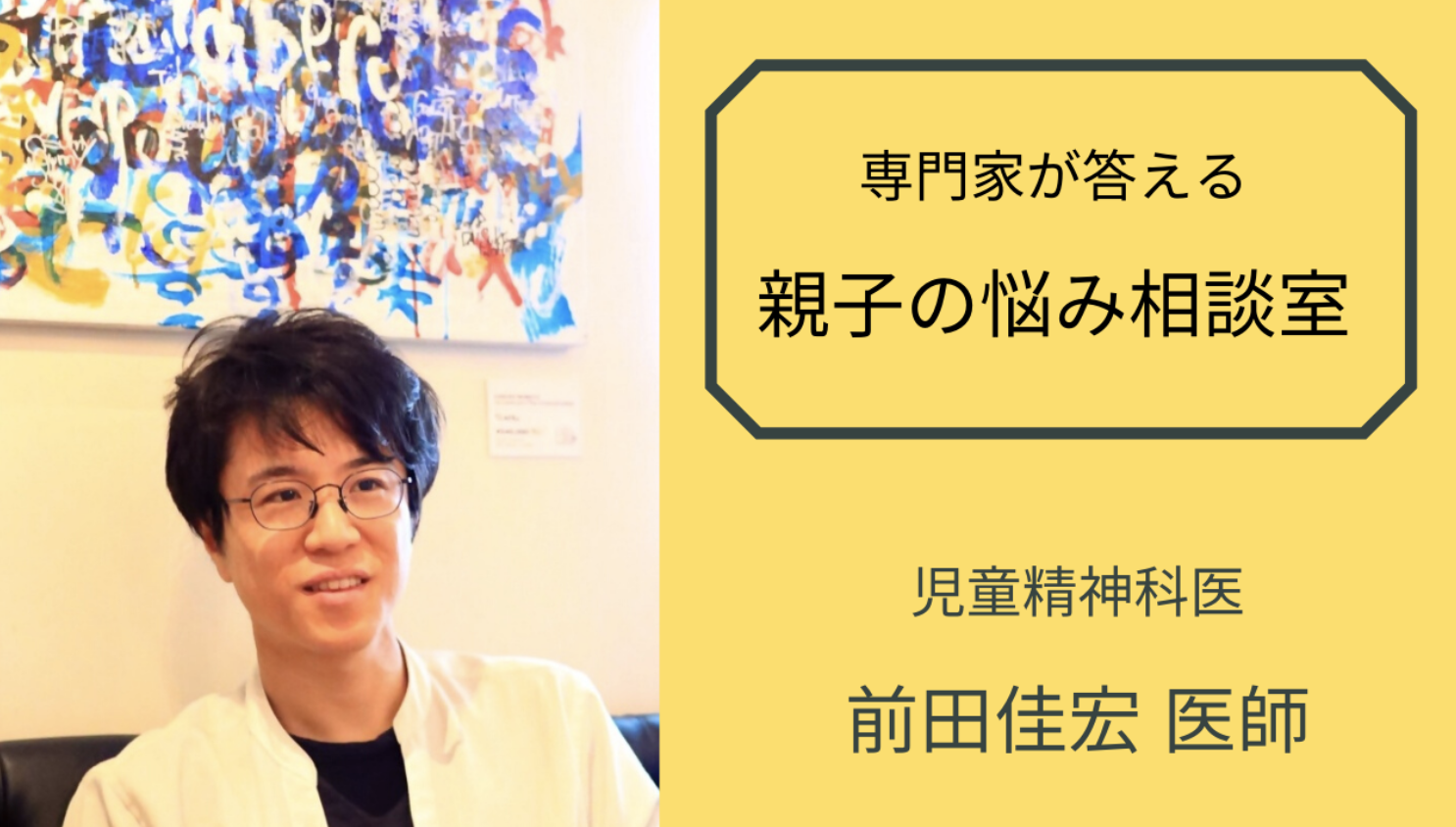HSCは病院に行くべき?セルフ診断の注意点や活かし方を精神科医が解説

人一倍敏感で繊細な気質の子どもを指すHSC(Highly Sensitive Child)。「うちの子、HSCかも?」と思ったとき簡単に試せるのが、セルフチェック診断です。その結果はどう扱えばいい?当てはまる場合は病院に行くべき?気になる点について精神科医の前田佳宏さんに解説してもらいました。
目次
HSCとは?定義と4つの特徴
HSCの定義
HSCとは、Highly Sensitive Child(ハイリー・センシティブ・チャイルド)の略称で、生まれつき感覚が鋭く、刺激に敏感な子どものことを指します。HSCの子どもたちは、周りの環境の変化や刺激に敏感に反応し、感情の起伏が激しいことがあります。また、繊細で共感力が高く、想像力が豊かな傾向があります。
一方で、繊細で感受性が豊かな大人のことをHSP(Highly Sensitive Person)といいます。
HSC、HSPともにそれほど珍しい気質ではなく、5人に1人はあてはまるといわれています。
▶関連記事:HSCの特徴や発達障害との違い
敏感な気質を持つ子どもの4つの特徴
HSCの子は「DOES」という4つの特徴を持つとされています。
| D…Depth of processing(深い処理) | HSCの子どもは、情報を深く処理する傾向があります。 |
| O…Overstimulation(過剰刺激) | 刺激に敏感なため、環境の変化に影響を受けやすくなります。 |
| E…Emotional responsiveness(感情反応) | 喜怒哀楽の感情表現が豊かで、共感力が高いです。 |
| S…Sensitivity to subtleties(細部への敏感さ) | 細かいニュアンスや変化に気づく敏感さを持っています。 |
▶関連記事:HSCの4つの特徴「DOES」
HSCは病院に行くべき?診断してもらえる?
HSCは医学的な診断名ではありません。そのため、病院で診断してもらうことはできません。
しかし、子どもの感受性の高さに悩んでいる親御さんは、児童精神科医や心理カウンセラーに相談してみるといいでしょう。専門家から、子どもの特性を理解し、適切な関わり方についてアドバイスをもらえます。HSCの特性を踏まえた子育てを心がけることで、子どもの健やかな成長をサポートしやすくなります。
セルフ診断はあくまで主観によるもの
HSCのセルフ診断で代表的なものといえば、HSC/HSPの提唱者であるアメリカの心理学者エレイン・N・アーロン博士による下記のセルフテストです。チェックリスト形式になっていて、例えば以下のような項目があります。
【HSCセルフテスト項目の一例】
| 項目 | 当てはまる場合にわかること |
|---|---|
| 「うるさい場所を苦にする」 | 感覚の鋭敏さを測る項目で、周囲の刺激に敏感に反応する特性があるかどうかがわかります。 |
| 「他人の苦しみによく気がつく」 | 共感力の高さを測る項目で、他者の感情を敏感に感じ取る特性があるかどうかがわかります。 |
| 「大きな変化にはうまく対応できない」 | 慎重さや適応力を測る項目で、新しい環境への適応に時間を要する特性があるかどうかがわかります。 |
しかし、セルフ診断ってどう捉えていけばよいのでしょう。
そもそも、セルフ診断(自己診断)と医師や心理士などの専門家による診断の違いは、主観によるものかどうかです。
セルフ診断には、どうしても主観が入ってしまいます。質問の内容にどの程度当てはまれば“YES”とするのか、その境目は自己判断。「うちの子はHSCかもしれない」と思って行うのか、それとも「HSCではないだろうな」と思って行うのかによっても変わるものだと思います。
つまりセルフ診断は当てはまる項目が多いからといって、「うちの子はHSCに違いない!」と断定したり、当てはまる項目の多さでHSC傾向の強さを測ったりできるものではありません。
「うちの子には、HSCの傾向があるのかもしれない」程度のことが分かる程度のものだと考えてよいでしょう。
大切なのはセルフ診断をどう活かすか

なぜセルフ診断を行ったのかを考えよう
大事なのは、HSC・HSPだと判断すること自体ではなく、HSC・HSP傾向があるという結果を今後にどう生かしていくのかということです。
そもそも、セルフ診断を行ったのは、何か気がかりなことや困りごとがあったからだと思います。「HSC傾向がある」と分かったからといって、その困りごとが解決するわけではありません。
では、どうすればセルフ診断の結果を実生活に生かしていくことができるのでしょうか。
セルフ診断を活かしたアプローチ方法
例えば、セルフ診断を行った理由が、“わが子の育てづらさ”にあるならば、HSC傾向がある、ということで終わりにするのではなく、HSCというものを親自身が学び、子どもを分析したり、理解したりすることに役立てみてください。
HSCの特徴には、“疲れやすい”ということがありますが、「うちの子はHSC傾向があるから疲れやすいのかもしれない」という可能性は考えられますよね。本人の意思や努力で変えることができない“疲れやすさ”なのであれば、アプローチは生活習慣や体力づくりに口うるさく言うことではなく、疲れたときにどう対処していくかということになります。一般論や親の価値観ではなく、子ども自身の特性に合わせた生き方を考えるヒントになるのではないでしょうか。
子ども自身が改善を望む場合は専門家へ相談
では、学校での生活に馴染めず、子ども自身が「自分はほかの子と何か違う」「どうにかして周りに合わせなければ」と苦しんでいる場合はどうでしょうか。
HSC傾向があることが分かって、「ああ、自分みたいな子(HSC)はいっぱいいるんだ。こういう特性があってもいいんだ」と思えるのであればいいのですが、もし、HSC傾向があるということを知ったうえで、実際にある“困りごと”や“できないこと”を改善していきたいと本人が望むのであれば、心理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
▶関連記事
・HSCと不登校の関係
・HSCの中学生が抱える悩み
この記事で回答している前田佳宏さんに相談してみませんか?
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で前田さんに子育ての悩みを相談できます。
前田佳宏さんへの相談ページを見てみる
セルフ診断をするときの注意点
病気や症状を過剰に捉えてしまう人もいますが、自己診断などをして「私はこういう病気に違いない」と思い込んでしまっている人もいます。詳しい検査をすると違っている場合もあるのですが、自分で過剰診断をしてしまうのはいいことではありません。
子どもがHSCだということが分かり、保護者が「この子は特性だから変わらない」「ほかの子とは同じようになれないんだ」と成長を諦めたり、子どもを見放すようなことはしないようにしましょう。子どもをカテゴライズやレッテル貼りするためのセルフ診断であればしないほうがいいと思います。悩みや問題の本質を見失ってしまいかねません。
HSCを医師に相談してもいいの?

HSCについて、医師に相談していいものなのか悩んでしまうかもしれません。ただ「うちの子はHSCなのでしょうか?治してください」と言われても医師は困ってしまいます。
受診をするときは、日常生活のどんなことに困っているのか、何に悩んでいるのかということを伝えてください。その際に「うちの子はHSC傾向があるようです」ということをお子さんの情報として加えてもいいですが、すべての医師がHSCを理解しているわけではないのが現状です。
HSCは病名ではないため、“ストレスを受けやすく生活に支障が表れている”ということから適応障害と診断されるかもしれません。その場合、認知行動療法などを用いて治療をしていくケースが多いと思います。
また、HSC傾向があり強いストレスを受けて二次障害(うつ病、精神症状、問題行動)が出ている場合は、症状に対して治療をしていくことになるでしょう。
なお、私はHSP/HSCを専門分野としていますが、神経系を落ち着かせる最新の治療をHSP・HSCに対して取り入れることもあります。
例えば「ソマティック・エクスペリエンシング(※)」という治療法や箱庭セラピーなど、体が過剰に反応してしまう事に対して、反応をうまく自分でコントロールできるようにしていくという治療です。
最近ではHSP・HSCは愛着のトラウマと関係があるのではないかという見方もあり、過去に“親など重要な他者の顔色を繊細に伺わないと生きていけない”と感じてきたことなどの影響があるのではないかといわれています。
ただし、これは親が何かをしたとか、愛情が足りなかったということではなく、たまたま子どもが親にいてほしいと思ったときにいなかったりとか、親が病気になったのを自分のせいに思っていたり、という場合もあります。
※ソマティック・エクスペリエンシング…身体の感覚に働きかけ、自律神経を整えて自己治癒力を高め、過去のトラウマによるさまざまな辛い症状を和らげる治療法のこと
HSC傾向がある子への接し方のポイント
HSC傾向のある子どもへの接し方で大切なのは、その子の特性を理解し、受け止めることです。
感覚が鋭敏で、感情表現が豊かなHSCの子どもたちは、周囲の刺激に敏感に反応します。そのため、穏やかで安心できる環境を整えることが重要です。たとえば、HSCの子どもは何気ない言葉でも強い意味に受け取り、自分を否定したり責めたりしてしまうことがあります。肯定的な声かけをする、きょうだいや友達と比較しない、といったことも大切です。
また、HSCの子どもは、自分の感情を上手に調整することが難しいことがあります。感情のコントロールを助けるために子どもの気持ちに寄り添い、共感的に接することが必要です。さらに、HSCの子どもは自分の特性を理解し、受け入れることで、自信を持って生きていくことができます。
周囲の大人が子どもの特性を肯定的に捉え、長所として認めて自己肯定感を高めてあげることが、HSCの子どもの健やかな成長につながるでしょう。
▶関連記事
・HSCの長所を伸ばす育て方のポイント
・HSCの10の特徴と接し方
HSCであることで良いことも
HSCの特性があることは、決して悪いことではありません。HSCであることがポジティブに作用することもたくさんあります。子育てで悩むこともあるかもしれませんが、一人で抱え込まず、周りの人や専門家に相談しながら、自分なりのペースで、自分なりのやり方で子どもに寄り添っていけば、将来その子に合った居場所がみつかると思います。最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
この記事で回答している前田佳宏さんに相談してみませんか?
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で前田さんに子育ての悩みを相談できます。
前田佳宏さんへの相談ページを見てみる
▶HSCの特徴やその子に合った接し方、対応について紹介した「HSC特集」はこちら
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

エディター、ライター、環境アレルギーアドバイザー。新聞社勤務を経て、女性のライフスタイルや医療、金融、教育、福祉関連の書籍・雑誌・Webサイト記事の編集・執筆を手掛ける。プライベートでは2児の母。