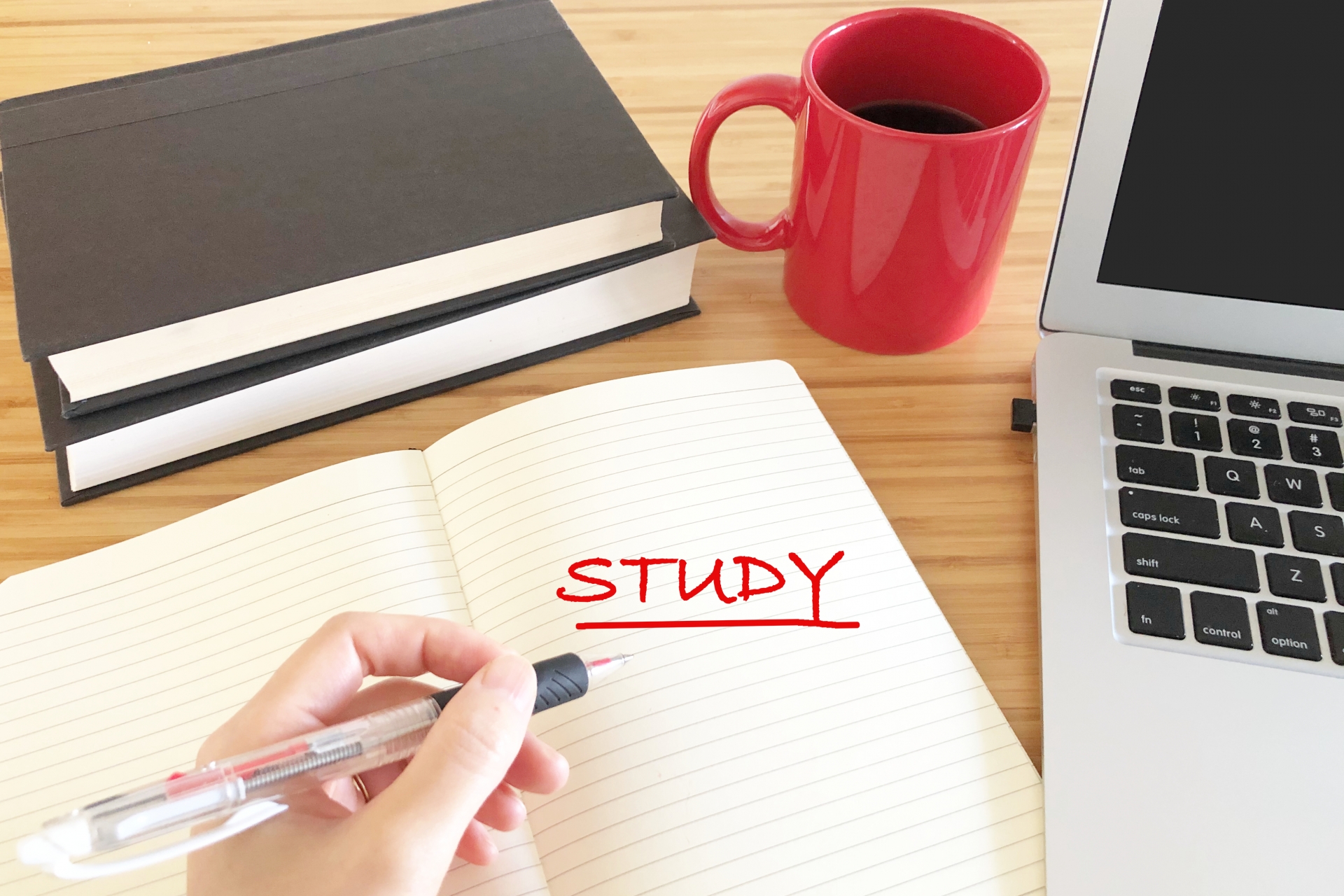自分の「怒りのタイプ」を診断してみよう/アンガーマネジメント連載 第1回
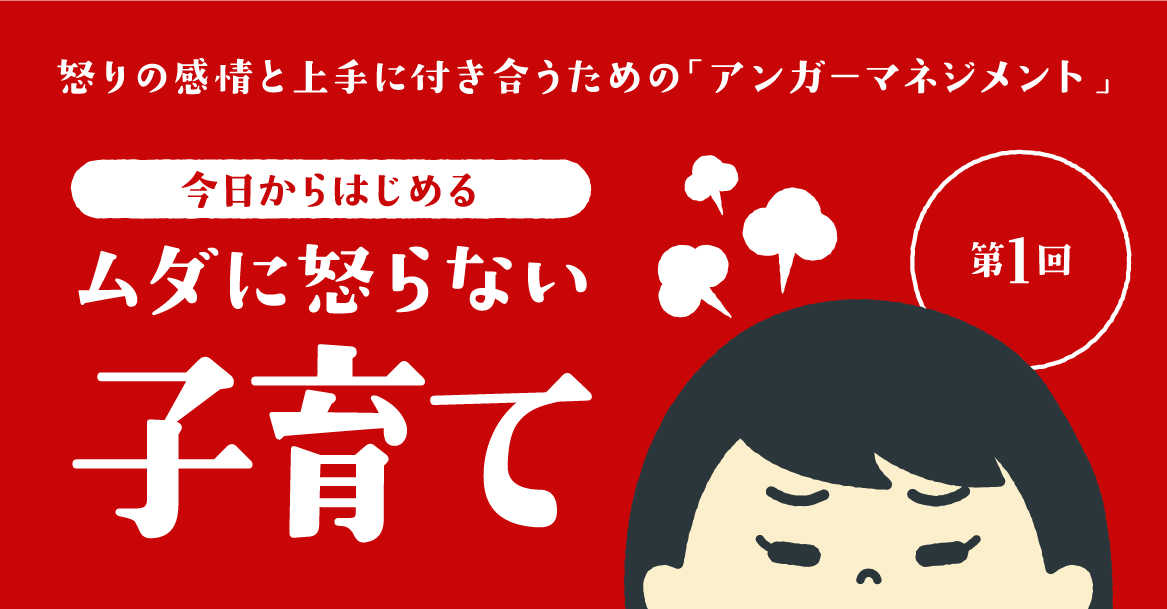
気づけば子どもを強い口調で怒ってしまう…。そんなあなたにおすすめなのが「アンガーマネジメント」。まずは、人によって違う怒りのタイプを「怒り診断テスト」で調べてみましょう。自分の怒りがどんなタイプか分かれば、怒りをコントロールしやすくなりますよ。
怒りに振り回されない体質になろう
「さっさとして!」「何度言ったらわかるの!」「いい加減にしなさい!」
朝からイライラ、エネルギーを使い、疲れてげんなり。怒りたくはないのに、つい怒ってしまって自己嫌悪。笑顔で子育てをしたいのに理想とはほど遠い日々…。そんな思いをしていませんか?
「このイライラを何とかしたい!」という人に役立つのが「アンガーマネジメント」です。アンガーマネジメントは、1970年代にアメリカで始まったとされるイライラと上手に付き合うトレーニング。子育てをやり直したい…そう思っている人は、ちょっと待って。諦めるのはまだ早いです。
イラッとしたときにとっさに対処できるテクニックから、ムダな怒りに振り回されずに済む怒りの体質改善まで今からできることがあります。
アンガーマネジメントはトレーニングです。身近な人、大切な人とより良い関係でいられるためにも、今日から一緒にトレーニングをしていきませんか?
それでは、レッスンスタート。
怒りは大人から子どもへ連鎖していく
怒りの感情についてどんなイメージがありますか?
怒りの感情はイヤなもの、悪いもの。怒ることはダメなこと、恥ずかしいこと…そう思っていたとしたら、それは誤解です。
怒りの感情そのものは、悪い感情ではありません。問題があるとすれば、怒りの感情に振り回されて暴言を吐いたり自分を責めたりモノに当たって後悔すること。多くの人が感じているように怒りは人間関係を壊してしまうくらいパワフルな感情です。
怒りは上から下へと、強いものから弱いものへと連鎖していきます。親から子ども、上の子から下の子、そして言いやすい子にぶつけていきます。
さらに怒りは身近な人にほど強くなる傾向があり、八つ当たりをしてしまうことも。怒りは悪い感情ではないのですが、家族や友人、職場の中で怒りの問題が起きてしまうと、居心地が悪くなり信頼も崩れ、安心して生きていけなくなります。キャリアを失うことだってあります。
また、子どもの怒り方は親や周りの大人のコピーになりやすいともいわれています。だからこそ怒りの取り扱いには気をつけないといけないのです。
【レッスン1】怒りの特徴を知る5つの質問
まずここで、ちょっとしたチェックをしてみましょう。次の項目をYESかNOで答えてみてください。自分自身、どんな怒りの特徴があるかが分かります。
- 1日に何度も怒ってしまう。【YES・NO】
- 思い出し怒りをしてしまう。【YES・NO】
- 強く怒ってしまう。【YES・NO】
- 怒ったときに、誰かを責めたりモノに当たってしまう。【YES・NO】
- 怒った後で自己嫌悪に陥り自分を責めてしまう。【YES・NO】
どうでしたか?
怒りの感情は悪くないといいましたが、それぞれの質問にYESと答えた人には下記の怒りの特徴があり、人との関係で問題となってしまうことがあります。
1は「怒りの頻度」が高く、しょっちゅう怒ってしまう。
2は「怒りの持続性」があり、忘れられない怒りがある。
3は「怒りの強度」が高く、一度怒ると止まらない。
4と5は「怒りの攻撃性」があり、他人を責めたり、自分を責めたり、モノに当たってしまう。
全部当てはまっているかもと落ち込む必要はありません。今日から変えていけばよいのです。安心してくださいね!
怒りの特徴に合わせた対策を取り入れよう
それぞれの怒りに合わせた対策を紹介します。
「怒りの頻度」が高い人は、何をしても楽しめなくなります。こまめに気分転換をしてみましょう。1人でできること、友人とできること、家族とできること、職場でできること…何ができそうですか?
「怒りの持続性」が高い人は、過去や未来を行ったり来たり。あの時もこうだった、今度会ったらどうしてくれようか…と恨み節。
そこで五感を使って“今”を感じるトレーニングをしてみましょう。好きなアロマの香りを嗅ぐ、モコモコの柔らかいクッションを抱きしめる、食べ物を味わって食べてみる…今この瞬間を感じられることを取り入れていくのがオススメです。
「怒りの強度」が高い人は、ONかOFFかで怒っています。怒りの感情には幅があります。本当のところ4ぐらいの怒りだったのにMAX10で怒ってしまったら理不尽になってしまいます。
イラッとしたとき、10段階で怒りを数値化できると冷静になれますし、自分の怒りを客観的にみることができるようになりますよ。
「怒りの攻撃性」がある人は、3つのルールを意識してみましょう。怒ってもいいのですが、他人を傷つけず、自分を傷つけず、モノを壊さずに怒っていることを伝えられると良いですね。
今日からできることを少しずつトレーニング。アンガーマネジメントにレッツトライ!
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会(東京)アンガーマネジメントファシリテーター。子育てや教育・福祉・司法関係において、心に触れる実践的なアンガーマネジメントを伝え、一人一人が大切にされる教育社会を目指して怒りの連鎖を断ち切るために活動を続けている。著書に「マンガでわかる怒らない子育て」(永岡書店)「イラスト版子どものアンガーマネジメント~怒りをコントロールする43のスキル」(合同出版)などがある。 https://www.angermanagement.co.jp/