勉強や登校へのモチベーションを取り戻してほしい……「朝起きられない」子に親ができることは?

「朝に弱い」という言葉がありますが、それは単なる体質とは限りません。中学生の約10%は、朝起きられない病気「起立性調整障害(OD)」といわれているようです。『起立性調節障害お悩み解消BOOK 「朝起きられない」子に親ができること!』では、ODの子どもとの関わり方や治療法などが詳しく解説されています。
「朝起きられない」は病気だった!?
2023年7月、株式会社翔泳社から『起立性調節障害お悩み解消BOOK 「朝起きられない」子に親ができること!』が発刊されました。
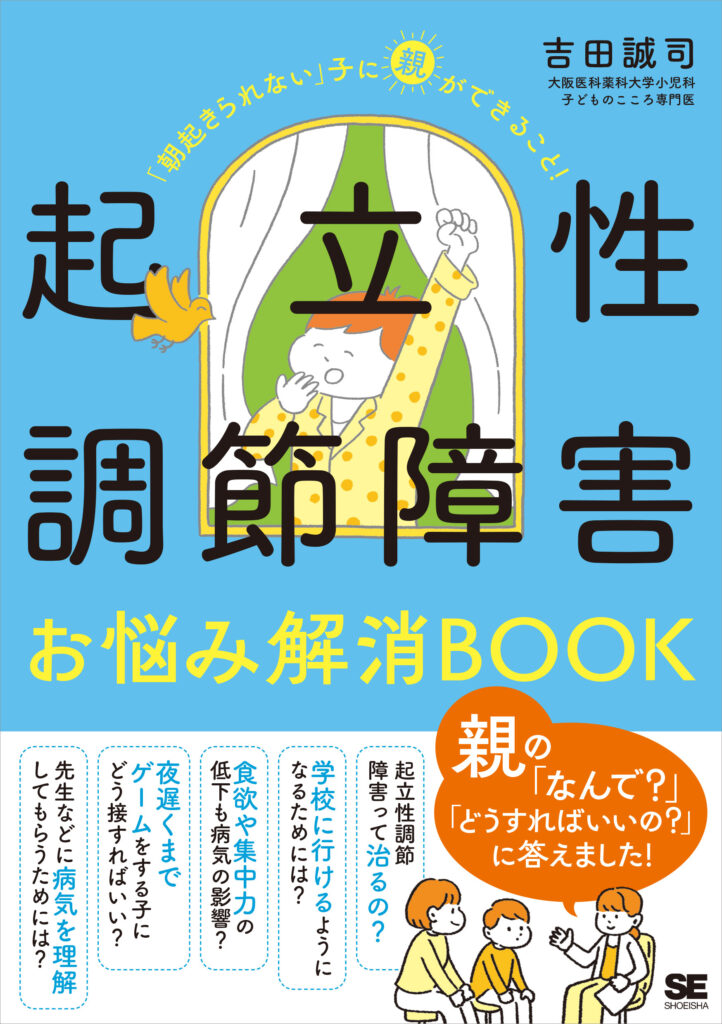
著者は吉田誠司さん。起立性調節障害(OD)について長年研究しており、書籍の出版はもちろん、各種メディアでも精力的に活動中の医学博士です。
起立性調節障害(OD)は、思春期によくみられる病気の一種。
特に中学生の発症率が高く、中学生の約10%が発症するといわれています。これってつまり10人に1人––– クラスだと3~4人はいる計算ですね。ちなみに小学生の発症率は5%です。
このようにわりと“当たり前”の病気であるにも関わらず、周囲の理解を得にくいのが厄介なところ。本人も朝の行動がつらいうえ、「夜もっと早く寝なさい」「やる気がないの!?」など叱責の対象になることもあるでしょう。
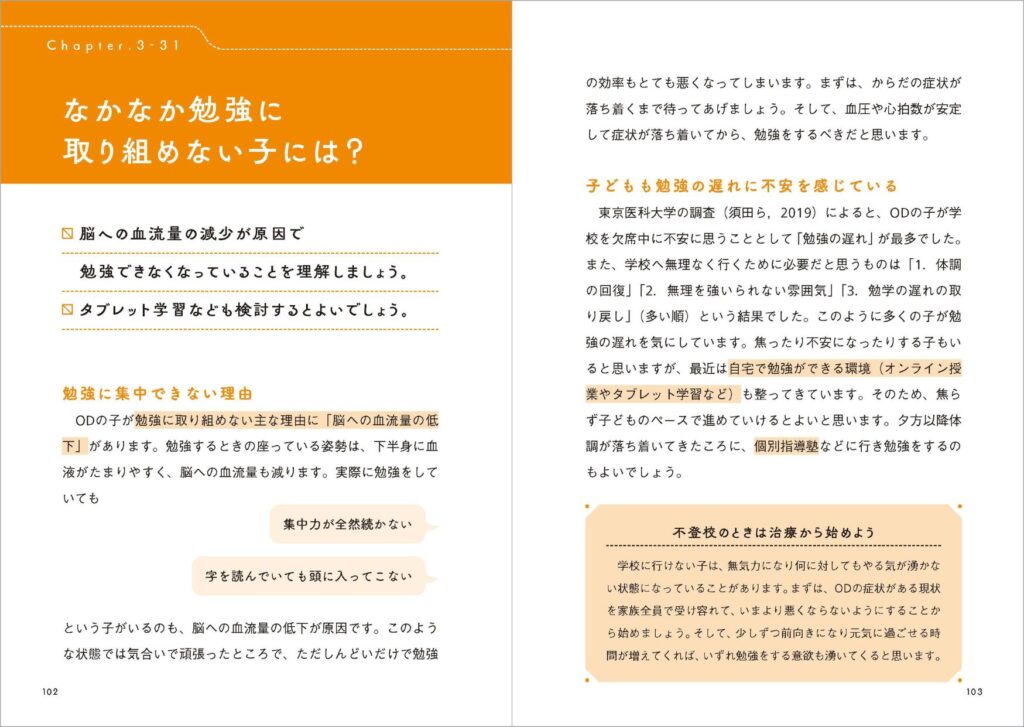
起立性調節障害(OD)の明確な治療法は、まだ確立されていません。そのため、改善には家族や学校など周囲のサポートが欠かせないそうです。具体的には、
- 規則正しい生活習慣(食事、睡眠、運動)
- 学校側の理解(先生との連携)
が大切とされています。
起立性調節障害(OD)のお子さんは、不登校になることも珍しくありません。朝が起きられない、あるいはどうにか起きても気分や体調が優れないと、「毎朝〇時〇分集合!」というイベント(学校)は苦行でしかないでしょう。
めまい、ふらつき、動悸。失神することも……
起立性調節障害には、大きく分けて4つの症状タイプがあります。「朝起きられない」だけではなく、体調に悪影響が及んだり、症状が重いと失神まで至ったりするケースもあるので注意が必要です。
起立性調節障害の症状タイプ
- 起立直後性低血圧 寝ている状態から立ち上がった時に低血圧になり、めまい、立ちくらみ、動悸が起きるタイプ。起立性調節障害の中でも最も多い症状。
- 体位性頻脈症候群 立ち上がると脈拍が上がってめまいやふらつき、頭痛などが起きるタイプ。
- 神経調節性失神 交感神経と副交感神経のバランスが崩れて急激に血圧が低下し、突然失神するタイプ。
- 遷延性起立性低血圧 起立した直後は問題はないものの、立ったままでいると数分後に血圧が少しずつ低下していくタイプ。失神してしまう場合もある。朝礼中などに倒れてしまうのがこのタイプ。
起立性調節障害を引き起こす原因は明確にはわかっていませんが、生活習慣に関わりがあるとされています。

1カ月以上もある夏休み期間、夜遅くまで起きていたり、運動不足になっていたりすると起立性調節障害を発症しかねません。夏休み中、あるいは夏休み明けに「起きられない」ということがあれば、『起立性調節障害お悩み解消BOOK 「朝起きられない」子に親ができること!』を読んでみては?
「やる気がないだけでしょ」「嘘ついてもダメよ」など親から叱責されていると、子どもがストレスや劣等感を抱えてしまいます。頭から決めつけて叱らないようにしたいですね。

「朝起きられない子」に対しては、勉強や登校へのモチベーションを疑ってしまいますが、実はメンタルの問題ではなく病気が原因かもしれません。
起立性調節障害は、成長しても完治するのは半数程度だそうです。「自分はダメな人間なんだ」と自己否定につながりかねないので、お子さんの状況に心当たりがある方は、かかりつけの小児科でまずは相談してみてくださいね。
<参考資料>
・PR TIMES(翔泳社)
・ソクラテスのたまご
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!






















































