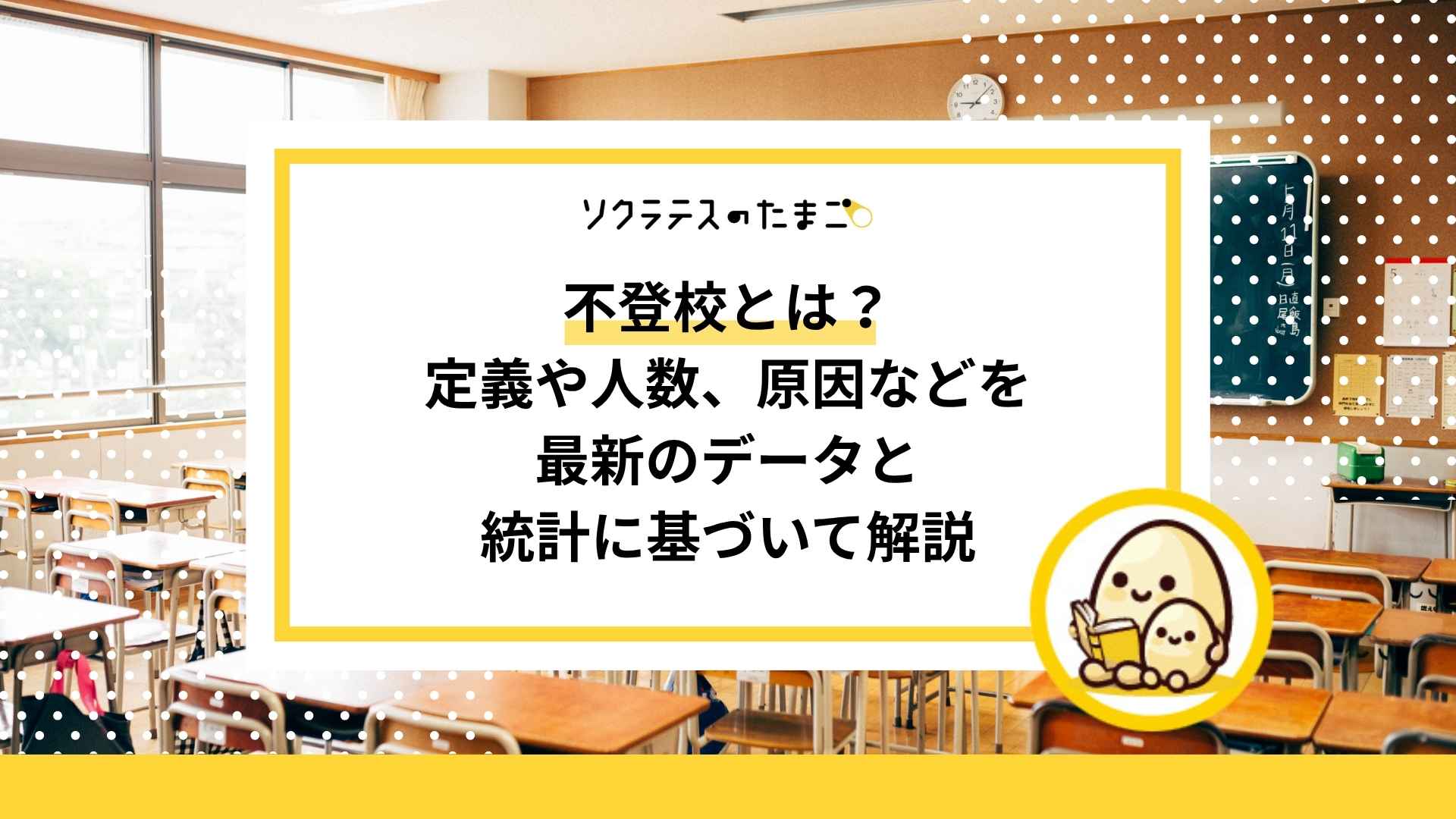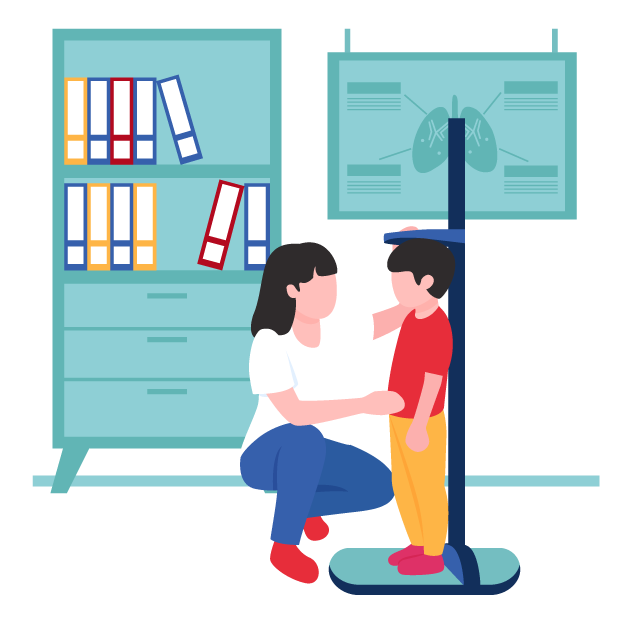夏休み明け、不登校のサインや原因、親の対応を3人の専門家が解説【相談先も紹介】
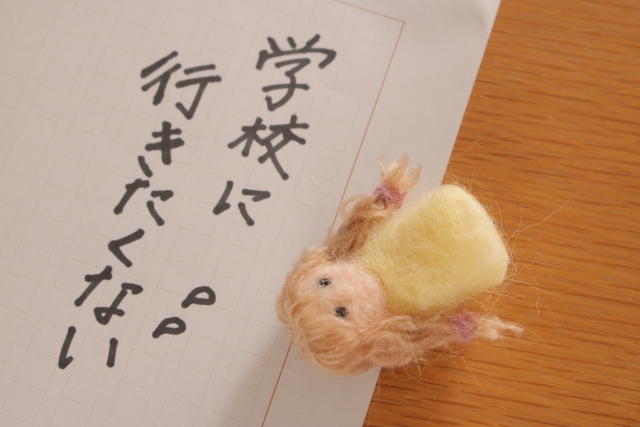
夏休み明けは、子どもの生活が大きく変化する時期。暗い顔をして学校の準備をする子ども、登校しぶりの子どもを見て不安になっていませんか?そこで、元教員や不登校支援の専門家が、登校への違和感を覚えたときの親の対応を解説。悩んだときの相談先も紹介します。
目次
夏休み明けは不登校の子が増える?
長期休暇中の生活からもとの学校生活に戻る夏休み明けは、子どもにとって、生活リズムや環境が大きく変化するタイミングです。
「夏休明けに不登校の子が増える」という明確な調査結果はありませんが、文部科学省では、子どもにとって長期休暇明けは以下のような時期であるとしています。
学校の長期休業の休み明けの直後は、児童生徒にとって生活環境等が大きくかわる契機になりやすく、大きなプレッシャーや精神的動揺が生じやすいと考えられる。
引用:文部科学省「平成27年版自殺対策白書(抄)」
また、同報告によると「過去約40年間の日別自殺者数をみると、夏休み明けの9月1日に最も自殺者数が多くなっている」という深刻な調査結果もあります。約1ヶ月間の長期休みを挟んだ夏休み明けはそれ程に、子どもの心身にとって影響の大きい時期といえるでしょう。
夏休み明けの子どもが「学校に行きたくない」と感じる理由やサインには、どのようなものがあるのでしょうか?また、そうした変化を感じたとき、保護者はどのように対応したらよいのでしょうか?
夏休み明けの子どもとの向き合い方について、公立小学校で10年以上、教師をしていた伊藤さくらさんにお聞きしました。
夏休み明けに不登校になる原因

小学生や中学生が夏休み明けに学校へ行きしぶる要因とは、何なのでしょうか。その例を3点紹介します。
<夏休み明けに不登校になる原因の例>
- 生活リズムの崩れ
- 家で過ごす楽しさに気付いた
- 環境が変わる不安
1.生活リズムの崩れ
夏休みに入り決まった時間に登校することがなくなると、「遅寝遅起き」に陥りやすい環境になります。新学期に入っても生活リズムが戻らないと、朝起きるのがつらくなり学校への足が遠のくことがあります。
2.家で過ごす楽しさに気付いた
涼しい部屋で動画を見る、ゲームをするなど、快適で楽しい過ごし方に慣れ、学校の環境に戻ることにハードルの高さを感じるケースもあります。
3.環境が変わる不安
1カ月ほどの夏休みを挟み、学校に行くこと自体に緊張感を覚える子どももいます。のんびりとした夏休みの生活から、慌ただしい生活への切り替えに苦戦するケースです。この場合は、学校生活に慣れることで少しずつ落ち着いてくるでしょう。
学校が再開する夏休み明けは、子どもを取り巻く環境が変化する時期です。1学期までは毎日学校に通っていた子でも、「学校に行きたくない」と感じる場合があるのです。
<関連記事>
・不登校の原因・理由を解説|親が家庭でできる対応とNG行動とは?
・登校しぶりを早期解決!原因や親が朝できる対応方法は?【教員の対応例あり】
夏休み中・夏休み明けに見られる不登校のサイン

「夏休みが終わっても、学校に行きたくない」と思っていても、うまく言葉にできない子どもも少なくありません。夏休み中・夏休み明けのタイミングで、保護者が感じられる子どもからのサインを紹介します。
<夏休み明けに「学校に行きたくない」と感じる子のサインの例>
- 学校を嫌がる言動をする
- 新学期が近づくにつれて、表情が暗くなる
- 宿題の進みが悪い
- 寝る時間や起きる時間が遅くなる
1.学校を嫌がる言動をする
比較的わかりやすいのが、「夏休みがずっと続けばなぁ」「ずっと家にいたいなぁ」といった学校を嫌がる言動です。ひとり言のようにポツリと吐き出すケースも多いので、聞き逃さないように心がけましょう。
2.新学期が近づくにつれて、表情が暗くなる
学校を嫌がる言動がなくても、新学期が近づくにつれて言葉数が減る・表情が暗くなるといった変化が見られるときは注意が必要です。
3.宿題の進みが悪い
新学期が近いにもかかわらず宿題が進まない場合、子どものやる気が低下している可能性があります。もちろん全てではありませんが、「学校」に気が向かないサインとも考えられます。
4.寝る時間・起きる時間が遅くなる
寝る時間・起きる時間は、子どもの心理状態を現すバロメーターのひとつです。当然ながら、寝る時間が遅いと早く起きられず、「もっと寝ていたいから、学校に行きたくない」という気持ちにつながる恐れがあります。
夏休み明けの不登校を防ぐために親にできること

夏休み明け、子どもがスムーズに登校するためには、どのような点を心がければいいのでしょうか?親が家庭でできる対応方法を3つ紹介します。
<夏休み明けの不登校を防ぐポイント>
- 子どもと2人の時間をつくり、話をする
- 新学期が始まる1週間ぐらい前から、生活リズムを整えていく
- 「家が楽しい」と思わせすぎない
1.子どもと2人の時間をつくり、話をする
きょうだいがいる場合は特に、2人の時間をつくって会話をすることが大切です。ランチに行くなど、場所を変えて「特別感」を出すのもよいですね。
2.新学期が始まる1週間ぐらい前から、生活リズムを整えていく
先述のとおり、朝起きられないことが登校しぶり・不登校につながるケースは少なくありません。子どもと話し合って起床・就寝時刻を決め、新学期が始まる1週間ほど前から徐々に生活リズムを整えていくようにしましょう。
3.「家が楽しい」と思わせすぎない
楽しいほうがいいのは当然の心情なので、家を快適にし過ぎない工夫が大切です。ゲーム・動画は時間を決め、娯楽ばかりにならないようにしましょう。子どもだけでオン・オフを切り替えるのは難しいため、家庭内のルールを決める手もあります。
学校現場にいるとき、「家族と一緒に楽しく過ごせる」「好きなだけゲームができる」など、家の快適さが登校しぶりにつながったケースが多数ありました。
学童に行っていないお子さんは特に、娯楽ばかりにならないよう、家庭学習の時間を組み込むなどの工夫が大切だと思います。
学校へ行きたくない子は休ませてもいい
子どもの学校に行きたくないサインに気付いても、「休んだら不登校になっちゃうの?将来はどうなるの?」と休ませることに抵抗を感じるかもしれません。休むって悪いことなのでしょうか? 元教師の伊藤さくらさんや、不登校支援の親子の相談に乗ってきた関野亜沙美さんは次のように話します。
私が小学校で1番驚いたのは「子どもたちの忙しさ」です。8時~15時まで、ほとんど休憩なしで過ごすのはかなり大変です。疲れから「学校に行きたくない」と言っている場合には、思い切って休むのは悪くないと思います。
休むかどうかよりも、休むことで家は好きなことができて、ダラダラできて居心地がいい家にいるほうが学校に行くよりも楽と思ってしまうのはよくありません。子どもが消耗しきっているのでなければ、休むとしても『じゃあ今日は家でどうやって過ごす?』と1日の行動計画を親子で作りましょう。
休ませることは必要。ですが、解決すべき(できる)ようなトラブルやストレスによる大きな消耗をしていない場合は、生活リズムを崩さないよう、活動計画を立てて過ごすことが「学校に行きたくない」と「学校に行けない」に移行させない方法のひとつかもしれません。
<関連記事>
・小学生の子どもが「学校に行きたくない」と言ったら?理由や親の対応を元教師がアドバイス
・学校に行きたくない…中学生の親の対処法は?理由を知る方法や休ませるときのポイント
小中学生の登校しぶり・不登校の現状

子どもの不登校は増加傾向にあり、小学生では過去10年間連続で件数が増加し続けています。子どもを取り巻く環境は常に変化しているといえるでしょう。
夏休み明けのタイミングに関わらず、子どもが「学校に行きたくない」としたら、気になるのは理由や原因です。いじめや人間関係のトラブルなど、さまざまなイメージが頭の中で広がっていきますが、子どもが学校に行きしぶるようになるのはなぜなのでしょうか。元教員や不登校支援の専門家は、次のように話します。
小学生の不登校の原因
元教師の伊藤さくらさんは、小学生が学校に行きたくないと思う原因は、大きく分けて次の3つだと考えます。
- 人間関係
友人や教師との関係は学校生活を支える土台のようなもの。嫌がらせやいじめなどの分かりやすいエピソードがなくても登校をしぶり始めるケースがあります。 - 勉強が分からない
学校生活の大半は国語や算数などの授業時間で占められています。授業の内容を理解できない子どもにとって、劣等感を感じながら難しい話を長時間聞き続けることは苦痛でしかありません。 - 心身の疲れ
心身の疲れが原因で、「学校に行きたくない」というパターンもあります。
一方、中学生が学校に行きたくないと感じる理由はどうなのでしょうか。
中学生の不登校の原因
日本財団が2018年に行った調査によると不登校経験(年間30日以上欠席)、不登校傾向にある(部分登校、教室外登校、仮面登校※1)中学生が「学校に行きたくない」と感じている理由は、「疲れる」「朝、起きられない」などの身体的症状、「授業がよく分からない」「テストを受けたくない」という学習面にあるとされています。
また、不登校中の子も多く通う学習支援塾「ビーンズ」代表の塚﨑康弘さんは、次のようなことも不登校の要因になっていると話します。
- 学校へ行くことが当たり前ではなくなった
10人に1人が不登校傾向にあり、学校に行かないという選択肢が身近になり、学校以外の選択肢を想像しやすくなっている。 - リアル(学校)がネットに負けている
ネットのゲーム上で友達と繋がることができて、孤独を解決できるだけでなく、対人のコミュニケーション力や社会性を育てることができる。また、ネット上で誰かと協力したり、達成感を得られたり、人間としての喜びや楽しみを現実(学校)以上に味わえる。 - 学校という独特の空間に耐えられない
本人のコミュニケーション力に難があったり、発達や特性に課題があったりするわけではなく、学校という特殊な環境下での閉鎖的な人間関係や特殊な振る舞いを強制されることに耐えられない。
以上のように「学校に行きたくない」理由にはさまざまなことが考えられますが、明らかなのは、親が「それなら休んでも仕方ない」とストレートに思えるような大きなトラブルでなくても、登校しぶりや不登校の原因になるということです。
<関連記事>
・中学生が不登校になる原因は?本音の理由と親の対応方法を不登校支援の専門家が解説
言葉以外の不登校のサイン
子どもが学校に対して深く悩んでいても、その気持ちを素直に話してくれるとは限りません。元小学校教師の伊藤さんは、小学生の登校しぶりのSOSサインとして、次の2つを挙げてくれました。
- 朝になるとお腹が痛くなる
「学校に行かなければならない」のは、子どもが自分で1番分かっていること。頭では分かっているけれど、心が追いつかないときに腹痛や吐き気という形で体の不調として表れる場合もあります。 - 学校に行く前後の表情が暗い
夜更かしをしたわけでもないのに、朝なかなか起きなかったり、表情がどんよりと暗かったりするのは、「学校に行きたくない」気持ちの表れ。また、学校から帰ってきたときの表情が暗い場合、学校で嫌なことがあったり、つらい思いをしたりした可能性があるかもしれません。
朝になると「お腹が痛い」と子どもが言っても、「でも下痢でもないし、熱でもないし」と流してしまうこともあるでしょう。
しかし、国立成育医療センターが2021年12月に行った調査によると、小学5年生~中学3年生の20~30%が「お腹が痛い」「頭が痛い」「腰が痛い」「めまいがする」などの体の不調を日常的に感じており、体の不調を感じている子は抑うつ症状の重症度が高いことが分かっています。
体の不調は体の病気のサインだけではなく、子どもがうまく言葉にできない心の不調やSOSのサインなのかもしれません。
不登校・登校しぶりの相談先とは
不登校が確定していなくても、子どもが悩んでいる様子を見るのはつらいもの。親も不安でいっぱいになってしまいますよね。そんなときはどこに相談すればよいのでしょう。
教育支援センター
居住している地域の教育支援センターで子育ての悩みを相談できるほか、教育委員会が不登校の相談窓口を設けている場合もあります。『市区町村名 不登校 相談』で検索してみましょう。ただし、相談できるのが子どもだけというケースもあります。
<関連記事>
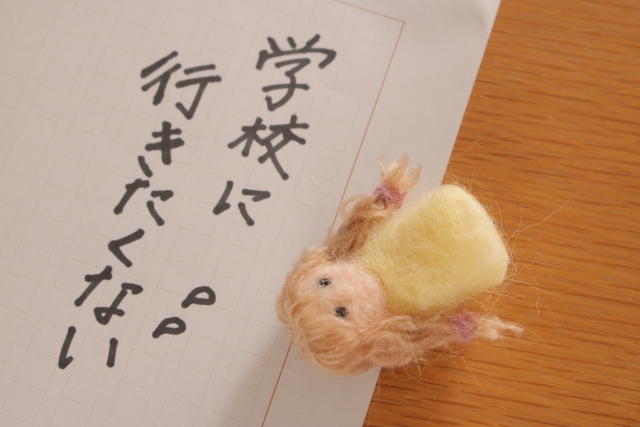
児童相談所
児童相談所は虐待と通報する場所のイメージがありますが、「育成相談」というカテゴリーで17歳までの教育・子育てに関する相談を受け付けています。
よりそいホットライン
電話、FAX、チャットやSNSによる相談に対応している「よりそいホットライン」。いろんな人のさまざまな悩みを24時間体制で受け付けています。大人も子どもも利用可能。
ソクたま相談室
保護者が発達や教育の専門家に匿名で子育ての相談をできるオンラインカウンセリングサービス「ソクたま相談室」。
<「ソクたま相談室」不登校・登校しぶり相談の専門家リスト>
- 車重徳さん(認定心理カウンセラー・児童発達支援管理責任者)
- 五十嵐麻弥子さん(不登校訪問支援カウンセラー・不登校支援団体代表)
- 若山修也さん(元通信制高校職員)
- 川下耕平さん(学習支援塾主宰・公認心理士)
- 伊藤さくらさん(元小学校教員)
ほかにも元教師や教育アドバイザー、元教師などが多岐にわたって親身に話を聞き、相談にのります。
不登校・母子登校・行きしぶりについて専門家へ相談できます

- 子どもの気持ちが分からない
- 子どもへの接し方が分からない
- 孤独を感じてつらい
オンライン相談室「ソクたま相談室」なら、不登校支援者、元教員など教育・子育ての専門家に悩みや不安を相談できます。
学校に行けるかどうかは、子どもだけでなく親も悩ませます。子どもだけケアすればいいではなく、親が自分自身もケアして日々を過ごせることを願っています。
<関連記事>
・不登校の悩みの相談先はどこ?6つの支援先と相談するメリット
・不登校のカウンセリングって?親と子どもへの効果や相談事例も紹介
※この記事はこれまでに「ソクラテスのたまご」で公開された記事や専門家への取材をもとに作成しています。
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!