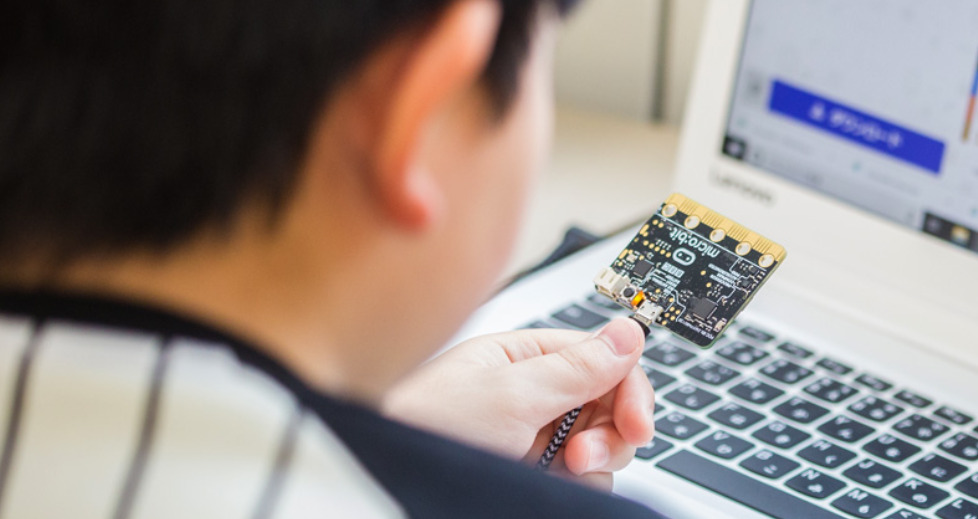ギフテッドの子の特徴とは?診断方法や発達障害との違い、親のサポート方法を解説

ギフテッドとは、生まれつき特別な才能や高い能力を持つ子どものこと。特定の分野で突出して優れた才能を持つことから、発達障害との関係が気になる方も多いかもしれません。ここでは、ギフテッドの特徴や種類、医学的に診断できるのかについて紹介します。家庭でのサポート方法についても解説するので、参考にしてください。
目次
ギフテッドの定義

ギフテッドとは一般的には、生まれつき、特別な才能や並外れて高い能力を与えられた子どものことを指します。「神からの贈り物」という意味から、Giftedと呼ばれています。
日本では明確な定義はありませんが、この概念が浸透したギフテッド教育の先進国であるアメリカでは、教育関連の連邦法では次のように定義されています。
アメリカでのギフテッドの定義
学問や言語能力、芸術、創造性、リーダーシップなどのさまざまな領域の特定分野において、同年代の子どもと比較して突出した才能を持つ子ども
この定義によると、ギフテッドの子どもの才能が現れるのは“特定の分野”とされています。つまり、「何でもできてしまう天才!」というよりも、例えば「数学だけ」「語学力だけ」など、関心のある1つの能力が優れている状態です。
早い段階での教育で得られる知能ではなく、特定の能力が生まれつき突出していることをさすため、遺伝要因が大きいといわれています。
また、ギフテッドについて語る際に、ギフテッドかどうかを識別する値として“IQ130以上”という基準が用いられることがあります。しかし、IQのみで判定されることは世界的にもあまりなく、実際には才能の領域に応じた評価やチェックリストの活用など多様な評価方法が用いられます。
ギフテッドの2つの種類
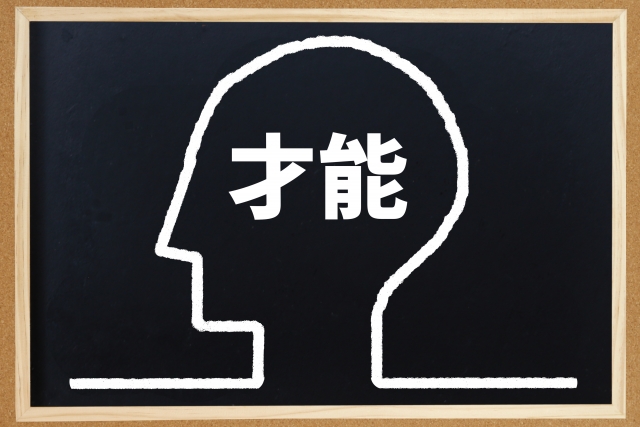
ギフテッドには「英才型」と「2E型」の2種類があります。
1.英才型
「ある特定の分野だけが突出して得意」というわけではなく、認知や記憶など全面的に高い知能を示す人です。例えば、「国語、数学、理科、社会、英語、美術、体育のどの学業も得意」「社会性を兼ね備えているため、日常生活が円滑」といったの傾向がみられます。周りからも「群を抜いて才能がある」ようにと見えるため、能力を伸ばすための環境や機会、チャンスに恵まれやすいのが特徴です。
2.2E型
ギフテッドの特性と発達障害の両方の側面を持つ人です。例えば、「数学は大人でも難しい分野まで解けるけれど、国語の読解は難しい」「興味のあることには思いきり集中できるけれど、こだわりや多動症によって他の人との交流が苦手」との傾向がみられます。
突出した能力を持つ一方で、苦手なことはとことん苦手な傾向を示しやすく、ときには「発達に偏りがある」と思われることも少なくありません。
ギフテッドの子どもの特徴は?

アメリカのギフテッド教育の推進団体『ギフテッド児童協会(National Association for Gifted Children。NAGC)』では、以下のような特徴を挙げています。
ギフテッドの特徴
- 物覚えが良い
- 記憶力が良い
- 語彙が通常以上に豊富で、複雑な文章を構成できる
- 数字遊びやパズルをはじめ、問題を解くのが好き
- 深く、激しい感情や反応を表す
- 物事に過敏に反応する
- 幼少期から理想や正義感を持っている。
- 注意力や集中力が長く続く
- 自分の考えに浸るなど、妄想傾向がある
- 人に探りを入れるような質問をする
- いろいろな方法を試して実験することに興味がある
- 鋭い、変わったユーモアセンスを持っている
- ゲーム的思考や複雑な構図で、人や物を系統立てたがる
- 鮮明な想像ができる(幼児期に空想の友だちをつくるなど)
このようにギフテッドの特徴は多岐にわたりますが、どれも「当てはまる気もするし、違う気もする」ケースが多くあいまいな印象です。つまり、保護者が「自分の子どもがギフテッドか」を判断するのは簡単ではないのです。
ギフテッドの子にみられる言動の例
ギフテッドの子は、以下のような特徴や言動が見られることがあります。
- 興味関心があることに過集中する
- 興味関心がとめどない
- 共感性・感受性が高い(全ての人、ものに博愛を感じる)
- 正義感の強さ
- 過剰適応(過度に譲歩する)
- 自身の世界を強く持っている
当てはまる項目があっても必ずしもギフテッドであるということではありませんが、一般的な傾向として紹介します。6つの特徴について詳しく見ていきましょう。
1.興味関心があることに過集中する
ギフテッドの子どもは、興味関心があることに時間を忘れて集中する傾向があります。興味があることをとことん調べたり、覚えたり、突き詰めてアレンジするといった姿が見られ、5時間でも10時間でも集中して取り組むため、保護者や先生が心配になることもあるほどです。
就学前の子であれば、切り替えが苦手であったり、ときには集中しすぎてトイレに行くのを忘れてお漏らしをしてしまったりすることもあります。
小学生以降になると、好きな教科と嫌いな教科に強い偏りが出ることがあります。好きなことは、詳細な情報まで事細かに覚えていたり、多くの時間を費やして探求することがあります。例えば、社会科のなかでも特に歴史が好きな子であれば、年号や人物の名前など、参考書などの書籍を一度読んだだけでも隅々まで記憶して大人が驚くほどの知識を持っていることがあります。
2.興味関心がとめどない
一見して過集中の特徴と相反するように思われがちですが、ギフテッドの子は「あれもしたい!これもしたい!」と、とにかく様々なことに関心や感受性がはたらくことがあります。
3.共感性・感受性が高い(全ての人、ものに博愛を感じる)
ギフテッドの子どもは、周囲をよく理解して非常に分け隔てなく人と接したり、気持ちをわかろうとしたりする傾向があります。一方で、いわゆるHSP・HSCのように、他者の出来事を自分のことのように感じ過ぎてしまう様子も見られます。ニュースを見る、他者の悲しい話を見聞きするだけで自分の事のようにダメージを受けてしまうことも珍しくありません。
強い共感性や豊かな感受性を持つ要因として、一説には他の動作を感知したとき、まるで自分のことのように感じる神経細胞(ミラーニューロン)が関連しているとされています。
4.正義感の強さ
ギフテッドの子は、周囲の様子や文脈を過敏にキャッチしているため、同年代の子に比べて理不尽さに敏感です。そのため、自分の中で納得がいかないことがある場合には正義感が相まって周りと衝突することがあります。
幼い頃にはまだ自他ともに言語や感情コントロールが未発達なため、相手に手を出してしまうこともあります。一方で、小学生以降になり周囲への理解、伝え方が成熟してくると、理論的に周囲に説明してリーダーシップをとったり、話し合いをまとめて仲裁に入ったりすることが出来るようになります。
5、過剰適応(過度に譲歩する)
非常に共感性が高いがゆえに、他者を困らせないように過剰に譲歩しすぎたり、適応しすぎてしまうことがあるのもギフテッドの特徴のひとつです。
幼児の場合は、友達と好きな遊びをするときに、自分がしたいことがあるのに友達に合わせすぎる、過剰に適応してしまうといった傾向も見られます。そのため、外では何も問題がないかのように見えてもフラストレーションを発散できず、抑えていた気持ちが家庭で大爆発してしまうこともあります。
そういった自分に気が付いたり、他者から気が付いてもらえることで、年齢があがるにつれ徐々にバランスが取れるようになってきます。
また、小学生以降では、学習や運動、人間関係など「期待に答えることで承認されたい」といった気持ちが高まり、過剰に適応的な行動がみられる場合もあります。
6.自身の世界を強く持っている
幼児期には、空想で遊ぶ場面が多く、独自の物語を作ったり、遊び方をアレンジしたり、あたらしい遊びを作ったりと独創的な様子が多く見られることがあります。連想や着想が強く、クリエイティブな遊びを生み出したいという欲求があるのもギフテッドの特徴です。
小学校に上がってからはより多くの情報に触れる機会が増えることもあり、ものづくりなどで本人が自由に着想する場面が多くみられます。一方で、学校生活でのルールなど「守らなければならない」規制も増えてくるため、本人にとってはストレスに感じる場面も増えてくるでしょう。
ギフテッドと発達障害の違い
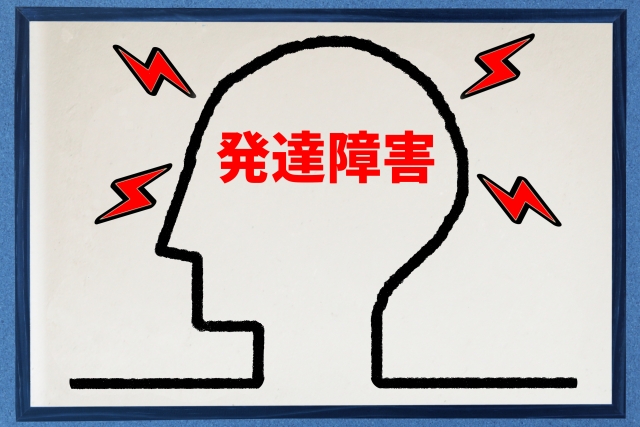
ギフテッドの子どもと混同しやすいのが、ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)等の発達障害です。
注意したいのは、大前提として、医学的な概念である発達障害と明確な基準がないギフテッドは定義も特徴も異なるということです。しかし、それぞれの特性に共通点が多いことやどの程度集団に適応できるかという観点で判断されるケースもあることから、ギフテッドなのに発達障害と誤診されることも多いのが現状です。
ここでは、あくまで傾向としての両者の共通点と相違点について紹介します。
ギフテッドと発達障害の共通点
例えばADHDは感覚が過敏だったり、得意分野にのみ関心を持ち、集中力が偏ってしまうという特徴があります。このような感覚過敏や集中力の偏りは、ギフテッドにも共通する特性です。
また、ASDは先天性の脳障害が原因といわれており、感覚過敏や特定の物事、人物に対しての愛着、関心の深さが特徴にあげられます。これらも、特定の分野に集中するギフテッドと共通している事項です。
ギフテッドと発達障害の相違点
ADHDに見られる衝動性や注意力欠如、好奇心の旺盛さは、ギフテッドの特徴とは異なります。衝動的な言葉を使うことによる友達とのトラブル、ケアレスミスなどはギフテッドには起こりにくいのが特徴です。また、ギフテッドが得意とする人の感情への共感、集団行動への適応、リーダーシップ等は、発達障害のある人にとっては苦手なことといえます。
(※こちらはあくまで傾向です。)
ギフテッドは医学的に診断できる?3つの検査方法

ギフテッド教育先進国であるアメリカでは、ギフテッドの客観的な判定のために下記のような方法が用いられているようです。
【診断方法①】WISC検査(ウェクスラー式知能検査)
一般的に「WISC検査」と呼ばれる同検査は、5~16歳11ヵ月の子どもを対象とした知能検査のこと。発達障害を診断する際などによく使用されており、全体的な認知能力(IQ)だけでなく、言語理解、知覚推理、ワーキングメモリー、処理速度という4項目のテストで測定されます。学校のペーパーテストとは違う側面から、子どもの能力を測ることができます。
▶関連記事:WISC-Ⅴの検査内容や検査からわかること
【診断方法②】総合的判断
IQの数値が130に達していなくても、ギフテッドの可能性はあります。また、知能検査では、音楽的知能などの芸術的な能力や対人的知能、創造性、語彙力などを測定することはできません。
そのため、親や教師への質問紙、子ども本人の様子や日常行動に関する観察記録、学力テストや各種受賞歴などの学校成績といったさまざまな項目・方法によって総合的な判断を行います。
【診断方法③】RTIモデル
ほかの子どもと能力的発達に違いがある子どもの才能・能力や必要な支援などを、客観的に判断する方法です。教育環境をはじめとする外部要因と、その子が先天的に持つ特性である内部要因の両面から判定を行います。
通常学級内でのハイレベルな指導から、少人数での補足支援の追加、個別支援という3段階で、より正確かつ早期でのギフテッド判定を目指します。
日本におけるギフテッド診断方法
日本では、ウィスク検査が用いられることが多く、IQでは測れない能力などを総合的判断で補うのが一般的です。ただし、ギフテッドは診断名ではないため、病院で知能検査や総合的判断が実施されても、「ギフテッドです」という診断を受けることはできません。
検査はどこでできる?費用は?
ウィスク検査は児童精神科・小児科などの病院や教育支援センター、カウンセリングルームなどで診断を受けられます。一方で、RTIモデルが使われることはほとんどないのが現状のようです。IQ検査については心療内科などの病院や自治体で実施していることもあります。
また、インターネットでは無料でIQテストを受けられるサイトがありますが、信頼度が低いテストも多いものです。より正確に調べたい場合は病院で知能検査を受けるのがおすすめです。
なおウィスク検査を受けるにあたってかかる費用は、平均的には10,000円~15,000円程度ですが、受ける施設により異なります。
ギフテッドの子どもたちが抱えやすい困りごと
並外れて高い能力を持つギフテッドの子どもは、学校生活や日常生活でどのような困りごとを抱えやすいのでしょうか。代表的な困りごとについて紹介します。
1.周囲や社会生活上でのストレス、過剰適応の疲労
子どもの年齢が上がるにつれて、家族や学校の友達や先生など、周囲との関係性も複雑になります。ギフテッドの子は、周囲への理解力や共感性が高いがゆえに、本人が物事に矛盾を感じてフラストレーションを抱えていても、自分の気持ちを抑えて周りの話を聞いたり、話をまとめたりします。他者に比べて感受性が強いからこそ、我慢の積み重ねで強いストレスや困難を感じることも多くなります。
「今自分がどれくらい疲れているか」「このくらいなら休む」などストレスへの対処が出来るようになってくると、困りごとを軽減できるでしょう。
2.周囲の環境にうまくなじめない
子どもが年齢を重ねるごとに、集団生活で守らなければいけないこと、期待されることは増えていきます。例えば、基本的な生活習慣を身につけることや時間や期日に合わせて行動すること、学校生活でのルールを守ることなどです。また、学業や学校の成績、場に合った適切な振る舞いなど、周囲から求められることも年齢とともに増えていきます。こうした環境になじめずにストレスを抱えてしまうケースもあります。
そのほかにも、学習面では学校の授業が自分の能力のレベルに合わず、簡単すぎておもしろくない・退屈だと感じて、授業の時間を苦痛に感じてしまうこともあるかもしれません。
子ども自身が「本人のままで」承認されるような環境やリソースを見つけることで、自分の力をプラスの方向で十分に発揮しながら、フラストレーションを軽くして穏やかに過ごせるでしょう。
ギフテッドの子どもへの家庭での接し方
ギフテッドの子どもは、学校でもクラスの友達など同年代からどこか浮いてしまったり、周囲の理解を得られなかったりする場合があります。そこで、ギフテッドの子どもがのびのびと学びを深められるためのポイントになるのが、家庭での接し方です。
わが子の自己肯定感をはぐくむ声掛けをする
才能の高さゆえに周囲になじめず「自分は周りの子と違うのかな」「変に見られていないだろうか」と自信を失くしてしまうギフテッドの子どももいます。そのため、「無理に合わせる必要はない」「勉強が好きなのは素晴らしいことだ」など、わが子を肯定する内容をしっかりと言葉で伝えるのが大切です。
▶関連記事:【東大卒・家庭教育コンサルタントが伝授】自己肯定感を高める声掛け・接し方
学校以外のイベントや活動に参加する
学校では集団行動が基本のため、ギフテッドの子どもは「なんとなく居心地が悪い」と感じてしまうことがあります。同年代同士のコミュニケーションにコンプレックスを抱いてしまう場合、「学校以外の活動場所」を教えたり検討したりするのも良いでしょう。地域活動や好きな分野のコミュニティ、ボランティア活動など、学校以外で居場所を見つけられる場は多くあります。
知的欲求を満たせる環境を作る
興味や関心のある分野、才能を発揮できる分野の学びを満足に深められる環境は、ギフテッドの子どもにとっては「安心できる居場所」といえます。得意なものを尊重し、子どもに合わせて知識欲を満たせる環境をできるだけ作ってサポートできるようにしましょう。
日本におけるギフテッドの理解は、海外と比較するとまだまだ成熟しているとはいえないのが現状です。しかし、持って生まれた才能を伸ばすための学習や「ギフテッド教育」のニーズも次第に高まっており、積極的に取り入れている協会や学校もみられます。
▶関連記事:ギフテッド教育のメリットや課題は?日本の事例も紹介
▶子どもの知能や特性を正しく理解しよう!知能検査「WISC」特集はこちら
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

ライター、コピーライター、編集など。広告出版会社のクリエイティブ職~オーストラリアの新聞社のデザイナーを経て、フリーに。雑誌やWebメディア、企業サイト、広告、PRツールなど、様々な媒体で執筆。ジャンルは、文芸、企業PR、テクノロジー、教育、音楽、法律、アート、妄想、ライフスタイル、旅行、人材系など。また、大手企業経営者からアイドルまで幅広く取材を経験。現在、東京在住。一人娘と座敷猫を溺愛中。