日本の「ジェンダーステレオタイプ」とは?男性=賢い、女性=優しい…具体例や子どもへの影響
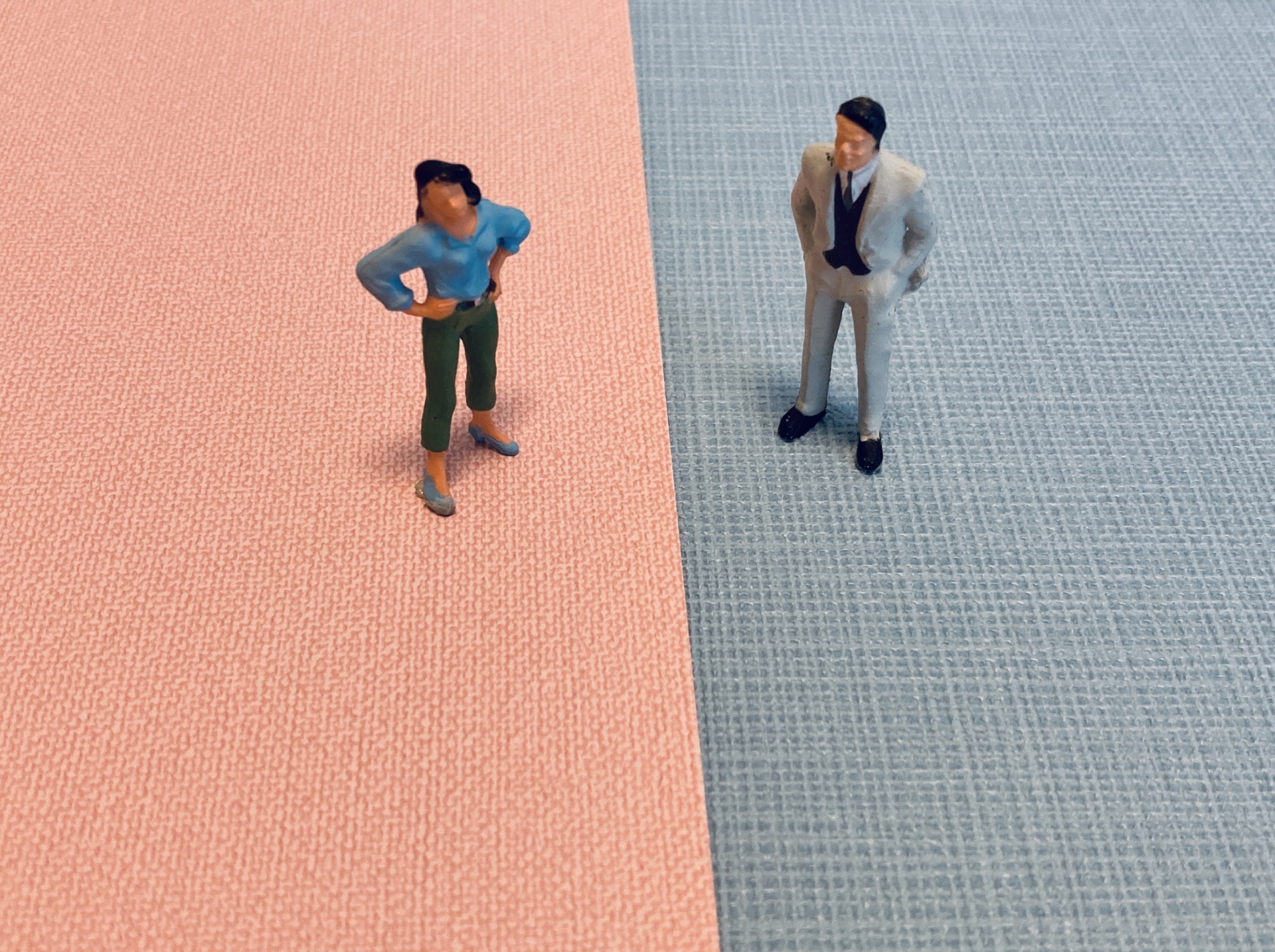
男女の違いにより生じる格差を表す「ジェンダーギャップ」は、とりわけ日本で大きいといわれています。その主な要因に「男性は頭がいい、女性は優しい」といった固定観念であるジェンダーステレオタイプが関係していると考えられています。子どもの将来の選択肢を狭めかねない、ジェンダーステレオタイプを解説します。
ジェンダーギャップが大きい国、日本
ジェンダーとは、生物学的な性差とは別の社会的・文化的な性差のこと。世界経済フォーラムが2022年に発表したジェンダーギャップに関する調査報告によると、日本は146カ国中116位と、世界的にジェンダーギャップが大きい国であることが明らかになりました。
なぜジェンダーギャップが問題視されるのかというと、ジェンダーに対する思い込み(ジェンダーステレオタイプ)から、性別にとらわれて将来の選択肢を狭めてしまう可能性があるからです。
ジェンダーステレオタイプとは、「男性=賢い、女性=優しい」など、社会に広く浸透した「男性」「女性」に対する固定観念やイメージのことです。ジェンダーステレオタイプを抱えたまま成長すると、男性は科学者などの職業を選択し、女性は逆に科学者という「賢い」イメージのある職業を避ける可能性があると懸念されています。
逆にジェンダーギャップが少ない国は、アイスランド・フィンランド・ノルウェーなどの北欧諸国です。これらの国では、仕事も子育ても男女による分け隔てがなく、男性も女性も生き生きと活躍する社会が実現しています。
このように、ジェンダー平等によるメリットは経済から社会活動に至るまで計り知れません。
具体的な例では、2008年のリーマンショック後にいち早く業績を回復したのは女性取締役がいる企業でした。
世界がジェンダー平等に向かう21世紀、ジェンダーギャップが大きい国・日本のありようが問われています。
男性は頭がいい、女性は優しい?

「男性は頭がいい、女性は優しい」はジェンダーステレオタイプの典型です。
その他ジェンダーステレオタイプに当てはまる発言は以下のものが挙げられます。
- 女の子だから家事をしなさい
- 女の子だからおしとやかにしなさい
- 男の子だから泣いてはダメ
- 理系は男子、文系は女子
15~18歳までを高校生としたアンケート調査では、ジェンダーステレオタイプに直面する場面の7割は学校内との回答結果が出ています。
高校生の多くがジェンダーステレオタイプを押し付けられていると認識していることは見逃せない傾向でしょう。
さらに、「ジェンダーステレオタイプは、自分の可能性を狭めていると感じるか」という質問に対し、「そう思う」「どちらかというとそう思う」との回答が7割を超えたことにも注目です。
日本の未来を担う子どもたちが、ジェンダーステレオタイプによる弊害に抵抗感を示しているという現実は無視できるものではありません。
社会全体としてジェンダーギャップを真摯に受け止め、向き合う時期にきています。
ジェンダーステレオタイプはいつ芽生える?
京都大学がおこなったジェンダーステレオタイプが芽生える時期に関する研究調査では、女児は4歳頃から「女性=優しい」というジェンダーステレオタイプを自身に押し付けていることが明らかになりました。
「男性=賢い」というジェンダーステレオタイプは7歳頃から現れる可能性があると考えられています。 ジェンダーステレオタイプは、4~7歳という物心がつき始める幼少期からもうすでに芽生え始めているという実態を知っておきましょう。
親はジェンダーバイアスな言葉に注意しよう
子どもにとってのジェンダーステレオタイプは、家庭でも生まれる可能性があるものです。親は「男性=賢い、女性=優しい」といった、ジェンダーバイアス(=性別による偏った決めつけ)な言葉に気をつけましょう。
無意識のうちにジェンダーステレオタイプを植え付けてしまうと、子どもの将来の選択肢や自己肯定感に悪影響を与えかねません。
「男だから」「女だから」などと、ものごとを性別によって決めつける時代は終わりを迎えつつあります。
世界が一丸となって「ジェンダー平等の実現」を掲げる今、子どもにとって一番身近な存在である親がまずはジェンダーバイアスへの理解を深め、向き合う姿勢が求められています。
以下の「ジェンダーバイアス」な9つの禁句を参考に、何気ない日常会話からジェンダーバイアスをかけてしまっていないか意識して見つめ直してみましょう。
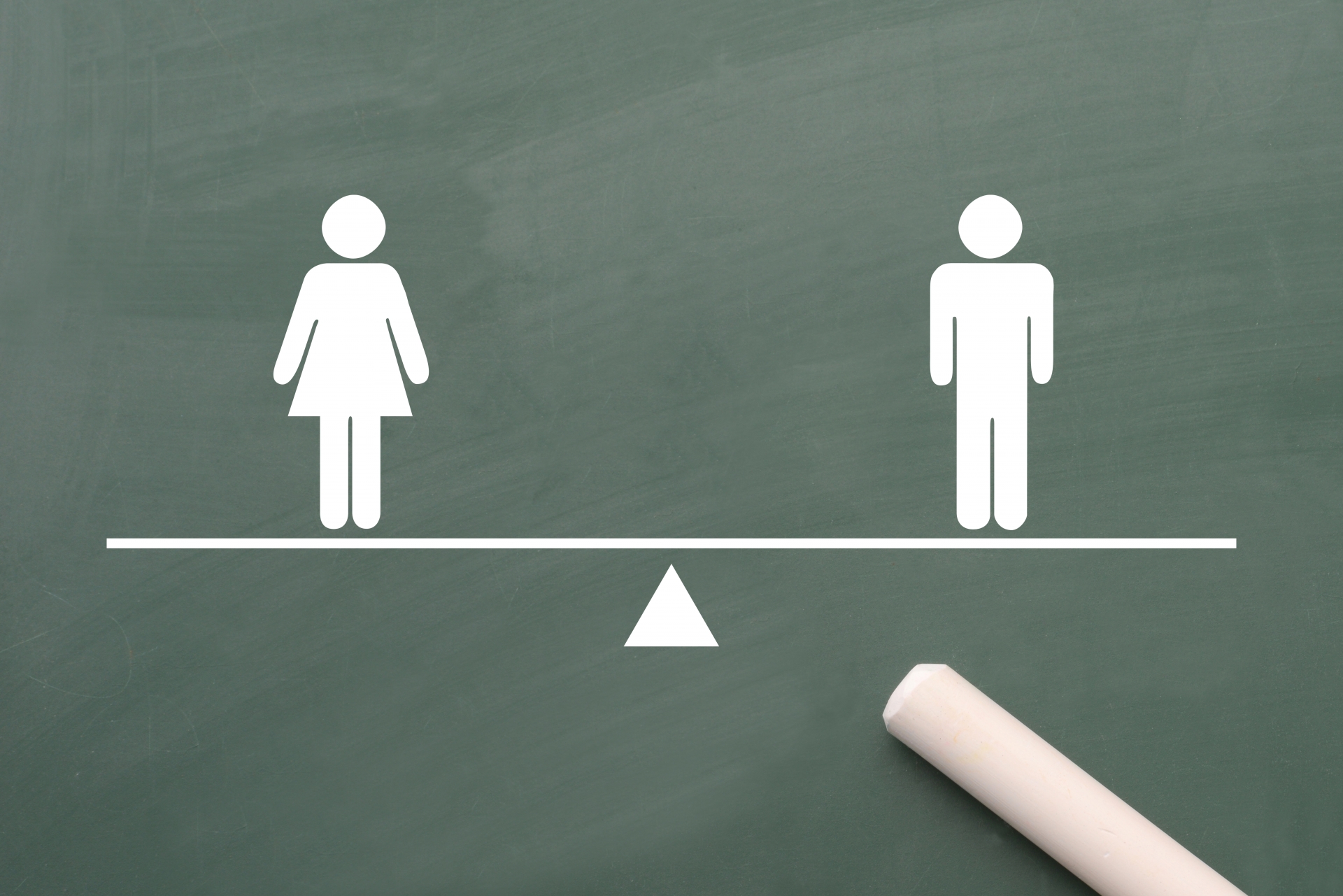
<参考資料>
・学校法人追手門学院 子どものジェンダーステレオタイプが生じる時期を解明(PR TIMES)
・内閣府 男女共同参画局 世界経済フォーラムが「ジェンダー・ギャップ指数2022」を公表 内閣府男女共同参画局総務課
・NHK公式HP 世界で一番ジェンダー平等の国=アイスランドのお話
・OTEMON VIEW 男女平等ランキングはなぜ低い?日本のジェンダーギャップ解消に求められる家族観・政策の視点
・寄付・募金の公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン 「日本の高校生のジェンダー・ステレオタイプ意識調査」レポート発表
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!





















































