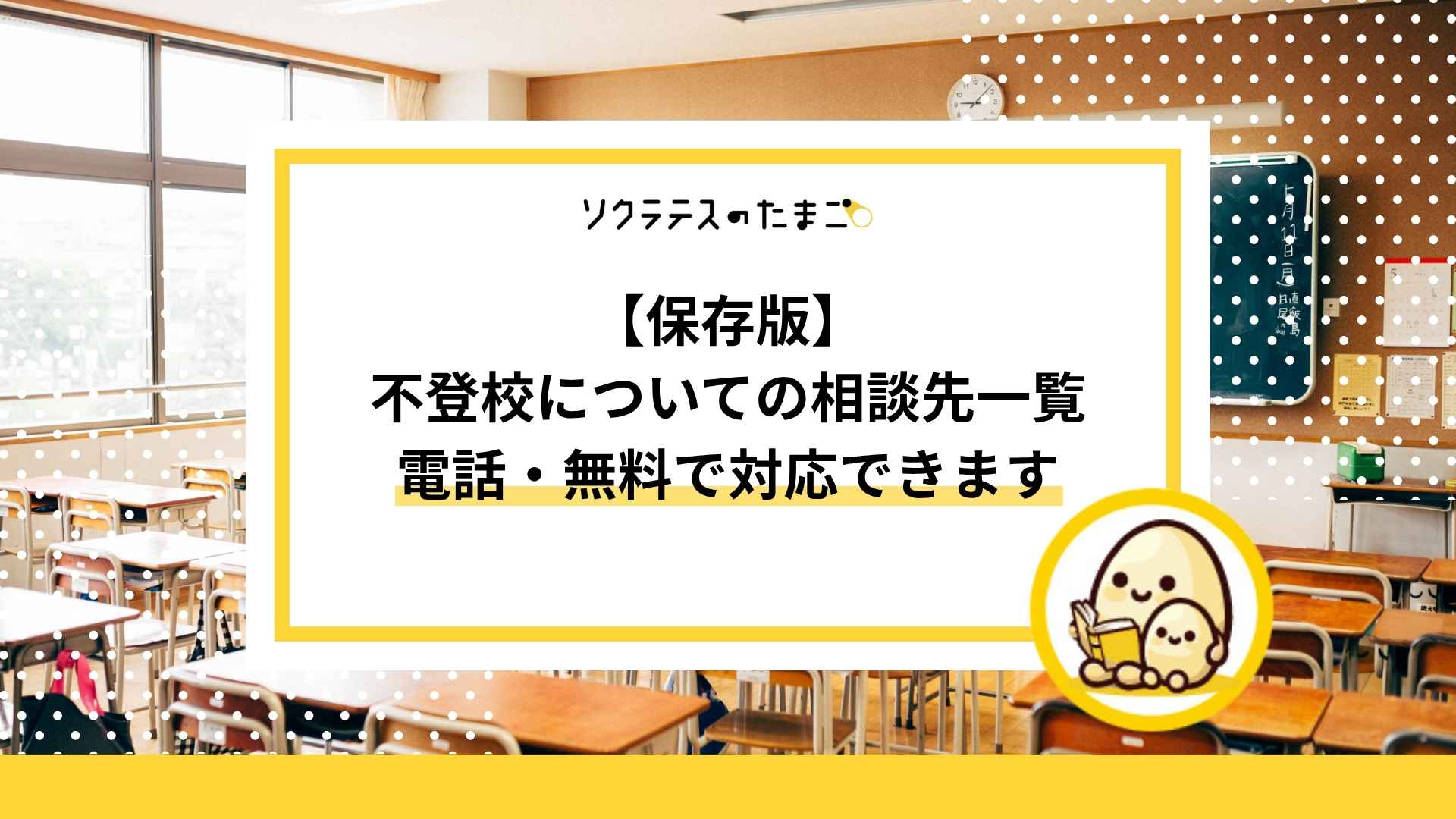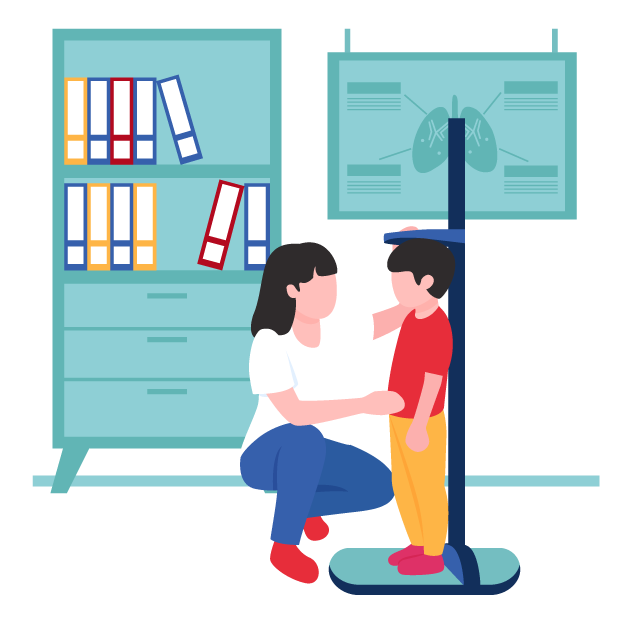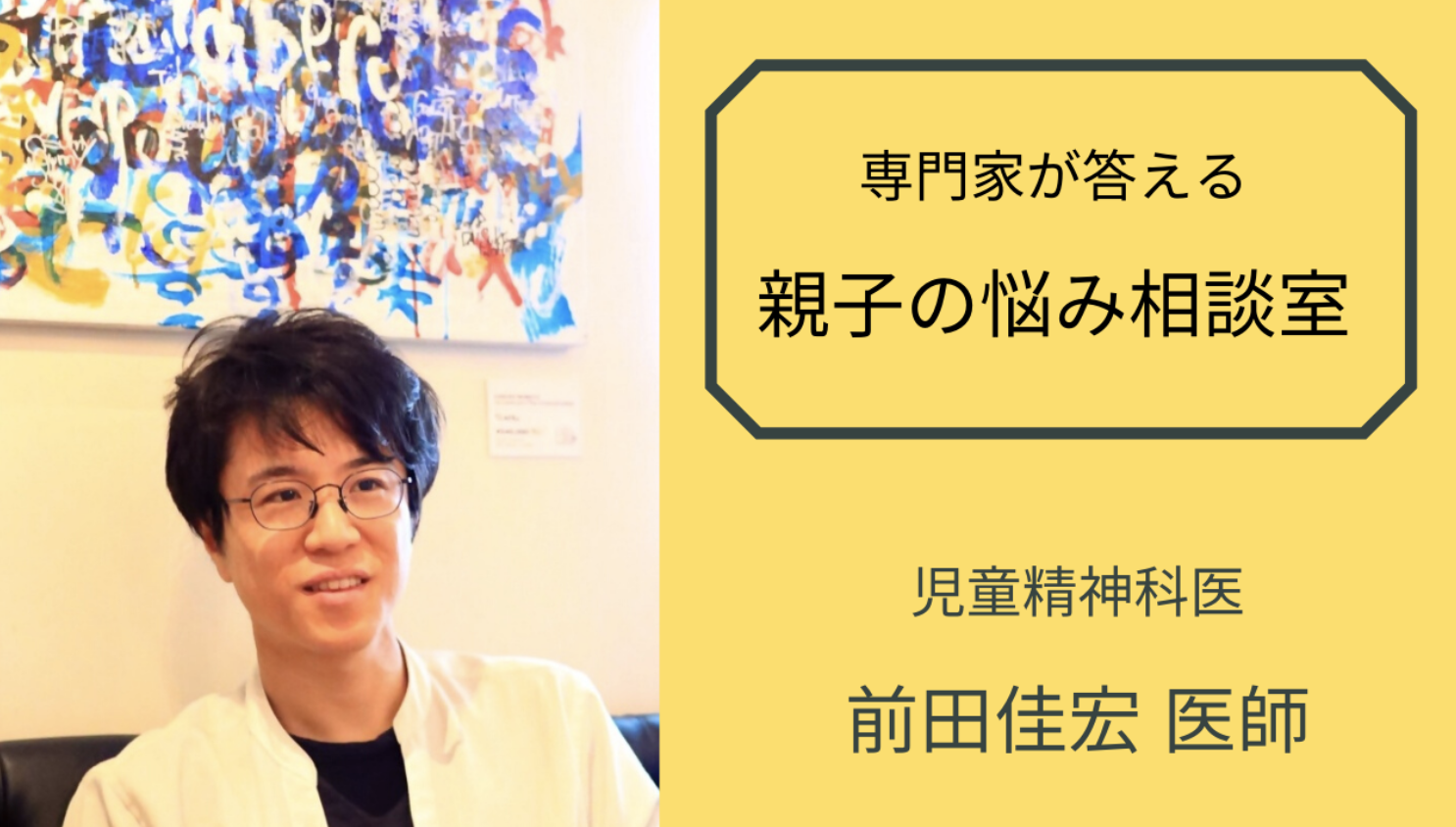毒親・毒親育ちの特徴は?チェックリストや対処法を専門家が解説

「私の親は毒親?」「親のような子育てはしたくない」と思うことはありませんか? 子ども時代の親子関係はときに生きづらさに繋がり、考え方や感じ方に大きな影響を与えます。親との関係を客観視して、自分の子どもへの負の連鎖を断ち切る工夫を考えていきましょう。毒親のタイプや特徴、毒親にならないための方法を解説します。
目次
毒親とは?
毒親とは、精神医学や心理学で明確に定義されている用語ではありません。「毒」とつくぐらいなので、子どもに悪い影響を与えている親のことですが、あくまで俗称として使われている言葉です。言葉のはじまりはスーザン・フォワードが書いた「毒になる親」という10年以上前に出版された本です。スーザンは「子どもの人生を支配し、子どもに害悪を及ぼす親」が「毒親」であると定義付けしています。この「支配と害悪」が毒親のキーワードと言えるのではないでしょうか。
毒親の4つのタイプと特徴
一般的に、毒親は主に4つのタイプにわけられます。以下で、タイプごとの特徴について解説します。
【毒親タイプ①】過干渉・過保護タイプ

このタイプは、子どもの意志よりも自分の考えや理想を重視するため、過保護だったり過干渉だったりすることがあります。
例えば、「言ったとおりにしないと○○するよ」「△△をしないと○○してあげないよ」と、自分の都合を優先して子どもに言うことを聞かせようとするケースもあれば、何かにつけて「あなたのため」という考え方や言葉で、親の思ったとおりの選択に誘導していくケースもあります。
また、「○○しないなんてお母さんは悲しい」と罪悪感に訴える場合もあります。
共通しているのは、子どもの気持ちや考えを尊重せずに、支配的に親の心配や考えや意図を押し付けていることです。
このタイプの毒親の元で育つと、子どもは自己決定をする機会を奪われていきます。そして、いずれ自分が何を望んでいるのかさえ分からなくなります。
ただし、子どもが小さい頃は、教育として道徳的、倫理的に「よくないこと」を教えることは大切です。子どもの気持ちに理解を示しつつ、好ましい言動に誘導していくことはこのタイプに当てはまりません。
<関連記事>
・過干渉な親の特徴(診断テストあり)
・子離れできない親の特徴
・ヘリコプターペアレントの特徴や影響
【毒親タイプ②】ネグレクト・無関心タイプ

過保護・過干渉とは真逆で、子どもを放置するなど関心を示さず、無視・無関心であるタイプです。
子どもは大人の庇護がないと生きていけません。なんとかして親の愛情を得ようとさまざまな努力をします。
しかし、それらの努力が無駄に終わってしまうとどうなるでしょうか。自信をなくし、自分はとるに足らない存在だという考えや思いを植え付けられてしまうかもしれません。
人間は、無条件に愛されたいという欲求を持っています。この愛情への欲求が満たされないと、大きな自己不全感を持ってしまうでしょう。
<関連記事>どこからがネグレクト?特徴や相談先
【毒親タイプ③】虐待をするタイプ

虐待には、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト、性的虐待の4種類がありますが、いずれの種類でも子ども時代に受けた虐待は、大人になってから強く影響します。虐待やストレスは脳機能に影響を与えるからです。
<関連記事>心理的虐待による子どもへの影響
また、父親や母親に虐げられ続けて育った子は、世の中は怖くて危険なところであると信じて他者との問題解決は暴力や高圧的な態度で行うようになったり、怒りっぽく用心深い性格になったりしていく可能性が高くなります。
<関連記事>子どもを怒鳴ることの発達や心への影響
【毒親タイプ④】親が精神疾患や障害を抱えているタイプ
保護者自身がいつも何かに怯えている、焦っている、イライラしている、気分が沈んでいるなどの精神的な不調・不安を常に抱えている場合、子どもにとって悪影響になることがあります。
また、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意・欠如多動症)など、保護者の発達障害の影響が子育てに影響することもあるでしょう。
ただし障害の程度には大きな差がありますし、すべての発達障害の人が毒親ということではもちろんありません。
<関連記事>発達障害の親の特徴や影響、親との付き合い方
この記事を監修した表 広大さんに相談してみませんか?
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で表さんに親子関係の悩みを相談できます。
表 広大さんへの相談ページを見てみる
毒親になる原因や毒親自身が抱える問題とは?

毒親になることには、さまざまな要因が考えられます。しかし、同じ親の元で育っても兄弟で全く違う反応や関係性が生まれることもあります。たとえば、兄弟の一人は毒親だと親を忌み嫌っている一方で、他の兄弟は上手く親と付き合っているようなケースです。
毒親の絶対的な理由や原因があるわけではありませんが、毒親が生まれる要因として親の性格傾向、育ってきた環境や文化背景、精神疾患などが考えられます。
親の性格傾向
神経質傾向が強い場合は、親が過度に心配や不安を向けることで子どもに悪い影響があるかもしれません。何に対しても厳格でキッチリした性格傾向では、その厳しさがあだとなり、子どもに無理を強いることもあるでしょう。
育ってきた環境や文化的背景
最近は薄れてきているかもしれませんが、男尊女卑や家長制度の強い家の価値観、体罰も必要悪だと考えている家庭の場合は子に悪影響があるかもしません。
教育虐待という言葉がありますが、学歴が絶対的な価値観として根付いている家や、親がなんとしても子を医者などにさせようなどと考えると、子どもにとっては窮屈でつらい経験になるかもしれません。
精神疾患の有無
親に何らかの精神疾患がある場合は、ネグレクトや心理的虐待、身体的虐待につながるリスクがあり、注意が必要です。
毒親に育てられた人の特徴は?
「自分はあまりよい子ども時代を送っていない気がする」「親から受けてきたことが当たり前だと思っていたが、実はそうではないらしい」と気づいたとき、自分が毒親に育てられていたのかも、と不安になる人もいらっしゃるかもしれませんね。毒親に育てられた人は色々なことができなかったり、認められなかったりした結果、以下のような特徴がみられることがあります。
特徴①:どうせ自分なんか、といつも思っている
親から認められた経験が少ないため、自己肯定感を感じづらく、自分自身を責めやすい特徴があります。物事をすぐあきらめたり、達成感を感じにくいために、実際は出来ていることも、そう感じられないことが多いです。また「結果を出せない自分が悪い」と、自分に矢印が向きがちで、否定的な考え方になってしまいます。みなさんはそんな思考のクセはありませんか?
<関連記事>否定されて育った子どもの特徴
特徴②:いつも周りの顔色を伺っている
いつも親が選択したり、自分で決断できないことから、自分が何を望んでいるのかが分からなくなります。自分の意志ではなく「ここはこうするべきかな」「相手が求めてくるから、こうしよう」と相手に合わせすぎてしまうことがあるかもしれません。周りの顔色を伺うあまり、自分のことは後回しになりやすく、またすべての物事に対して慎重になりすぎたりします。不安が高く、心身が落ち着かないことも多いでしょう。不安症やうつ病などの疾患や対人関係の問題を抱えやすくなります。他者ではなく、自分の気持ちや考えを優先しているか、一度振り返ってみるとよいかもしれませんね。
特徴③:自分の意見を素直に言えない
自分の考えを聞いてもらえなかったり、否定されたりするので、どう伝えたらよいかわからず寡黙になったり、「(うまくいえないから)別にどっちでもいいよ」と相手に丸投げしてしまうこともあるかもしれません。自分を押し殺して、主張することが少ないために、交渉やコミュニケーションの機会自体が少なく、対人関係や社会生活にマイナスの影響が出ることもあります。
特徴④:パートナーや子どもと依存的な関係になりやすい
相手中心の行動を積み重ねた結果、その後の人間関係も依存的な関係になる可能性があります。「わたしはわたし、あなたはあなた」という独立した関係性を築きにくく、どうしても相手との距離がわからず踏み込んでしまう場合があるかもしれません。また、逆に踏み込まれてしまう場合もあります。不健康な共依存の関係性になりやすく、注意が必要です。
特徴⑤:過度な完璧主義と責任感がある
親から完璧さを求められ続けた結果、何事もきちんとやりたい、誠実でなければならないという気持ちが強くなる可能性があります。子ども時代の「正しくありなさい」「しっかりやらない人はダメ」という親の言葉が、大人になってからも自分に影響を与えている可能性があります。「せねばならない」「してはならない」という考えはどこからきているのか、本当に自分がそう思っているのか、それともそういった考え方しか教えてもらっていないのか、振り返ってみるといいかもしれません。
私は毒親育ち?毒親チェックリスト

自分が毒親に育てられたかどうか、知りたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。以下に、毒親がとりがちな行動や子どもの反応を書き出してみました。過去の状況を思い出しながらチェックしてみてください。
毒親育ちチェックリスト
- 習い事は自分が望むものではなく、保護者が選ぶものしかやらせてもらえなかった。
- 兄弟やクラスメイトと比較されて、自分を否定する言葉を言われ続けた。
- テストや模試で高得点しか認めてもらえず、頑張っても褒めてもらえなかった。
- 保護者が認めた友達としか遊ぶことが許されなかった。
- 友達や恋人との外出は出かけた場所や何を話したかなど、すべて聞き出さないと納得してくれなかった。
- 「あなたが悪い」と決めつけられ、その言葉を信じてしまい、罪悪感を感じていた。
- 細かなルールを決められ、守らないと怒られていた。(例えば、お風呂は10分以内とか、家にいるときはリビングにいなければいけない、など)
- うれしいことがあっても、一緒に喜んでくれることはなかった。
- 進学先や進路などで親の希望を叶えようと頑張っていた。
- 身体的暴力、ことばの暴力があり、いつもビクビクしていた。
- 食事や洗濯などの身の回りの世話をしてくれなかった。
- 自分が親や家族の世話をしていた。
- 親がいつもアルコールや薬物の影響を受けていた。
- 大人になってからは、就職・仕事や結婚などで親の意見を優先していた。
いかがでしたか?
上記は診断するものではありませんが、もし当てはまる項目が多いようであれば、あなたの親は毒親だった可能性があるのかもしれません。その結果に「やっぱりね!」と溜飲を下げる人もいれば、「親のことを悪く言うなんて」と後味の悪さを感じてしまう人もいることでしょう。
カウンセリングの現場では、保護者を悪く思うことや反発することに抵抗を感じる人に出会います。保護者からの悪い影響を認めつつも、やってもらったこと、してもらったことを考えると、申し訳なさを感じるようです。
しかし、あなたが抱えている苦しさや痛みに素直になることと、親を拒否し、反発することは別の話です。まずは、自分の苦しさをそのまま認めてあげてください。
親に対して相反する気持ちを抱く人は少なくありません。あなた自身の気持ちや過去をありのままを見つめていくことが、毒親の負の連鎖を次の世代、自分の子どもに繋げないための最初のステップになるでしょう。
毒親の影響から逃れる6つの対処法
毒親との関係は、あなたが大人になったから終わるというものではないかもしれません。今ももし、毒親からの影響に傷つき続けているのであれば、子どもへの影響を考えてあなた自身が親との関係を見直してみてはいかがでしょうか。
親との関係をどうしたいか決める
まずは、あなた自身が親とどういう関係を作っていきたいのかを決めることが大切です。
親と良い関係をつくっていきたいと考えているのか、自分がイライラしなければOKなのか、親の影響を受けすぎないようにしたいのかなど、あなたが何に困っているのかをはっきりさせていくといいでしょう。
そして、どれくらいの距離感が自分にとって心地いいのかを考えてみてください。
例えば、
- まったく交流しない
- 年末年始やお盆だけ帰省する
- 直接会わず、電話やLINEでやりとりする
など、許容できる負担感の範囲で親とどう付き合っていくかを考えていきます。
親のコントロールの仕方やタイプを理解する
自分の親はどのような方法で、自分に影響を与えてきたのかを分かっておくと対策もとりやすくなります。上記で紹介している毒親の4タイプなどを参考に考えてみてください。
例えば、暴力や怒りや不機嫌でコントロールするタイプ、罪悪感に訴えてコントロールするタイプ、まわりと比較してコントロールするタイプなど、どんな形でコントロールしてきたのかを思い返してみてください。
物理的な距離をおく
もし物理的な距離をおけるなら試してみましょう。実家が近い場合、可能なら少しでも離れた土地へ引っ越すのも一つの手です。
また、理由や自分の用事をつくって接触する機会をコントロールしていくのもいいですね。同居しないといけない状況なら、同じ空間にいないようにしたり、家にいる時間を少なくしたりする工夫も考えられます。
また、直接話す、あるいは電話する際に、イライラや不安が高くなるのであれば、話す頻度を減らすなどをして自分の状態を整えるようにしましょう。
心理的な距離をおく
親の言動による影響を受けやすい状況は、親子の心理的な距離が近くなっているということです。
親の言動に自分の心が乱されたり、不安定になったりすることをやめたいのであれば、話しているときに親と自分の間に壁やさえぎるものをイメージしてみてください。
「なんだか馬鹿げているな」と思う人もいるかもしれませんが、実際にやってみると親から受ける心理的なダメージを軽減できることもあるのでぜひ試してみてください。
自分の感情に気づき、認める
自分が親から受けている影響と、その影響によってどんな感情が引き起こされるのか、ということに目を向けてみてください。
感情は、良いも悪いもなく、自然にわき起こってくるものであり、自分にとって大切なメッセージが隠されていることがあります。
たとえ、わき上がってきた感情が“怒り”というネガティブな感情であっても「親に対して怒りなんて感じてはいけない」と抑え込もうとせずに、怒りを認めましょう。そして、その怒りにはどんな意味があるのか、なぜこんなにイライラするのか、自分の感情を探求してみてください。
感情は自分自身が認めることで次第に小さくなっていく性質があります。もし、客観的に感情を見つめることが難しい場合、プロのカウンセラーの手を借りることを考えてもいいかもしれません。
自分自身の心を安定させる
親との健全な関係を築いていきたいと思うのであれば、まずは自分自身の心を安定させて、親と接していくことが求められるでしょう。
安定とは、興奮しすぎない、パニックにならない、頭が真っ白にならない、エネルギー不足で落ち込みすぎない、など、心と身体が平穏な状態であること、怒りや不安や恐怖に感情が大きく揺さぶられないことです。
心身を安定させるために自分なりのリラクゼーション法やストレス対処法などをつくっていきましょう。
この記事を監修した表 広大さんに相談してみませんか?
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で表さんに親子関係の悩みを相談できます。
表 広大さんへの相談ページを見てみる
自分は毒親?毒親度チェックリスト
このチェックリストは「毒親」という言葉を造ったスーザン・フォワードの著書「毒になる親」や「虐待早期発見のためのチェックリスト」を参考に作成しました。
毒親度チェックリスト
- 暴力や暴言を子どもに振るってしまったことがたびたびある
- 子どもに性的な行為や、性的な行動を見せたことがある
- 子どもに食事や清潔な衣類、住居を与えていない
- 子どもが病気やケガがあるのを知っていて、医療機関を受診させていない
- 子どもの言動が理解できず、イライラしてしまう
- 育児の仕方や子どもの将来に不安がある
- 自分の人生に不安や生きづらさを感じている
- 子どもの発言や意見を聞く前に、親側から行動を押し付けている
- 子ども部屋を勝手に散策したり、友人関係に対して常に監視をしている
このチェックリストに当てはまるからといって必ずしも毒親とは限りません。また当てはまらないからといって毒親ではない可能性もないわけではありません。少しでも客観的に自分の行動をふりかえるために、こちらのチェックリストをご活用いただければと思います。
自分が毒親と気づいたときの対処法
「自分は毒親かもしれない」と自覚したときに有効な対処方法のひとつが専門家によるカウンセリングです。カウンセリングでは、自分自身に向き合っていきます。その過程で、自分の中にある価値観や考えに気づいたり、カウンセラーとの穏やかで温かみのある関係性が子どもとの関わりの参考になったりするることもあるでしょう。
自分自身の親子関係に対してトラウマがあれば、トラウマ処理に特化した心理療法も効果があるかもしれません。
また、子どもの年齢によってその対処法を考えてもいいでしょう。
・子どもが低年齢の場合
就学前など低年齢の子どもであれば、親子合同面接、ICPT(親子相互交流療法)、ペアレントトレーニングなど、子どもと良い関わりができるようなアプローチから改善を進めてみることもよいと思います。
・子どもが学童期から青年期の場合
小学生から高校生くらいの子どもであれば、その年齢の心性や適した関わり方を知ることが親子関係の改善の助けになるでしょう。小学校低中学年とそれ以降の思春期では、ときに関わり方が真逆になるくらい意識して変えていくこともあります。
・子どもがすでに成人している場合
子どもが成人している場合、親を避けていることも多いものです。無理に近づこうと思ってもよい結果にはなりません。子どもの意思を尊重する態度や関わりを心がけていきます。
また、子どもとのより良い関わり方を具体的に学べるものとして「ペアレントトレーニング」もあります。行政機関や病院といった専門機関を中心に実施されている注目のプログラムです。
【関連記事はこちら】
・ペアレントトレーニングの種類や内容【Vol.1】
・ペアレントトレーニングの取り組み方【Vol.2】
毒親にならないためのたった1つのルール
親の育て方は、子どもの人生に大きな影響を与えます。ここまで自分の親との関係について解説してきましたが、親子関係に苦しんできたからこそ、「自分の子に同じ思いをさせたくない」「私はお母さん(お父さん)のようになりたくない」と思っている人もいるのではないでしょうか。
では、毒親にならないためにどんな親になればいいのでしょうか。
それは、子どもを一人の人間として尊重することです。尊重する態度といっても、ちやほやするということではありません。
例えば、あなたが家族以外の人と接する際の態度やスタンスをイメージしてみてください。
多くの場合、友人や同僚、近所の人に対して上から目線で接するようなことはないはずです。会話の中で意見や考えの違いがあったとしても、話し合って落としどころを見つけていこう、相手の考えを理解しようとするのではないでしょうか。自分のものさしで勝手な判断はしないはずです。
しかし、会社やプライベートの人間関係ではできていることが、なぜか子どもに対してはできないケースは少なくありません。
子どもが小さいときは、しつけや、世の中の社会的なルールを教えることが必要です。時には厳しいことを言わなければならないこともあります。しかし、「相手(子ども)を尊重する」「相手(子ども)の意見をきく」という態度を心がけていれば、自分の想い通りにコントロールしようとするのではなく、対等の人間として扱い、丁寧に説明してお互いに納得する落としどころを探れるでしょう。それができるならば、毒親にはならないはずです。
意見や考えを押し付けて無理強いしたり、気持ちを分かろうとしなかったり、話を聞かなかったりする態度は、対等性とはほど遠いものです。毒親になりたくないのであれば、これらと逆の言動や態度を心がけていくようにしましょう。
いきなり完璧にできるようにはならないと思いますが、繰り返し意識していけば改善できていくはずです。
自分がされてきたことについて、親を許せないと感じる人もいます。その気持ちも大切なものです。そんな自分の気持ちを大切にしつつ子どもを尊重して向き合ってください。
どうしても自分の子育てや態度、心の状態に不安がある場合は、躊躇せず、ぜひプロのカウンセラーの力も頼ってくださいね。
<参考文献>
「毒になる親」スーザン・フォワード(講談社)
「自分をドンドン傷つける「心のクセ」は捨てられる!」向後善之(すばる舎)
この記事を監修した表 広大さんに相談してみませんか?
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で表さんに親子関係の悩みを相談できます。
表 広大さんへの相談ページを見てみる
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!