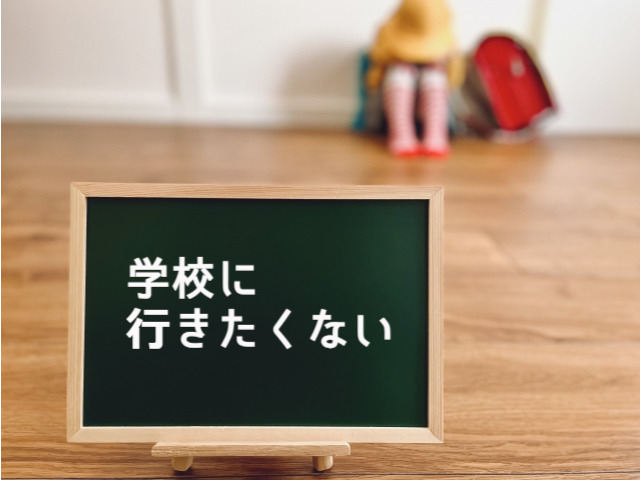【保護者に聞いた!】小学生の子どもに友達がいない…親にできることは?

自分の子どもに友達がいない…。小学校に上がると子どもだけで遊ぶことが増え、人間関係について心配になることもあるでしょう。今回は「小学生のわが子に友達がいない」と悩んだことのある15名の保護者に、自身の経験と親ができることを教えてもらいました。
目次
親はわが子の様子から友達関係の異変に気が付く
幼稚園や保育園時代と違い、小学生になると子どもだけで約束して遊ぶ機会も増えます。そして、何でも報告してくれた幼少時代と異なり学校生活の中で友達とのけんかや仲間外れといったトラブルが生じても、親に相談する子どもは少ないようです。
今回ソクたまの調査に協力してくれた保護者15名のうち、“友達がいない”ことを子どもから相談されたのは、わずか3名。友達関係をある程度は把握していても、親の知らないところでわが子が悩んでいるということは、少なからずあるようです。
教師や周りから教えてもらったという保護者は5名、残り7名は子どもの様子の変化から気が付いたそう。

先輩保護者がキャッチした“わが子の変化”
- 休日に誰とも遊ばなくなったし、学校でのできごともあまり話してくれなくなった。(5年女子/母)
- 授業参観に行くと、友達と話す様子がなくポツンとひとりでいた。(3年男子/母)
- 学校から帰宅した時の子どもの表情から感じ取った。(5年女子/父)
- もともとおしゃべりな性格で以前は学校や友達のことを詳しく話してくれたが、自分から話してくれることがなくなった(5年女子/父)。
※カッコ内は、子どもの性別と学年および調査に協力してくれた方の続柄。
では、そもそも子どもに友達がいない原因となったものは何だったのでしょうか。
小学生の子どもに友達がいない…その原因とは
友達関係で悩みやトラブルを抱える場合、仲間外れやいじめに結び付けて考えることは多いでしょう。しかし、大人にとってはささいだと感じることや予想できないようなことがきっかけとなることも大いにあります。

調査に協力してくれた保護者からは、“子どもに友達がいない”理由について以下のような回答が得られました。
“友達がいない”原因となったできごと
人間関係のトラブル
- 身に覚えのないことで悪口を言われ、人間不信に陥ってしまった。(5年女子/母)
- リーダー格の子の指示を聞かず、無視されるようになった。(5年女子/母)
価値観や趣味・ライフスタイルの違い
- 自分と友達との価値観や趣味嗜好が異なり、共通の話題で盛り上がることができなかった。(6年男子/父)
- 本格的に取り組んでいる習い事があったため、友達と学校以外で遊ぶ時間がなかった。(5年女子/母)
本人の性格
- 極端な人見知りで、話しかけられても意思表示がうまくできなかった。(2年男子/母)
- わがままですぐにカッとなる性格なため、周囲が離れていった。(4年男子/母)
環境の変化
- クラス替えで、仲良しの友達と同じクラスになれなかった。(3年女子/母)
親の影響
- 親の社交性がなく、子どもの友達関係に影響してしまった。(1年女子/母)
- 親の仕事の転勤が多く頻繁に転校、環境の変化が激しかった。(5年女子/父)
仲間外れが原因となったものもありますが、子ども同士の関係ではなく親が原因を作ってしまった場合や環境の変化もその原因として挙げられました。低学年の子ほど、コミュニケーションが苦手など内向的な性格が原因となることも多いようです。
また、子どもの大半は「友達がほしい」と感じていたようですが、中には身に覚えのないことで悪口を言われて人間不信に陥ってしまった子や、もともと一人で過ごすことが好きな子、周りに合わせるくらいなら「友達はいらない」と思っていた子もいました。

しかし、「一人でも、何でも話せる友達を作ってほしい」「友達と遊び、楽しく過ごしてほしい」と思うのが親心。実際、保護者の皆さんはお子さんにどのような対応をしたのでしょうか。
子どもに友達がいないと知った時、親が取った行動は?
“子どもに友達がいない”ことを知った時、多くの親は何らかのアクションを起こすのではないでしょうか。しかし、さりげなく子どもに気持ちを聞いてみても解決の糸口はなかなか見つけられないようです。
小学生になると、子どもは親に本心を話してくれないことも…
「友達と遊んだら?」「嫌なことを言う子は気にしなくていいよ」と何度か言いましたが、「面倒くさいので一人でいる方がいい」と言われました。また、学校に相談することも提案しましたが拒否されてしまいました(5年女子/母)
娘の様子の変化を感じ、「学校は楽しい?」と聞いたことがあります。しかし、あまり学校の話題に触れられたくはないようで「普通だよ」と答えてくれただけでした(5年女子/父)
中には、子どもと話をする機会を設けたものの、詳しく話してはくれなかったという人も…。親がフォローしようと思っても、そう簡単にはいかないようです。

相談することが解決への道筋になることも
親が子どもにできることとして、次に浮かぶのは妻(夫)や教師、ママ友への相談。わが子のこととなるとどうしても主観的に物事を捉えてしまう傾向にありますが、客観的な視点でアドバイスをもらえるため「相談して良かった」と考える保護者が多くいました。また、「話を聞いてもらうだけでも気持ちがラクになった」という意見もありました。
妻に相談したことで、別の視点でも考えることができました(3年男子/父)
学校の担任は、娘の状況を知らなかったそう。相談したことで、状況を共有できたのが良かったです(3年女子/母)
家族旅行やハイキング、ボランティア活動など「日常生活とは違った経験をさせることで、内向的な性格に変化があるかもしれないよ」という友人からのアドバイス。自分では考えもしなかったことを提案してくれました(3年女子/父)
「友達はいらない」と考えている息子。教師には「友達を作ろうと追い詰めるのは良くない。時期が来たら突然変わったかのように溶け込むことがあるかもしれないので、もう少し様子を見ましょう」とアドバイスされました。学校で目立つようないじめを受けているわけではなかったし、相談したことで安心できました(3年男子/父)

“子どもに友達がいない”悩みを解決した方法
いま現在悩んでいたり、解決することができなかったという家庭もありましたが、今回の調査に協力してくれた家庭の大半は“子どもに友達がいない”という心配事を解決しています。
学校以外の居場所を持つ
消極的な性格を変えるために、親子でボランティア活動に積極的に参加しました。次第に娘の表情が豊かになり、ボランティア活動で出会った大人に自分から話しかけられるまで成長しました。学校でも友達に話しかけ、遊べるようになっていきました(3年女子/父)
地域のスポーツクラブに入会させたことがきっかけで、内向的な性格に変化が表れ始めました。チーム競技のため気を遣い過ぎるという面が生かされ、息子も楽しんでいます。個人競技のスポーツだったら、ここまで変わらなかったかもしれません(5年男子/母)
子ども自身の努力や成長
価値観の違いに戸惑い、友達関係を築けなかった娘。自分と他人とは違うということを意識することで、徐々に友達ができ周りに溶け込めるようになりました(6年男子/父)
担任と娘、クラスメイトと話し合いの機会が持たれました。それがきっかけで仲良くなり、高校生になった今でも親友として付き合っています。今でも友達を作ることに神経質になっていることはありますが、自分から積極的に話しかける努力をしているようです(3年女子/母)
気の合う仲間と出会う
娘と同じようにグループに属することがあまり好きではないという子たちがいたことで、一緒に過ごせる友達ができたようです(5年女子/母)
時間が解決してくれる
小学生の間に解決はしませんでしたが、中学校に上がると娘自身が強くなったのか、上手にグループに入ったり友達の話題をしてくれたりするようになりました。今では、積極的にリーダーを務めることも。仲の良い親友が一人できたことが大きかったと思います(5年女子/母)
※学年は、当時のもの。
学年が上がるにつれて、少しずつ息子の性格が社交的に変わり友達が増えていきました(1年男子/母)
上の回答を見て分かるのは、親から子へのアドバイスや働きかけも大切ですが子ども自身の力で変えていく部分が大きいということ。また、深刻な状況でなければ時が解決してくれることもあるようです。

親子で会話する工夫も大切。親の接し方のコツ
公認心理師の佐藤めぐみさんは、以前の記事で「子どもが成長するに連れ、親自身の観察力=察する力」が問われると話しています。
【親に必要な“察する力”についての記事はこちら】
ママ友の態度や子どものことが気になり過ぎる。マイナス思考への処方箋はある?

「一緒にお風呂に入っている時、一緒にご飯を作っている時など親子二人きりになれる時間に相談してくれた(3年女子/母)」という回答がありましたが、子どもが親に話しやすい/相談しやすい環境作りも大切だということが分かります。
「どうしたの? 何があったの?」と問うても、答えてくれない子どもは少なくありません。また、親に問い詰められることがストレスとなり状況を悪化させてしまうこともあるでしょう。親子の会話の中で「困ったことがあったら、相談してね」ということは伝えつつ、ある程度の見守る姿勢も大切です。
子ども自身で考え行動する力を身につける、それが親のできる子どもへの寄り添い方なのではないでしょうか。「学校や外で嫌なことがあっても、家に帰ったらホッとできる」「お母さんやお父さんの顔を見たら安心する」。子どもをサポートする、そんな家庭の温かさが解決の起点になるのかもしれません。
<関連記事>
小学生の子どもに友達がいないという悩みの裏には、発達の問題などの要因がある可能性も考えられます。また、友達がいないことで「学校に行きたくない」と思う子もいるかもしれません。気になる方は、以下の記事も参考にしてみてください。
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

岩手県出身。大学卒業後、ゲーム会社で広報宣伝職を経験した後、ママ向け雑誌やブライダル誌を手掛ける編プロに所属。現在はフリーランスのエディター&ライターとして活動中。一人息子の中学受験で気持ちに全く余裕がない中、唯一の癒しとなっているのが愛犬と過ごす時間です。