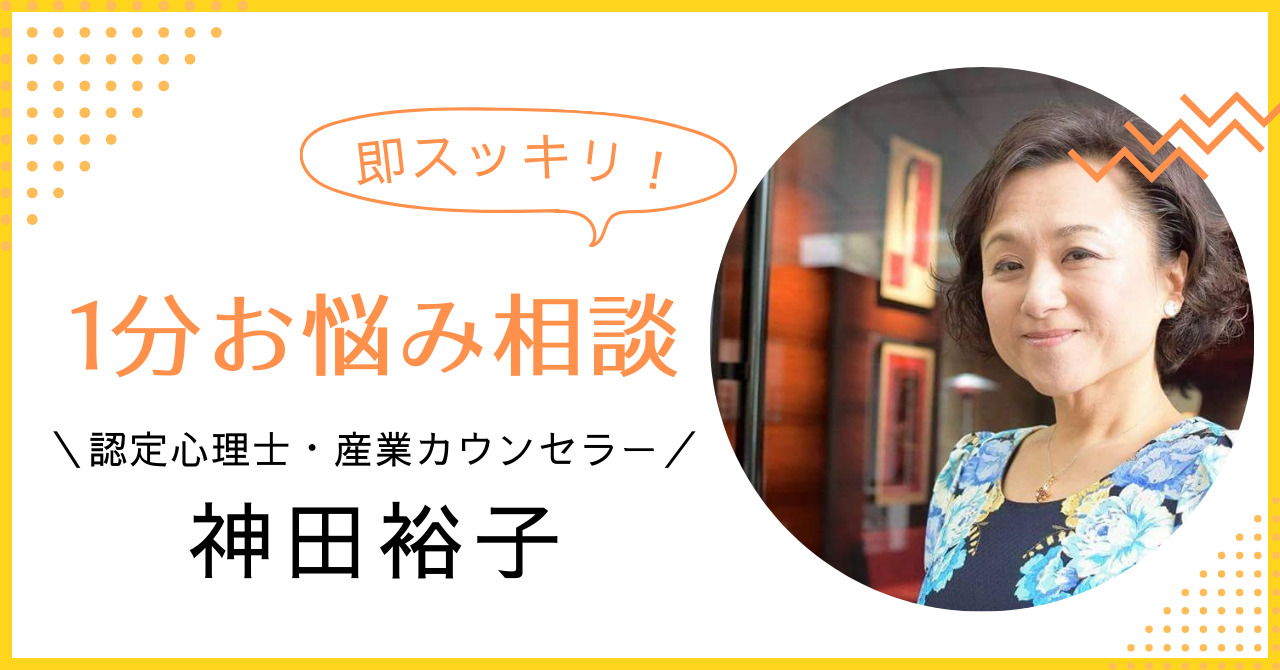子どものアンガーマネジメントとは?感情コントロールの5トレーニング【第13回】
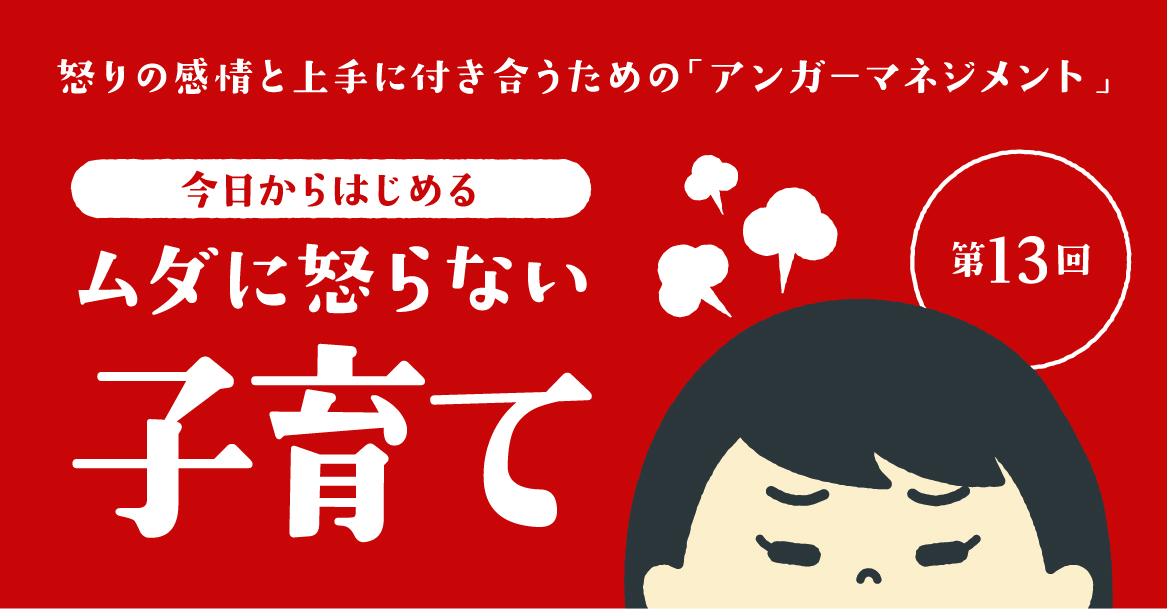
子どものイライラや癇癪に困っていませんか?自分の感情をコントロールすることは、子ども自身にとっても意味のあることです。この記事では、子ども自身が怒りの問題に気付くための方法や小学生でもできるアンガーマネジメントのトレーニング方法を紹介します。
子どもはアンガーマネジメントを望んでいるか?
具体的なアンガーマネジメントのトレーニングを教える前に気をつけて欲しいことがあります。それは、子ども自身がアンガーマネジメントの必要性を感じているかということです。本人が「怒った後で落ち込んだり、悔やんだりして困っている」「怒りっぽいのを何とかしたいと思っている」のでしたらトレーニングを続けていくことができるでしょう。
しかし、感情のコントロールは一日で身につくものではありませんし、他の誰かが変わって何とかできるものでもなく、本人が主体的に取り組まないと意味がないのです。ですから、子ども自身が何のためにアンガーマネジメントをする必要があるのか知っておくことが大切なのです。
子ども自身が怒りの問題に気づけるように、子どもがアンガーマネジメントに取り組む際、動機づけの一つとして、次の質問をしてみるのもよいでしょう。本人にイエスかノーで答えてもらいましょう。
子どもが怒りの問題を知るための5つの質問
①思うようにならないと大声を出したり、暴力的になったりしてしまう。
②怒るとなかなかおさまらず、エスカレートしてしまう。
③怒っていることを上手く伝えられない。
④普通にしていても怒っているように見えてしまう。
⑤怒ったあとケンカになるなど、よいことがなく嫌な気持ちになる。
もしひとつでもイエスがあれば、怒りの感情と上手くつきあうアンガーマネジメントを学ぶ意味があるといえますね。例えば、漢字が書けるようになる、自転車が乗れるようになることと一緒で、毎日少しずつ練習をしながら経験を重ねて身につけていくことで、感情の爆発や怒りに支配されずに済みます。
もう少しいえば、怒りを感じたとしてもその先どうするか最善の方法を自分で選択していく力がつくということです。
子どもが自分の感情の動きに上手に対応できるようになることは、家庭の中だけでなく学校生活での友達関係を円滑にするなどのメリットがあります。その一歩目として、子ども自身が怒りの問題を自覚することから始めてみましょう。

怒りは、子ども自身で対処できるということを伝えて
そもそも“怒り(感情)”と“怒りの表し方(行動)”は違います。子ども自身が小さいうちから“感情”と“行動”を区別することができていたら、かんしゃくを起こして当たり散らしたり、反抗的な態度をとり続けたり、攻撃的になって誰かや自分を傷つけてしまって後から罪悪感や後悔するということは減るはずです。
怒りを感じたときにやってはいけないことは、とっさに言い返したり仕返したりする行動をとることです。体を使って感情のピークである6秒をやり過ごす方法はこちらの記事で紹介しましたが、今回は、怒り(感情)を感じたあと、かんしゃくを起こす・反抗的な態度等(行動)に繋がる流れを中断させる方法を紹介します。
子どもに伝える際には、「『カチンときた』『頭にくる』など、怒りを感じたときに、何もしないと“怒りモンスター”が暴走して、暴力をふるったり、暴言を吐いちゃったりするよね。“怒りモンスター”を発動させないためには、自分に魔法をかけることもできるし、発動スイッチを切り替えることだってできるんだよ」と話してみると子どもにも分かりやすいかもしれません。自分で対処できるというイメージをもたせると子ども自身が取り組みやすいと思います。

子どもが実践しやすい5つのトレーニング
それでは、いよいよ、子どもが実践しやすい5つのトレーニング方法を紹介するので試してみましょう。小学生や中学生もすぐに取り入れることができる内容なので参考にしてくださいね。
気持ちが落ち着く言葉をつぶやく
イライラしはじめたら、「だいじょうぶ」「気にしない」「落ち着け」などの言葉を自分にかけてみましょう。ちなみに小学生の私の息子は、「ドンマイ」とつぶやいています。結構大きな声で言っているので“つぶやき”のレベルではなく、自分への“言い聞かせ”になっていますが…(笑)。
以前、小学校でアンガーマネジメントのワークをした時のことです。ある子が「飼っているペットの名前をつぶやくと気持ちが落ち着く」と話してくれました。確かにかわいがっているペットの名前をつぶやき、思い出すと気持ちがほぐれる感じがしますよね。
ただし、大事な注意をひとつだけ。「この野郎」「クソッ」「バカ」など、気持ちを高ぶらせたり、相手を挑発したりするようなつぶやきはNGですよ。
頭を真っ白にしてみる
これは、得手不得手があるかもしれません。カァーッとなったときに目をつむって頭を真っ白にしたり、黒いモノが消しゴムで消えていくイメージをしてみましょう。頭が空っぽになる感じでもいいですね。上手くできれば、怒っていることが何だかちっぽけに思えてくることがあります。
動きを止める
むかついたときなど、いったん自分の動きを止めてみましょう。自分に魔法をかけて、“凍りつく”あるいは“石になる”イメージでもいいですよ。何も言わない、何もしないという時をわざと作るのです。好まないケンカを引き起こさないように、怒りのまま何かをしでかさないようにしてくれますよ。
数を数える
頭にきたとき、いったん目を閉じてゆっくりと「1,2,3,4,5,6…」と数を数えたり、英語で「ワン・ツー・スリー…」と数えてみましょう。九九の苦手な段を思い出す、九九を後ろから唱えてみるというのも怒りから意識が離れるのでいいですね。
前向きになる言葉を自分にかける
「許せない!」と思ったとき、あえて「何ができる?」「どうしたらいい?」と自分に声をかけてみましょう。解決に向けて考えていこうという前向きな気持ちになることができます。怒りにまかせて誰かを責めたり自暴自棄になってやる気を無くしたところで、状況は変わらないか、むしろ悪化してしまいます。みじめな気持ちになって自分を責めてしまうこともあるでしょう。怒りは破壊のエネルギーではなく、建設的なエネルギーに変えていくことができるのです。
子どものアンガーマネジメントのために親ができること
子どものアンガーマネジメントのトレーニングとあわせて、親にもできることがあります。例えば、子どもの怒りのパターンを知るために親子で怒りを共有する、親自身が怒りの表し方を見直してみるといったことです。詳しくは以下の記事で紹介しているので、こちらも参考にしてください。
<こちらの記事もチェック>
・子どものアンガーマネジメント 子どもがどんなときに怒っているのか聞いてみよう
・親の怒り方を見て子どもは育つ 怒りっぽい子に育てないためのルールとタブー
今日紹介した方法は慣れてしまうと効果が下がってしまいます。そのため、毎回同じ方法を使わない、あるいは前回の記事で紹介した体を使った方法と組み合わせてやってみるのもいいですよ。
今日からできることを少しずつトレーニング。アンガーマネジメントにレッツトライ!
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会(東京)アンガーマネジメントファシリテーター。子育てや教育・福祉・司法関係において、心に触れる実践的なアンガーマネジメントを伝え、一人一人が大切にされる教育社会を目指して怒りの連鎖を断ち切るために活動を続けている。著書に「マンガでわかる怒らない子育て」(永岡書店)「イラスト版子どものアンガーマネジメント~怒りをコントロールする43のスキル」(合同出版)などがある。 https://www.angermanagement.co.jp/