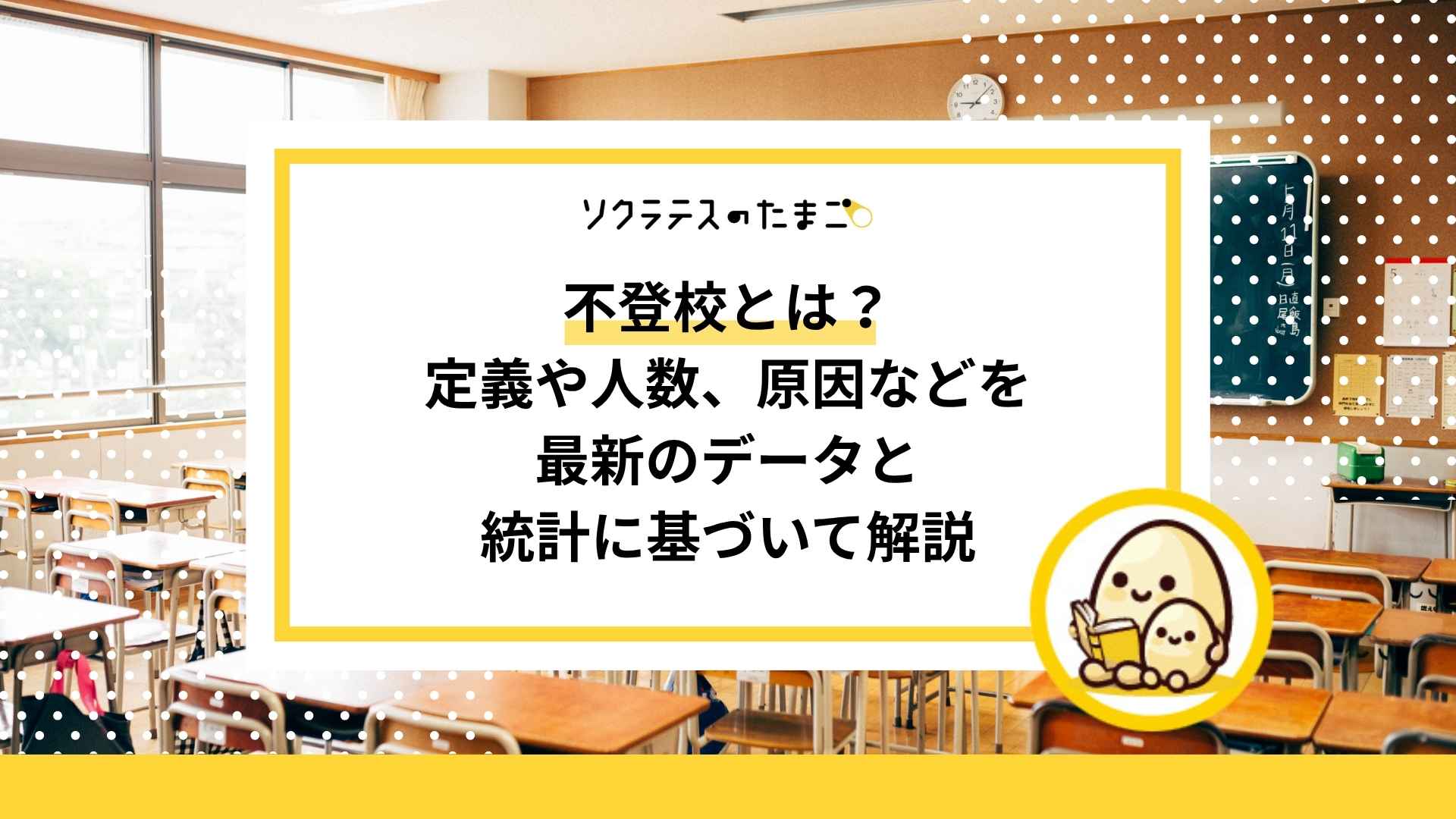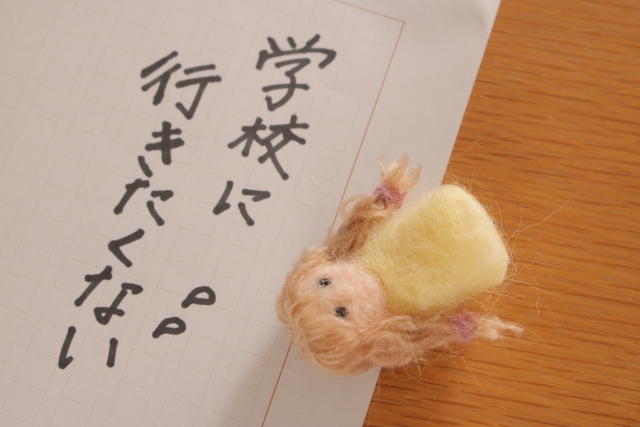ブラック校則とは?背景や子どもたちと教員にもたらす問題点を徹底解説

ブラック校則とは、一般社会から見て不合理な校則のこと。本記事では、ブラック校則ができた背景や子どもたちや教員にもたらす問題点はもちろん、具体的な校則例や廃止に向けた取り組みなども紹介しています。ブラック校則について詳しく知りたい方はぜひ最後までご覧ください。
「ブラック校則ってなに?」
「ブラック校則ってなんでできたの?」
ブラック校則によってどのような問題が起こっているのか知りたいという方も多いのではないでしょうか。納得いかない校則を守らされる学生、それを指導する教員のフラストレーションにつながります。
本記事では、なぜブラック校則が生まれたのか、ブラック校則によって起こる問題について詳しく紹介します。また、ブラック校則が廃止になる見通しがあるのかについても解説しています。
ブラック校則について詳しくなりたい方は、ぜひ最後まで読んでください。
目次
ブラック校則とは?一般社会・常識から見て不合理な校則のこと
ブラック校則という言葉は、辞書に載っているものではなく、明確な定義はありません。
ブラック校則をなくすために活動している『「ブラック校則をなくそう!」プロジェクト』では、ブラック校則を以下のように定義しています。
「一般社会から見れば明らかにおかしい校則や生徒心得、学校独自ルールなどの総称」(引用:「ブラック校則をなくそう!」プロジェクト)
些細な外見や服装の特徴を執拗に規定し学校の雰囲気を悪くするもの、無理に対応して生徒の健康を害する恐れのあるもの、生徒のプライバシーを侵害しかねないものなど、様々な問題のあるブラック校則が存在しているようです。
本来の校則がある理由|ルールの理解と自制心を育てるもの
校則は、1873年に文科省が発表した「小学生徒心得」が始まりとされています。同心得には、「朝早く起きること」「勉学に励むこと」などのルールが記載されていました。
その後、1980年代頃問題となった校内暴力や非行、近年問題になっているいじめを取り締まるために年々厳しさが増していきました。
時代に合わせて変化してきた校則ですが、「生徒の自由や個性を過度に制限する」と批判があるのも事実です。校則は、学生が社会で生活していく上で必要な行動様式や礼儀を身につける役割を持っています。しかし、それを実現するためには、時代や社会の変化を踏まえた柔軟な適用が必要です。
学校のブラック校則ができた理由とは?
校則の中には「ブラック校則」と呼ばれる校則があります。ブラック校則とは、過度に厳しい、または時代遅れで不合理な校則のことを言います。
時代に合わせてブラッシュアップしてきたはずの校則に、なぜブラック校則と呼ばれるものが生まれたのでしょうか。理由は主に3つあります。
- 若者の非行行動の改善
- 近隣の住民からのクレーム対策
- 学校のアピール
それぞれの理由を解説します。
理由①若者の非行行動の改善
1980年代、学生の非行行動が問題視されていました。不登校、暴力行為、万引き、喫煙・飲酒などのさまざまな非行が頻発していたのです。
そのような学生の非行を取り締まるための校則ができ、学生の非行が減少しました。学生の非行はかなり減りましたが、「非行を事前に防ぐ」という目的で、校則として残している学校が多くあります。
理由②近隣の住民からのクレーム対策
学校は、近隣住民から理不尽なクレームを受けることもあります。例えば、以下のようなクレームです。
- 学生の登下校中の態度が気に食わない
- 学生があまり楽しそうにしていない
- 他の学校の学生と比べると学力が低い
理不尽な内容であっても、学校としては近隣住民からのクレームをしっかりと聞き、解決に向けた手段のひとつとして校則に反映する場合があります。
このように制定された校則は、学生にとって面倒だと感じる内容があるため、ブラック校則だと捉えられる傾向にあります。
理由③学校のアピール
厳しい校則は、規律正しい学校だというイメージにつながります。
規律正しい学校というイメージがあれば、地域から評判の良い学校になりますし、入学希望者の増加も見込めます。近隣住民や保護者と良い関係を築くことは、学校の運営側にとっては重要なことです。
しかし、学生への制限が厳しい学校都合の校則は、学生からブラック校則だと捉えられることもあります。
具体的なブラック校則とは?おかしい校則例一覧
学校によってさまざまな校則が設けられています。中には、ブラック校則と呼べるほど意図がわからないものも……。
中高生や高校職員が回答した「これはおかしい!」と思うような校則は下記が挙げられます。
| 系統 | 校則 |
| 服装 | ・腕時計禁止・腕まくり禁止・マフラーは原則白黒等のみ・白のスニーカーのみ・猛暑日でも制服・迷彩禁止・日傘は許可制・長靴禁止・キーホルダーは一個まで |
| 頭髪・身だしなみ | ・髪の長さ(両肩より上)・流行を追った髪型の禁止・髪が長すぎると原則三つ編み・編み込み禁止・日焼け止め禁止・爪磨き禁止 |
| 学校外の活動 | ・旅行許可証が必要・カラオケ / 映画禁止・麻雀禁止 |
| 学習関連 | ・予備校禁止・模試が休日・共通テスト受けないと卒業できない |
| 行事 | ・瞑想の時間がある・文化祭でハート禁止・文化祭のお化け屋敷でも電気消すの禁止 |
| 恋愛 | ・男女2人きりで勉強してはいけない・男女が手をつなぐこと |
| その他 | 漫画が没収されると売られてしまう |
炎天下、通学する生徒たちは熱中症の危険にさらされています。それなのに「猛暑日でも制服」「腕まくり禁止」「日傘は許可制」、さらには「日焼け止め禁止」というのはさすがに根拠を問いたくなってきます。
学習関連でも根拠のわからない校則が続きます。「予備校禁止」とは、学習を推奨していないのでしょうか。
恋愛についても同様で、「男女が2人きりで勉強してはいけない」「男女が手をつなぐこと」など、ひと昔前の香りがただよいます。「文化祭でハート禁止」も、いったいなぜなのでしょうか。
頭髪や身だしなみにも、昭和から抜け出せていない感があります。「髪の長さ(両肩より上)」「髪が長すぎると原則三つ編み」って、昭和のモノクロ写真に写っている学生そのものではないでしょうか。
ブラック校則例①下着の色指定
スタディプラスは、中高生5697名・高校職員209名を対象に「学校のルールについての意識調査」を行いました。
「以下の中で、自分の高校にある校則(近いものも含む)をチェックしてください」と質問したところ、このような結果になりました。
出典:PR TIMES
「下着の色」は、高校生(11.1%)よりも中学生(25.3%)のほうが規定がある学校が多いようですね(いったいどのようにチェックするのでしょうか……)。
「メイク禁止」は中高生どちらも7割程度になりました。「特定の髪型(ツーブロックやパーマなど)の禁止」も、中高生ともに高めです。
頭髪はこの「特定の髪型の禁止」を含めて、「黒染めの義務化」「地毛証明書の提出」の項目とも連動している気がします。
地毛証明書がどのようなものか分かりませんが、保護者が記入するのでしょうか。いずれにしても、さすがにここまでいくと“やりすぎ感”が否めません。
ブラック校則例②ツーブロックの禁止
ツーブロックを禁止している学校は多いのではないでしょうか。ツーブロックとは、サイドを刈り上げた髪型のことです。
ツーブロックが禁止されている理由は、「外見が原因で事件や事故に巻き込まれる可能性があるため」とされています。しかし、ツーブロックは美容室に行くとカタログに載っているなど、一般的な男性の髪型です。
そのため、納得がいかない男子生徒が多く、ブラック校則と捉えられています。
ブラック校則例③地毛証明・頭髪届
地毛証明・頭髪届とは、髪の毛を染めたり、パーマをしたりしていないことを証明するための届け出です。つまり、自分の髪の毛が地毛であることを証明するものです。
生まれつき髪の毛が明るかったり、くせ毛の学生もいます。
しかし、それが地毛であることを証明する届け出が必要なケースがあるようです。髪の毛の色が明るすぎる場合は、地毛であっても黒染めを求める学校もあります。
ブラック校則がもたらす3つの問題点とは
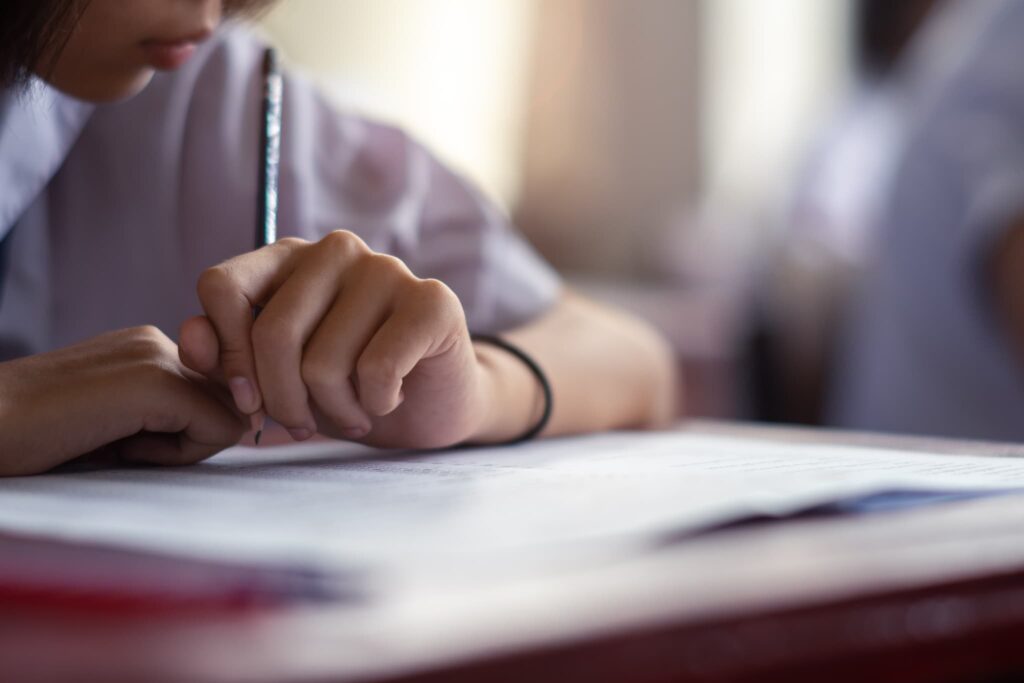
ブラック校則が、ただ制限が厳しいだけの校則ならそれほど問題はありません。
しかし、ブラック校則があることで次のような問題点が発生しています。
- 人としての尊厳を傷つける
- ハラスメントに繋がる
- 教員のストレスに繋がる
それぞれの問題点を解説します。
問題点①人としての尊厳を傷つける
髪の毛の色や髪型にはそれぞれの好みがあります。
また、地毛が明るいことや、くせ毛なのは生まれつきの特徴です。髪の毛や地毛を統一するような校則は、人の尊厳を傷つけることになり得ます。
また、近年はグローバル化が進んでいるため、学校に外国籍の子がいることも珍しくありません。
それぞれが持つ特徴を理解し合うことが重視される時代の流れに逆行する校則といえるでしょう。
問題点②ハラスメントに繋がる
ブラック校則として有名なのが「下着の色の指定」です。
下着の色の指定は、教員によるチェックがセクシャルハラスメントに該当する可能性もあります。
また、近年学生への体罰が問題視されています。校則に従わない学生に対して度を超えた指導を行い、体罰だと捉えられるケースもあります。
問題点③教員のストレスに繋がる
無くても良いブラック校則は、教員のストレスにもつながります。納得のいかない内容でも、学校の決まりとして生徒に指導する必要があるためです。
仮に理不尽な校則を守るよう指導しても、その指導が体罰と捉えられると保護者からのクレームにつながります。
ブラック校則は、学生だけでなく教員のストレスの要因にもなります。
ブラック校則の廃止に向けた取り組みとは?

本来の校則の趣旨から逸れたブラック校則は、さまざまな問題を引き起こす原因となり得ることを解説しました。
では、このブラック校則を廃止に向けてどのような取り組みがされているのでしょうか?
実際に行われている取り組みは以下の通りです。
- 「ブラック校則をなくそう!」プロジェクトの発足
- 文部科学省の「生徒指導提要」の改訂
- 教育委員会単位での拘束の見直し
それぞれどのような取り組みかを解説します。
取り組み①「ブラック校則をなくそう!」プロジェクトの発足
2019年8月に、「ブラック校則をなくそう!」プロジェクトが発足しました。
このプロジェクトは、下記のNPO法人理事長やLGBTアクティビストが運営しており、子どものためにならない理不尽な校則の見直しを目的にしたプロジェクトです。
NPO法人理事長は、特定非営利活動法人の最高責任者であり、組織の運営や管理を総括する役割を担う人物です。また、LGBTアクティビストは、性的少数者の権利や平等を推進するために活動する人々のことを指します。
| 法人名 | 運営者氏名 |
| 認定特定非営利活動法人キッズドア(NPO Kidsdoor) | 渡辺 由美子 |
| NPO法人ストップいじめ!ナビ | 荻上チキ |
| マネックスグループ株式会社 | 松本 大 |
具体的な取り組みの1つとして、2019年にブラック校則に対する署名を6万以上集め、文科省に要望書を提出しています。
取り組み②文部科学省の「生徒指導提要」の改訂
文部科学省は、2021年6月に発表した「校則の見直し等に関する取組事例について」の中で、校則を見直す必要性があることや校則本来の目的に言及しています。
そして、2022年に生徒指導提要の改訂に動きました。
文部科学省が生徒指導提要の改訂に動いたのは実に12年振りのことです。
取り組み③教育委員会単位での校則の見直し
校則見直しの動きが徐々に強くなり、教育委員会単位での校則の見直しが行われました。
例えば、東京都では都立の各高等学校が、Googleフォームにて生徒の意見を募ったり、教員・学生・保護者が意見交換できる仕組みを整えました。
髪の毛の色や、下着の色の指定に関する校則計6項目の改定が行われています。
ブラック校則に関するよくある質問
ブラック校則に関してよくある質問を紹介します。
- ブラック校則はなぜなくならないの?
- 中高生は校則を厳しいと感じている?
- 先生たちは学生だったころは校則を守っていた?
それぞれの質問へ順に回答します。
ブラック校則はなぜなくならないの?
ブラック校則が無くならない理由としては、昔の校則を見直していく文化が学校空間にはないからと言われています。
社会の空気や生徒たち自体の在り方が変わってきているにも関わらず、歴史を重んじて現在を見直す文化がなければ、ブラック校則は無くならないといえるでしょう。
中高生は校則を厳しいと感じている?
思春期真っただ中の学生たちは、各種ブラック校則にいろいろ思うことがあるのでしょう。
スタディプラスのアンケート調査で、「校則を厳しいと感じているか?」の質問に関する地域別の集計では、以下のような結果になっています。
出典:PR TIMES
「厳しすぎる!」と感じている県はそれほど多くなく、「中の上」レベルの厳しさのようです。
さまざまなブラック校則が並んでいますが、意外と学生たちも寛容なのでしょうか。
先生たちは学生だったころは校則を守っていた?
ちなみに高校の先生方が学生だったころは、生徒として校則を遵守していたのかというアンケートでは、以下のような結果が出ています。
出典:PR TIMES
なんと半数以上が「なんの校則違反もしなかった」と回答しています。しかし、下記のような意見も見受けられました。(回答ママ)
- オシャレに目覚めてパーマかけて指導されて直したことはある。
- バイク3無い運動(※)が高校1年で始まり、校長に法的根拠を示すように生徒会として質問文を書いた。生徒総会で校長は欠席し、大騒動になった。
- 生徒会執行部に入った時、白色指定だった靴下の色を紺色や黒も認めて欲しいと抗議し、総会でその案が通りました。自主的な活動が校則の変化につながると実感することができました。
※編集部注:バイク3無い運動とは、1970年代に一部の県や学校で行われていた、高校生にバイクの「免許を取らせない」「買わせない」「運転させない」の3つを指針とした運動のこと。
思春期だからこそ、おしゃれと校則の間で葛藤することもあるようです。また「これはおかしい!」と自主的に抗議活動をおこなった方もいます。
まとめ

今回は、理不尽な校則として問題視されている「ブラック校則」について解説しました。
ひと昔前ならある程度当たり前だったかもしれませんが、今は令和です。
先生と話し合いながら意義のあるルールを決め、校則をブラッシュアップしていく必要があります。
本記事をきっかけにブラック校則が少しでも減り、教員と学生が快適な学校生活を送れることを願っております。
もし、お子様がブラック校則が原因で悩んでいたり、不登校になっていたりする場合は専門家への相談するのも選択肢のひとつです。
学校は毎日通う場所なので、そこで受けるストレスは子どもにとって大きな影響があります。
ソクたま相談室では、子育ての専門家がオンラインで相談を受け付けています。一人で抱え込まず、まずは一度お気軽にご相談ください。
<関連記事>
・日本の「ジェンダーステレオタイプ」とは?男性=賢い、女性=優しい…具体例や子どもへの影響
・不登校の原因・理由を解説|親が家庭でできる対応とNG行動とは?
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!