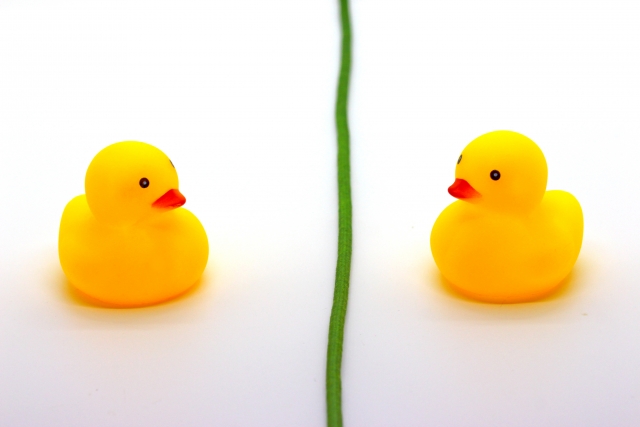子どもが夏休みの宿題を終わらせたくなる!応用行動学をヒントにしたアイデアとは

夏休みももうすう折り返し地点。思うように宿題が進んでいないことにヤキモキしている保護者も多いのではないでしょうか。そこで今からでも間に合って、子どもが自ら宿題をしたくなるアイデアを紹介します。
目次
嫌な夏休みの宿題を成功体験に変えよう
発達が気になる子どもの療育法として取り入れられている「ABA(応用行動分析)」を知っていますか?
「ABA」とは、子どもの行動のだけでなく、行動の前(きっかけ)後(結果)に着目して子どもへの理解を深め、効果的なアプローチをしていく方法論です。
今回紹介するのは、この「ABA」の考え方をヒントにした夏休みの宿題の進め方。子どもが宿題に取り組みたくなるきっかけや結果を明確にして、宿題へのモチベーションを刺激していくのがねらいでです。

【準備・考え方】材料を用意しよう
まずは、計画を立てるための準備をしましょう。今回提案する夏休みの宿題の進め方では、下記の材料を使用します。
- 宿題を書き出す紙
- 宿題数分のシールを貼ることができるシート
- 宿題を終えたらシートに貼るためのシール
要は、宿題をしたらシールを貼っていくだけなのですが、シールの枚数設定などは子どもの意見を取り入れていきます。
シートは宿題数のシールが貼れるのであれば、自作でもいいですし、トイトレで使った人もいるような、すごろくのようになった市販のシートを購入してもよいでしょう。
【ステップ①】宿題を書き出し、大変さをシールの枚数に反映する
どのように宿題計画を立てて、進めていけばいいのか紹介していきましょう。
ますは、紙などに今後やらなければいけない宿題をすべて書き出します。ただし「夏休みのドリル」などと、ざっくりとではなく「算数15ページ、国語10ページ」など、細かく具体的に書くようにしましょう。
次に、それぞれの宿題から矢印を伸ばし、その宿題を行ったらシールを何枚貼るかを子どもが設定します。
シールの枚数は、その宿題をする大変さに合わせて決めていきます。枚数に上限は決めずに、子どもの気持ちを尊重しましょう。
例)算数が苦手で、読書感想文や自由研究が負担になっている子の場合
- 問題集(国語10ページ)→1ページ/シール1枚
- 問題集(算数15ページ)→1ページ/シール2枚
- 読書感想文→シール5枚
- 自由研究→シール5枚
- 絵日記→シール3枚
すべてを書き出したら、シールの合計枚数を数えてみましょう。
シールの合計数や設定枚数で子どもが何をどの程度大変だと感じているのかが分かり、子どもの気持ちを理解することに繋がりそうです。
【ステップ②】ごほうびを設定する
次に、【ステップ①】で判明した全枚数のシールを貼り終える(宿題をすべて終える)までに、いくつか「ごほうびポイント」を設定します。
宿題を終えたら、その都度、設定された枚数のシールを貼り、シールの枚数が「ごほうびポイント」に達したら、ごほうびがもらえるという仕組みです。どこに「ごほうびポイント」を設定するかは、子どもと相談して決めてくださいね。
前半はこまめに「ごほうびポイント」にたどり着けるように配置にし、後半は「ごほうびポイント」が少なくても、特別感のあるごほうびを用意しておくとモチベーションがキープしやすいですよ。
もちろん「宿題をすることにごほうびをあげるの?」と違和感がある人もいることでしょう。ですが、大人でも苦手な仕事、大きな仕事を終えた自分にごほうびを挙げる人は少なくありません。しかも、子どもにとって「ごほうびを得ること」「努力を目に見える形にすること」は、成功体験のひとつになりえます。
子どもの中で宿題や勉強に対する意識が、ポジティブに変わることは、今後も学習を習慣化させるきっかけになり、いつかごほうびがなくても自ら学習できるようになるかもしれませんよ。
ごほうびはどんな内容がいいの?
ごほうびの内容は、子どもと相談しながら決めていきます。
前半のごほうびは「パパとのキャッチボール」「ゲームを10分延長権」「おやつにケーキ」「カレーパンを2個」「夜ご飯を焼き肉にする」「木の上で昼寝」など、親の負担が少なく提供しやすい内容がおすすめ。
後半の特別感のあるごほうびは、「ディズニーランドへ行く約束」「ゲームを買う」などはいかがでしょうか。
うれしいごほうびを考えることで「宿題=楽しいこと」と感じてくれたら、宿題を意欲的に取り組むことに大きく前進です!
【ステップ③】宿題をして、シールを貼っていく
あとは、宿題をしていき、達成した分のシールを貼っていきます。シールを貼っていくことで、日々の努力が目に見えるので、子ども自身も達成感を感じることができます。
保護者も進度がひとめで分かるので、「宿題やったの?」と聞く必要もないですし、「宿題をやりなさい」とやみくもに急かすのではなく、「ドリルをあと4ページやったらごほうびだね」と、モチベーションを刺激するような声掛けをできそうです。
また、シールやすごろくを用意するのが面倒な人や、新学期が始まって以降もごほうびシステムで学習を習慣づけさせたい人におすすめなのがコクヨの「しゅくだいやる気ペン」。装置を付けたえんぴつを動かした分、連動させた専用アプリにエネルギーを注入することができ、すごろくゲームを進めていくことができます。
夏休みの最後になって必死に残った宿題を終えなくてもいいように、少しでも楽しく宿題を進められるようにサポートできたらいいですね。
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!