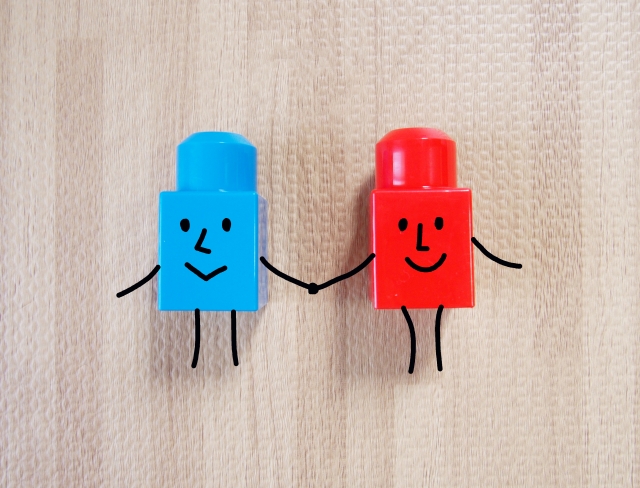包括的性教育とは?日本の性教育の現状やはどめ規定、家庭での性教育まで徹底解説

現代社会では子どもたちが膨大な情報を手軽に得られるからこそ、正確な性に関する知識を体系的に学ぶ機会が欠かせません。
そこで本記事では、「包括的性教育」がいったいどのようなものなのか、従来の性教育とは何が異なるのか、そして日本の現状や課題、家庭でのアプローチなどについてできるだけ詳しく解説します。
なお、この記事は特に保護者の方を想定読者としています。子どもが育つ過程で、学校だけでは十分にカバーできない部分を家庭でどのようにサポートしていけばいいのか、国際標準に近い形の性教育を実現するために何が大切なのか、これを機に一緒に考えてみましょう。
目次
はじめに:なぜ今「包括的性教育」なのか

近年、世界保健機関(WHO)や国連児童基金(UNICEF)、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)などの国際機関が、「包括的性教育」の重要性を強く訴えるようになってきました。性教育と言うと、「思春期に入る前後で、男女の身体の違いを教え、性交や避妊、妊娠に関する基礎知識を伝える」というイメージを抱く人が多いかもしれません。しかし、国際的に推奨される性教育は、それだけにとどまらない広範な内容を含むものです。
子どもたちはインターネットの普及により、いつでも様々な情報に触れられる時代を生きています。その中にはもちろん性に関する情報も多く含まれますが、玉石混交です。不適切な情報に触れてしまい、誤った知識や偏見を身につけてしまうリスクも無視できません。また、日本では未成年の妊娠や性感染症、性的マイノリティへの差別や偏見、望まない性行為などに関する問題も後を絶ちません。
こうした社会背景がある中で、狭義の「性行為」だけでなく、ジェンダー平等や多様な性、身体の尊重、人間関係づくり、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)などを含む「包括的性教育」の実践が世界的に求められているのです。
包括的性教育とは何か
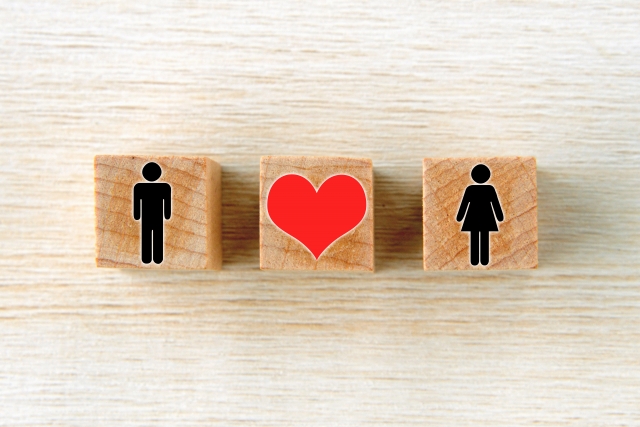
包括的性教育の定義
包括的性教育(Comprehensive Sexuality Education:CSE)とは、「人間の性に関して包括的に学ぶ教育」を意味します。ここでいう「包括的」とは、単に性交・避妊・妊娠などの生物学的な知識を教えるだけでなく、ジェンダー、性的指向、性自認、恋愛やパートナーシップ、コミュニケーションスキル、性暴力防止など、多角的な視点で性をとらえるアプローチを指しています。
従来の性教育は、どちらかと言えば「望まぬ妊娠を防ぐ」「性感染症を防ぐ」「思春期の身体の変化を教える」といった健康面に焦点が当てられがちでした。しかし包括的性教育は、「知識や技術の習得」だけでなく、子どもたちが自分や他者を尊重し、健康的で充実した人間関係を築く力を養うことを目指しています。
さらに包括的性教育では、年齢に応じて段階的に教えることが重視されています。「何歳で何を学ぶ」といったことではなく、後述する8つのキーコンセプトを4つの発達年齢段階に応じて、繰り返し積み重ねて学びます。子どもが混乱しないよう徐々に内容を深めていくイメージです。
8つのキーコンセプトについて

UNESCOの『国際セクシュアリティ教育ガイダンス』などでは、包括的性教育を構成する内容として以下の「8つのキーコンセプト」が示されています。これは年齢に応じた学習テーマを整理したもので、各キーコンセプトが相互に関連し合い、総合的に子どもたちの知識や態度、スキルを育むとされています。
| キーコンセプト | 目的 |
| ①人間関係(Relationships) | 友人関係や家族関係、恋愛関係などを通じて、互いを尊重し支え合う方法を学ぶ |
| ②価値観、権利、文化、セクシュアリティ(Values, Rights, Culture, and Sexuality) | 個人が持つ価値観や人権、文化的背景、多様な性に対する理解を深める |
| ③ジェンダー(Understanding Gender) | 社会的に形成される男女の役割や固定観念を問い直し、ジェンダー平等を考える |
| ④暴力と安全確保(Violence and Staying Safe) | いじめや虐待、性的暴力などに対する予防や対処方法を学び、自分や他者を守る術を身につける |
| ⑤健康と幸福のためのスキル(Skills for Health and Well-being) | コミュニケーション能力や意思決定スキル、ストレスマネジメントなど、人生全般に役立つスキルを養う |
| ⑥人間の身体と発達(The Human Body and Development) | 身体の構造や機能、思春期の変化など、生物学的な面を正確に学ぶ |
| ⑦セクシュアリティと性的行動(Sexuality and Sexual Behaviour) | 性的欲求や行為、性的指向について正確に理解し、健康で責任ある選択を考える |
| ⑧性と生殖に関する健康(Sexual and Reproductive Health) | 避妊法、性感染症の予防、妊娠・出産に関する知識など、リプロダクティブ・ヘルスとライツを含む |
①人間関係(Relationships)
友人関係や家族関係、恋愛関係などを通じて、互いを尊重し支え合う方法を学ぶ

具体的には「健全なコミュニケーションのとり方」「お互いの意思や気持ちを尊重する関係づくり」「相手が望まないことを強要しないための態度」などを学ぶことが含まれます。子どもたちは幼い頃から親や保育者、学校の先生や同級生などとの関係の中で成長していきますが、このプロセスで培われる「相手を大切にし、自分も大切にされる」感覚こそが、将来的に自分の性や体を守り、他者の尊厳を尊重する基盤となります。
さらに、思春期になると恋愛感情や性的欲求といった側面が加わり、より複雑な人間関係が生まれます。その際に「相手がどう感じているのか」を想像する力や、「自分はどう感じているのか」を整理する力が育っていると、トラブルや誤解を最小限に抑えることができます。
人間関係において大切なのは「自分のことをしっかり理解し、同時に相手も尊重する」ことであり、これを年齢に応じて学んでいくのが包括的性教育の狙いのひとつです。
②価値観、権利、文化、セクシュアリティ(Values, Rights, Culture, and Sexuality)
個人が持つ価値観や人権、文化的背景、多様な性に対する理解を深める

性にまつわる価値観や文化は、社会や時代によって大きく異なります。また、人それぞれが持つ性に関する価値観も多様です。このキーコンセプトでは、そうした多様性を認め合い、互いの権利を尊重する姿勢を育むことを目的としています。
たとえば、「性行為は結婚してからすべきだ」という価値観を持つ人がいる一方で、パートナーとの合意があれば結婚前でも構わないと考える人もいます。また、性的指向や性自認の違いによっても、望むパートナーシップや生き方は異なるでしょう。
こうした多様な価値観を「自分とは違うから間違いだ」と断じるのではなく、「そういう考え方や文化があるのだ」と理解する力が大切になります。さらに、性に関する権利として「自分の体や生き方をどう選択するか」が本来的に尊重されるべきだということを学ぶのもこの領域です
③ジェンダー(Understanding Gender)
社会的に形成される男女の役割や固定観念を問い直し、ジェンダー平等を考える

「男女はこうあるべき」「男の子は泣いてはいけない」「女の子だから優しくしないといけない」といった固定的な性役割意識は、無自覚のうちに子どもたちを苦しめることがあります。ジェンダーのキーコンセプトでは、性差にまつわる社会的・文化的な枠組みを客観的に見つめ直し、「本来はもっと自由に個性を発揮していいのだ」ということを学びます。
たとえば、男の子がピンク色を好きだったり、女の子が理系の分野に興味を持ったりするのは何らおかしなことではありません。しかし現実には周囲の偏見や社会的ステレオタイプによって、子どもたちが自分の興味を素直に表現できないケースも少なくありません。
ジェンダーについて正しい理解を深めることで、自分らしさを抑圧せず、他者の「らしさ」も受け入れる姿勢が育つのです。これは将来の職業選択や人間関係の選択にも大きく影響を与えるため、子どもの段階から学ぶ意味は非常に大きいといえます。
④暴力と安全確保(Violence and Staying Safe)
いじめや虐待、性的暴力などに対する予防や対処方法を学び、自分や他者を守る術を身につける

性暴力や虐待は、子どもの人権を大きく侵害する深刻な問題です。このキーコンセプトでは、暴力とは何か、どんな行為が暴力やハラスメントに当たるのかを知り、自分自身が被害者にも加害者にもならないためにどうすべきかを学びます。
具体的には、「嫌だと思ったらはっきり『嫌だ』と言っていい」「自分の体を誰にどのように触られても良いかは自分で決めて良い」「誰かから性的ないたずらをされたら信頼できる大人に相談する」など、子どもにとっては非常にリアルで身近なテーマが含まれます。また、ネット上での性的ないじめや児童ポルノ被害を防ぐためにどう行動するかといったトピックも重要です。
性にまつわる暴力は表面化しづらく、子どもが声を上げにくい分野だからこそ、包括的性教育ではこうした問題を「誰にでも起こりうること」として取り上げ、具体的な対処法を身につける機会を提供するのです。
⑤健康と幸福のためのスキル(Skills for Health and Well-being)
コミュニケーション能力や意思決定スキル、ストレスマネジメントなど、人生全般に役立つスキルを養う

思春期を迎える子どもたちは、身体の変化に伴い、感情面でも大きな揺れを経験します。また、人間関係のトラブルや勉強面でのプレッシャーなど、ストレスの要素が増えていくのもこの時期です。このキーコンセプトでは、そうしたストレスや不安に対処する方法、誰かに助けを求める術、周囲との上手なコミュニケーションなどを学びます。
たとえば、思春期に入るとホルモンバランスの変化もあって、情緒が不安定になったり孤立感を抱えたりしやすいとされます。そんなときに「自分の感情を言葉で表現する方法」を身につけていれば、家族や友人に助けを求めることができるでしょう。思春期に限らず人生のさまざまな局面で必要となる「自己理解」や「コミュニケーション・スキル」は、生きていくうえでの基礎体力となります。
性教育という枠を超えて、心身の健康や幸福感に直結するテーマを含む点が、包括的性教育の特徴のひとつです。
⑥人間の身体と発達(The Human Body and Development)
身体の構造や機能、思春期の変化など、生物学的な面を正確に学ぶ

従来の性教育で扱われることが多いこの領域では、男女の体の構造や思春期の身体的変化、妊娠・出産の仕組みなど、生物学的な面に重きが置かれます。子どもたちが正しい知識を得ることは、自分の体をどのようにケアし、将来どのような選択をしていくかを考えるベースとなるため、とても重要です。
ただし、「体の発達」や「月経」「射精」といった話題は、特に日本ではまだ恥ずかしいもの、触れづらいものとされがちです。しかしこうした身体の機能や変化を理解しないままだと、月経や性欲に対するネガティブな感情や誤解が生まれたり、「自分は他の人と違うのではないか」という不安に苦しむ子どもが出てきます。
包括的性教育は、「自分の体を知ることは自然で大切なこと」というメッセージを伝え、体を正しく理解することで自己肯定感を高めることをねらいとしています。
⑦セクシュアリティと性的行動(Sexuality and Sexual Behaviour)
性的欲求や行為、性的指向について正確に理解し、健康で責任ある選択を考える
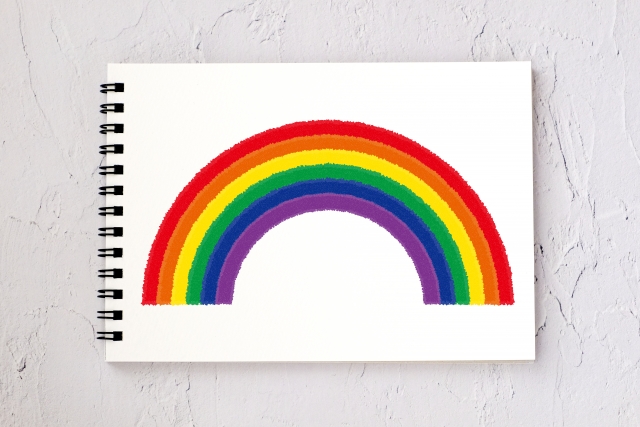
思春期以降の子どもたちは、性欲や恋愛感情をもち始めることで自分の内面に戸惑いを感じたり、ときには衝動的な行動に走ったりすることがあります。その際に「もし妊娠してしまったらどうするか」「性感染症を防ぐにはどうすればいいか」「パートナーが望まない性行為は絶対にしてはいけない」など、具体的な知識やルールを知らなければ取り返しのつかない事態に至る恐れも否定できません。
また、性的指向がヘテロセクシュアル(異性愛)のみならず、同性愛や両性愛など多様に存在すること、自分の性自認について正しく把握することは、その人のアイデンティティ形成にとって非常に大切です。
包括的性教育では、性に関して「何が普通で何が異常」という二元論ではなく、「多様性を前提に、相手や自分を傷つけない選択をする」ことを重視します。そのため、生理学的・心理学的アプローチだけでなく、倫理的・社会的な観点を含めた幅広い学びが必要となるのです。
⑧性と生殖に関する健康(Sexual and Reproductive Health)
避妊法、性感染症の予防、妊娠・出産に関する知識など、リプロダクティブ・ヘルスとライツを含む

たとえばコンドームの正しい使い方やピルなどの避妊法について知らないまま性交渉に及べば、妊娠のリスクだけでなく性感染症のリスクも高まります。また、妊娠や出産に関しては、どのようなタイミングで子どもを産むかを本人が主体的に決められるよう、パートナーや社会がサポートする必要があるというリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の考え方も重要です。
性と生殖に関する健康の学びは、単に「トラブルを避ける」ためだけではなく、自分の人生を自分でコントロールする意識を育むことにもつながります。妊娠・出産に関する理解を深めることは、子どもたちが将来、パートナーや家族とどのようなライフプランを築きたいかを考えるきっかけにもなるでしょう。相手に対しても、こうした情報を共通の基盤として共有し合うことで、対等な関係を結びやすくなります。
包括的性教育のポイントと重要性

「性の知識」以上の広範な内容
従来の性教育というと、「保健体育の授業で生殖機能を習う」「保健室の先生から初潮や射精について説明を受ける」といった限定的なイメージを持つ人も多いでしょう。しかし包括的性教育は「生物学的な知識を伝える」にとどまりません。上で紹介した8つのキーコンセプトが示すように、人間関係、コミュニケーション、ジェンダー、そして性にまつわる権利や責任など、多方面から性を学ぶことが重要視されます。
たとえば、思春期の子どもに対して性交や避妊の知識を与えることは大切ですが、それだけでは不十分かもしれません。身体の変化にともなう不安や、友人関係・恋愛関係における悩み、SNSやネット上の性的コンテンツへのアクセスリスクなど、子どもを取り巻く問題は多岐にわたっています。
包括的性教育は、それらの課題を包括的に扱うことで、子どもが自分自身や他者を尊重し、安全で健康的な関係を築ける力を育もうとするのです。
子どもの心身の健やかな成長を支える

性に関する正しい知識を得ることは、子どもの心身の健康に直結します。誤った情報や偏見を持ったまま思春期を迎えたり、性的暴力などのリスクを知らずに行動したりすれば、予期せぬ妊娠や性感染症、トラウマなどにつながる危険性が高まります。
また、思春期の体の変化に戸惑いを覚えたり、「自分だけがおかしいのでは?」と不安になったりする子どもは少なくありません。
包括的性教育によって、身体の仕組みや変化をポジティブに理解し、自分や他者のプライバシーや尊厳を守る方法を学ぶことは、子どもの自己肯定感を育む上で大きな意味を持ちます。
ジェンダー観や多様性理解の促進

ジェンダー観や性的指向、性自認、ライフスタイルは人によってさまざまです。たとえばLGBTQ+(性的マイノリティ)の子どもや、身体的特徴が典型的な男女どちらにも当てはまらない子どもなど、多様な性を持つ子どもたちは、伝統的な性教育では十分にサポートされてきませんでした。こうした子どもたちが自分の性的アイデンティティを理解し、孤立しないためにも、多様性を前提とした学習環境が必要です。
包括的性教育は、性を男性/女性の二元論だけでとらえるのではなく、「人間の性は多様である」という視点を基本に据えています。このアプローチは、すべての子どもが自分のアイデンティティを肯定できる社会をつくるための土台となります。ジェンダーや多様な性に対する理解が育まれると、差別や偏見のないクラスメイト同士の関係性や社会環境を形成しやすくなるでしょう。
日本の学校における性教育の現状

学習指導要領と「はどめ規定」について
日本では、文部科学省が定める学習指導要領に沿って学校教育が行われています。保健体育の授業では「男女の身体のしくみ」「思春期の保健」「性感染症やHIV、エイズについて」といった内容が取り扱われますが、一部の深いテーマやタイミングについては「はどめ規定」と呼ばれる指導上の制限が存在し、慎重に扱われるべきとされています。この「はどめ規定」は、「小学校・中学校では集団指導で性交を取り扱わない」とするもので、実質的に学校現場での性教育が制限される一因になっているという指摘もあります。
たとえば、中学校の段階では「性交渉」や「避妊」に踏み込む授業はほとんどの学校で実施されておらず、高校で初めて学びます。また、ジェンダーや性的マイノリティ、性的同意(性的同意年齢・性的行為における合意)などに関しては、学習指導要領の範囲外とみなされ、ほとんど触れられないまま卒業する生徒が少なくありません。
学校現場で見られる課題

先述のように、日本の性教育は「はどめ規定」の存在もあり、十分に深いところまで踏み込めていないケースが多いと言われています。また学校や地域、教育委員会の方針によって取り扱いの程度にばらつきがあり、熱心に取り組んでいる学校がある一方で、保護者や地域社会からの反発を恐れて消極的になってしまう学校もあります。
さらに、子どもが授業中に抱いた疑問や不安を気軽に相談できるような体制が整っていないことも問題の一つです。性に関する質問を受けることに慣れていない教師や、性教育に積極的ではない学校環境では、子どもたちは「こんなことを聞いたら変に思われるかもしれない」と口をつぐんでしまい、本当に必要としている情報が得られないことがあります。
国際基準との比較

UNESCOなどは、先に述べたとおり包括的性教育を世界のスタンダードとして推奨しています。しかし、日本で行われている性教育は国際基準と比べると大きな差があります。たとえば海外の一部の国や地域では、小学校低学年からすでに「自分や他者の体を尊重する」「プライベートゾーンとは何か」「相手が嫌がる行為をしてはいけない」といった内容を扱います。一方日本では「生命(いのち)の安全教育」として2023年から全国で取り組みが始まっているものの、地域差があるのが現状です。
「それを教えると性的に奔放になる」「早い段階から余計なことを教えるべきではない」といった偏見や不安が根強く、体系的・段階的な性教育の実践が難しい状況にあります。その結果、子どもが興味本位でインターネットなどから断片的・過激な情報を得てしまい、間違った知識を身につけるリスクが高まっているという指摘もあるのです。
日本における包括的性教育へのアプローチ
実践例や先進的な取り組み

一部の自治体や学校、NPOや市民団体などは、日本であっても国際的なガイドラインに則った包括的性教育を取り入れる実践を進めています。
たとえば、東京や大阪などの都市部では、学校保健委員会やPTAと連携し、外部の専門家を招いて多様な性やジェンダーに関する講演を行ったり、LGBTQ+に配慮したカリキュラムを独自に整備したりしているケースがあります。また、民間団体による出張授業やオンライン学習教材の提供も増えており、従来の学習指導要領の枠を超えた多角的なアプローチが少しずつ注目されています。
そうした取り組みでは、子どもたちが自分の意見を自由に表現できる場や、実際に自分たちで調べたり議論したりするアクティブラーニングの要素を取り入れることが多いです。たとえば、性犯罪防止やSNS上の性被害に関するワークショップを通じて、自分や友達を守る方法をリアルに考えさせる授業なども行われています。
教材や情報源の紹介
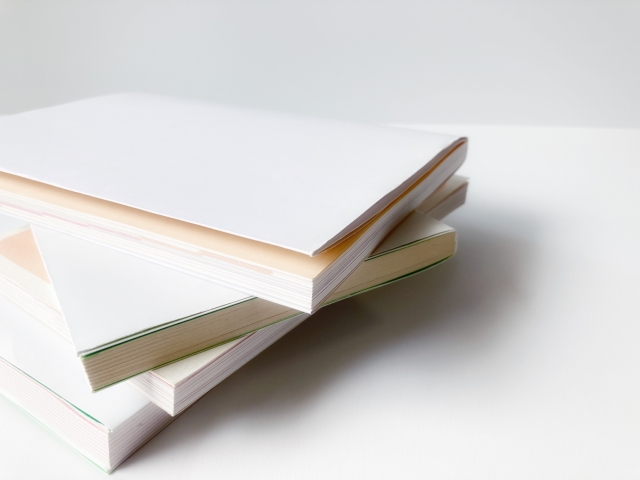
近年では、日本語でも包括的性教育をサポートするための教材や書籍、ウェブサイト、動画などが徐々に充実し始めています。たとえば、
- NPO法人や市民団体が作成した、年齢別に適切な性教育の内容をまとめた冊子
- オンライン上で閲覧できる「思春期向け性教育」カリキュラムや動画 まるっと!まなブック(女性の健康教育プログラム)※厚生労働省科学研究班(荒田班)監修
- 保護者や教師向けの解説書や研修プログラム 命育(家庭でできる性教育サイト)
- LGBTQ+やジェンダー問題をわかりやすく解説するマンガやイラスト
- 子どもが匿名で相談できる電話・チャット窓口
など、探せば多種多様なツールが見つかる時代になってきています。学校で取り上げることが難しいテーマでも、こうした外部リソースを活用すれば、保護者としても子どもに適切な情報を伝えたり、一緒に学んだりしやすくなるでしょう。
家庭で補う性教育:足りない部分をどう伝えるか

年齢に応じた伝え方の工夫

日本の学校での性教育が十分ではないと感じる保護者も多いかもしれません。その場合、家庭での会話やちょっとしたきっかけを活かして、子どもの疑問に応えていく姿勢が重要です。ただし、一度に「すべてを教えよう」と焦る必要はありません。子どもの成長段階や興味関心に合わせ、段階的に話をしていくほうが理解も進みやすいものです。
幼児期・小学校低学年であれば、「自分の体を守る」「プライベートゾーンを大切にする」「男女の体の名称」を正しく知るくらいからスタートしてもよいでしょう。小学校中学年から高学年にかけては、思春期に向けた身体の変化や生理・射精の仕組み、気持ちの変化などを中心に話し、さらに中学・高校生になると、避妊や性感染症の予防、性的同意の重要性、ジェンダーの多様性、恋愛やコミュニケーション能力など、一歩踏み込んだ内容を伝えていくイメージです。
子どもとのコミュニケーションのポイント

性教育は「保護者から子どもに一方的に押し付ける」ものではなく、対話の中で疑問や意見を自由に言いやすい環境をつくることが望ましいです。以下のようなコミュニケーションのポイントを意識するとよいでしょう。
①子どもが何か疑問を口にしたら、まず否定せずに聞く

「そんなこと考えるなんて早い」と決めつけると、子どもはもう話してくれなくなるかもしれません。
②自分の体験や価値観を押し付けすぎない
性に関する考え方は人それぞれです。自分の体験談を話すのはいいことですが、「こうしなきゃダメ」という押し付けは避けましょう。
③常に「あなたのことを尊重している」という姿勢を見せる。

何か失敗をしてしまったときや、予想外の相談をされたときも、怒るよりまず話を聞き、「よく相談してくれたね」という声かけが信頼関係を築きます。
多様性への理解を深めるために

先ほど述べたように、包括的性教育は多様な性のあり方を前提とした教育でもあります。子どもがLGBTQ+やジェンダーの問題に関心を持ち始めたり、自分自身がその当事者として悩みを持ち始めたりするケースもあるでしょう。その際、保護者が否定的な態度を示したり、「そんなの一時的なものだ」「普通じゃない」と決めつけたりすると、子どもは深刻に傷つき、孤立してしまうかもしれません。
多様性を理解するためには、保護者自身も正確な知識を得ることが大切です。LGBTQ+に関する書籍を読んだり、信頼できる団体や専門家の情報を参照したりして、自分の中にある思い込みや偏見に気づくことが第一歩となります。子どものアイデンティティや尊厳を尊重し、「どんな選択をしてもあなたは大切な存在だ」というメッセージを日頃から伝えるよう心がけましょう。
保護者が知っておきたいQ&A

ここでは、保護者が子どもの性教育や日常的な性の話題について、よく抱きがちな疑問や不安に対するヒントをまとめます。
Q:子どもに「性」について聞かれたらどうする?
A:まずは「どうしてそれを知りたいと思ったの?」と子どもに聞き返してみましょう。子どもが知りたいと思ったきっかけによって答え方が変わってきますし、急に性について聞かれてびっくりした自分を落ち着けるのにも役立つフレーズです。また「聞いてくれて嬉しいよ」と肯定的に受け止めましょう。
そして質問の内容が意外に感じても、「そういうことに興味を持つのは自然だよ」と声をかけてあげることで、子どもは安心して質問を続けられるようになります。もしすぐに答えが見つからなかったり、正確に説明できる自信がなかったりするなら、「一緒に調べてみようか」と言って、書籍やインターネットで情報を探すプロセスを共有するのも良い方法です。
Q:性教育を早くから教えると、子どもの性行動が早まるのでは?
A:国際的な研究では、包括的性教育を受けた子どもほど、逆に性行動の開始が遅くなったり、慎重な行動をとる傾向があるという結果が多く示されています。「教えないで隠す」ことはリスクを高める可能性が高いと考えられます。
Q:LGBTQ+に関する話題はいつ・どうやって伝えればいい?
A:特別扱いする必要はなく、小さい頃から「いろんな家族の形や好きになる相手があるんだよ」と自然に伝え、絵本やテレビ番組などで多様性を示す機会をつくるのがおすすめです。
Q:子どもがネットで性的な情報を見ているようだが、どう向き合えばいい?
A:禁止や制限をかけるだけでは、子どもの好奇心をむしろ刺激することもあります。危険や誤った情報を見た時に「これは正しい情報か?」と立ち止まれる判断力を育てることが大事です。フィルタリングは一つの手段ですが、それだけに依存するのではなく、日頃からオープンに話し合える環境づくりが重要といえます。
なお、子どもがネットで性的な情報を見ていることに保護者が気付いた時は性教育のチャンスと言えます。「AVなどはゆがんだ情報かもしれない」ということをこの機会に話し合えるといいでしょう。
Q:親が迷った時、どこに相談すればいい?
A:保護者自身が「子どもへの性教育でどこまで踏み込んでいいかわからない」「LGBTQ+の話題をどう扱うべきかわからない」といった迷いを抱えることは珍しくありません。そんなときは、学校の養護教諭(保健の先生)や信頼できる医療機関、NPO団体などに相談してみましょう。
今はオンラインで相談を受け付けている団体も多いです。また、性教育や子育てに特化した書籍・Webメディアも充実してきています。客観的で科学的な情報を提供しているところを選び、参考にすると安心です。
包括的性教育は子どもを“守る”ための大切な知識

包括的性教育は、単に性行為や妊娠・出産の基礎知識を教えるものではなく、ジェンダー平等や多様性、人間関係の築き方、心身の健康などを多面的に学ぶ総合教育でもあります。子どもたちは自分の体と心、そして他者の体と心を尊重する術を身につけることで、より安心できる環境で成長し、将来的に自分らしい人生の選択をしやすくなります。
日本の学校教育では未だ十分に深いアプローチが難しい現状が続いているため、保護者が知識を得て子どもを支える役割が大きいことは否めません。「性」は本来、誰もが関係するテーマであり、知らないで困ることがあっても、知っていて困ることはほとんどありません。とりわけ、性暴力や望まない妊娠、性感染症などを回避するためには、正確な知識と意識が欠かせないのです。とはいえ保護者の世代も学んできていないため、子どもとともに(もしくは子どもより先に)学ぶと良いでしょう。
また、思春期以降の子どもは、自分でもまだよくわからない感情や欲求に直面しがちです。そのとき、安心して相談できる大人がそばにいることは何よりの支えになります。保護者の側も、最初は戸惑いや恥ずかしさを感じるかもしれませんが、「子どもに一番近い存在として適切な導きをしてあげられるのは自分かもしれない」という意識を持ってみてください。
性教育は一度きりで終わるものではなく、成長段階にあわせて必要な知識をアップデートしていくものです。親子で一緒に学び合い、互いを尊重するコミュニケーションを築けたら理想的でしょう。また「親にだけは言えない」という時のために、性について子どもが相談できる環境も必要です。たとえば、若い世代が性や体、心の悩みなどについて医師や看護師などに相談できる「ユースクリニック」が全国にありますが、まだまだ認知度は低いのが現状です。
性は人間の根幹にかかわる重大なテーマであり、自分らしく生きるための土台でもあります。保護者がその尊さや危うさを理解し、適切な時期に適切なかたちで導くことができれば、子どもの未来はより明るいものになるでしょう。ぜひ本記事を参考にしつつ、親子で納得できるやり方を模索し、「知らないまま放置しない」性教育を目指してみてください。
【参考文献・URL】
「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」活用ガイド――包括的性教育を教育・福祉・医療・保健の現場で実践するために(浅井 春夫・谷村 久美子・村末 勇介 ・渡邉 安衣子 (編集,・著) 明石書店
国際セクシュアリティ教育ガイダンス――教育・福祉・医療・保健現場で活かすために(ユネスコ (編集) 明石書店
https://www.unesco.org/en/articles/international-technical-guidance-sexuality-education
https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-researc
https://www.who.int/health-topics/sexual-health
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!