家庭でできる子どもの性教育|小学生への伝え方と年齢別ポイントとは?

子どもが成長していく中で、いつ、どのように「性」に関する話をしたらいいのか、悩む保護者は少なくありません。実際に相談でも多い内容の一つです。
日本は特にネットやメディアなど、子どもが様々な情報に触れやすい社会なので、正確で年齢相応な性教育が必要に感じます。
そこで今回は、「子どもの性教育」をテーマに、性教育の重要性、スタート時期、具体的な伝え方や日常での取り入れ方、よくある質問への対応などを解説していきます。
性教育は日常生活の中から積み上げていくものです。日々の暮らしの中で子どもをどのように導けるかこの記事を通じて、保護者が性教育を前向きに進めるためのヒントにしていただければ幸いです。
目次
そもそも性教育って何?
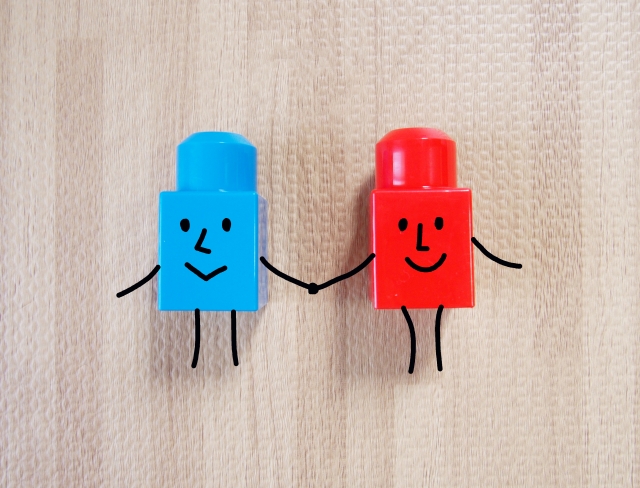
性教育とは「権利教育」です。自分自身と他者の身体や心を尊重し、多様な人間関係を築き、社会の中で健全に生きていくための総合的な教育です。「包括的性教育」という言葉が最近よく目にされる方も多いのではないでしょうか。
性教育は「単なる生殖知識の伝達」ではなく、性にまつわるすべての側面――身体の仕組み、思春期の変化、コミュニケーション能力、ジェンダーや性的指向の多様性、人権意識、相互尊重――を年齢に応じて段階的かつ包括的に学ぶ必要があるからです。
日常生活の中で子どもの権利や基本的な生活習慣の情報を土台に子どもの理解度や発達度合いに合わせて積み上げていくからです。
文科省が推進している「命の安全教育」では幼児期、小学校低学年には自分の身体を知るところから始まり、プライベートゾーンの知識や見られたり触られたりしそうな場合には拒否することを教えることから始めています。
高学年になると第二次性徴、つまり思春期の身体に起こる変化についてやSNSの危険性など「性暴力」についても学びます。更に中高生になるとパートナーシップや生殖についての責任や避妊についての情報も必要になります。
このように性教育は発達段階に応じて積み上げていく必要がある教育です。そして「権利教育」と申し上げたように人が生涯にわたり必要な情報になるのです。
覚えておいていただきたいのは性を思春期の一時の「恥ずかしいもの」や「危険なもの」と捉えるのではなく、「生きていく上でずっと終わらないもの」として理解していただきたい、ということです。
また、子どもの「性教育」というと、学校の保健体育で教えるイメージが強いかもしれませんが、実は家庭でのコミュニケーションが、パートナーを尊重することであることや自分を大切にすることとはどういうことかということを、理解させるための重要な役割であることを忘れないでいただきたいと思います。
性教育が大事な理由とは?
最近、家庭での性教育が話題になっているのか?その背景には、子どもにとっての環境や情報アクセスの急激な変化があります。
自己肯定感と尊厳の育成
子どもが自分の体を知り、自分を大切に思うことは自己肯定感の基礎になります。「自分の身体や心は尊重される権利がある」と理解することで、子どもは自分を守り、堂々と生きる力を身につけます。
誤った情報への対処力向上

ネット上には、大人向けの情報や誤った知識が氾濫しています。子どもが何のガイドラインも持たずにそうした情報に触れると、誤学習を招きやすくなります。家庭で正しい基礎知識を得ていれば、将来、有害な情報に直面しても大人に助けを求めることが出来ます。
多様性の理解と相互尊重

性教育は、男女間の違いだけでなく、自分の性的指向やアイデンティティなどの多様性を理解する機会でもあります。多様なあり方を知ることは、子どもは偏見を持ちにくくなり、相手を尊重し合える柔軟な人間関係を築きやすくなります。
トラブル防止と身を守る力
不適切な接触や性犯罪被害を防ぐためには、子ども自身が「自分の身体は自分の権利」と言うことを主張できる存在であり、自分の体の健康を保つ目的の場合以外は自分の許可なく他人は自分の身体に勝手に触れてはいけないという境界意識を持つことが重要です。拒否できる権利を教えることは、性教育の重要な側面です。
継続的なコミュニケーション環境の醸成
幼児期から性に関して、大人が正直で誠実な対応ができれば、子どもは思春期や青年期になっても性や人間関係について悩みやすい時期に安心して保護者に相談できます。これが長期的な家族内コミュニケーションの信頼関係を強める基盤になります。
性教育は何歳からはじめるのがいいのか

性教育は、子どもが自分の身体に興味を持ち始めたり、疑問や質問など達段階に合わせて自然に進めることが理想です。
幼児期(3~5歳)
まずは子どもが疑問に思っている事、知りたい事に応えることです。例えば男の子・女の子で体のつくりが違うことなどシンプルな説明から始めます。また、「プライベートゾーン」の概念を軽く示すことで、自分の体は大切で守られるべきものだと伝えられます。「赤ちゃんはどうやって生まれるの?」といった興味が出やすい時期です。
小学校低学年(6~8歳)
自分の身体の権利を教えます。拒否の仕方、大人への伝え方などです。この時期は家族形態についても疑問がわく年齢です。ステップファミリーやシングルペアレンツの家庭など、子どもの理解度に合わせて説明が必要になります。ここで性についても科学的な正しい言葉遣いや表現を心がけておくと、子どもは性を自然なものとして受け入れやすくなります。
小学校高学年(9~12歳)
第二次性徴が近づき、思春期の入り口に立つ頃です。身体や心の変化が起こる前に、その変化が当たり前であること、月経や精通、体毛の増加、変声期などが成長の証であると前向きに伝えておけば、子どもは不安を軽減できます。また、ネットで嘘の情報を拾わないためにも検索方法などを一緒に教えておくことです。
この記事を執筆した藤原美保さんに相談してみませんか?
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で藤原美保さんに子育ての悩みを相談できます。
藤原美保さんへの相談ページを見てみる
子どもへの性教育で抑えるべきポイントとは?

性教育を家庭で実践する際には、以下の点を意識するとスムーズです。
プライベートゾーンの重要性
下着で隠れる部分は「自分だけの大切な領域」であると伝えましょう。他人に勝手に触らせない、見せないこと、自分も他者に同じことをしないことを子どもの言葉で示します。早期からこの感覚を身につけることで、子どもは将来、不適切な接触に遭遇した際に「これはいけないことだ」と理解しやすくなります。
科学的な正しい名称を使い、タブー視しない
性器や生殖に関する言葉を正しく用い、ふざけたり隠語を使ったりしないことで、子どもは身体についての知識を健全に受け止められます。「恥ずかしい話」という雰囲気が漂うと、子どもは質問しづらくなってしまうため、あくまで冷静に対応しましょう。
日常の中で自然に取り入れる
特別な時間を設けず、子どもの質問や好奇心が発生したときがチャンスです。妊娠中の知人を話題にしたり、動物番組で生まれたばかりの赤ちゃん動物を見たら、「人も同じようにお母さんのおなかの中で育つんだよ」とさらりと伝えるといった、日常生活に溶け込む形が理想的です。
子どもの理解度や表情を見ながら進める
子どもが戸惑っていたり、十分理解できていない様子なら、踏み込みすぎない事です。「難しい言葉が出てくるね、あなたがもう少し成長して解るようになったらもう一度話そう」と説明を止めても大丈夫です。
保護者自身がリハーサル、シナリオを考えておく
保護者も初めての場合ぎこちなくなるのは当然です。しかし、その時は必ず来ます。子どもは成長するからです。性教育を恥ずかしがったり、過剰に緊張したりすると、その空気は子どもにも伝わります。聞かれてもいいようにリハーサルをしておきましょう。夫婦で話し合っておくことがおすすめです。大切なのは、子どもが「安心して質問できる」と思える関係性を作ることです。
【関連記事はこちら】子どもに性教育を「していない」62%。23%の「している」人に、家庭でどんなことをしているのかを聞いた
「性的同意年齢13歳」の日本で、家庭でできる“男の子”の性教育とは?
こんなときはどうすればいい?性教育あるあるQ&A

「赤ちゃんはどこから来るの?」
まずはなぜ疑問に思ったかを聞いてみましょう「赤ちゃんがどこからくるのか知りたいのね?なぜ疑問に思ったの?」と訊ねてみましょう。
というのも以前、妊婦さんを見て、もし自分にも赤ちゃんが出来たらどうしようと不安になった子がいたのです。幼い子の場合、子どものつくり方を説明する必要はありません。
私はお子さんに「細胞って言葉知ってるかな?人間の体は沢山の細胞で出来ているんだよ。女の人の体には卵巣っていう内臓があってね、大人の身体になるとその中に赤ちゃんの元になる細胞が出来るの」と話すと子どもは解らないといった表情をします。「たくさん知らない言葉が出てくるね。難しいね、だから子どもの身体には赤ちゃんが出来ないの。あなたがもう少し成長したら解るようになる。その時にもう一度詳しく説明しようね」と話すと子どもはそれで納得します。
「おちんちん・おしり」を連呼して笑う場合
多くの場合、周囲の子が笑ったり、反応したりすることから「面白いこと」と誤解し繰り返していることがほとんどです。これはいわゆる注目行動です。
もし、場面が適切でない場合はまず、「それ面白いと思っている?」と聞き、「私は面白くないと思う。不快だと思うから止めて欲しい」と伝えましょう。この場合、あくまで冷静にフラットに対応してください。感情的になると誤学習を積み上げてしまいます。
友達から変な性情報を聞いてきたとき
「○○ちゃんが、赤ちゃんは妖精が運んでくるって言ってた!」などの誤情報に対しては、「なるほど、絵本の中にはそういう物語があるのかもしれないね。あなたはどう思う?」聞いてみましょう。
「わかんない」と答えた場合「そうなのね、質問(疑問におもったら)したくなったらママに聞いてね」と伝えましょう。子どもに「本当は、赤ちゃんはママのおなかから生まれてくるの」と言おうものなら子どもは相手の子に「妖精が運んでくるんじゃないよママのおなかから生まれてくるんだよ」と言いに行き、相手の子との関係性が悪くなってしまうかもしれません。余計な情報は必要ありません。しかし、子どもの疑問には誠実に対応しましょう。
性器をいじっていたら
子どもの「性器いじり」は不思議な事ではありません。特に男の子が幼い時期にはよくみられる行動です。「これなんだろう?」手にあたる柔らかいものを触っている感じです。しかし親として見ている方はいい気がしないでしょう。この時期に教えるのはパブリックとプライベートの違いと衛生管理です。
パブリックとプライベートの区別を教える
もう一つこの時期に子どもに伝えたいことは、プライベートとパブリックの区別です。
プライベートなトイレなどは性器を触ることは問題ありませんが、家の中だとしてもパブリックスペース、他の人がいる場所、他人から見える場所はパブリックです。性器を触ってもいいのはプライベートなスペースだけでと教えましょう。
清潔な手で触る
手が汚れていると性器が炎症を起こす場合があります。性器に触れる時はしっかり手を洗い清潔な手で触れることを教えましょう。
私が対応した中では感覚欲求を満たしてあげることで性器を触らなくなったケースがいくつかあります。
・一日の中でしっかり身体を動かす遊びを取り入れる
・子どもが好きな感触の物を持たせる
ぬいぐるみやタオルでもなんでも良いのですが、以前アドバイスした保護者が作ったのはふわふわ生地でキーホルダーを手作りしていました。子どもが握りやすいようなものを工夫してあげることがおすすめです。
子どもに性教育をするにあたり、参考にしたい情報源とは

家庭での性教育を行う場合、信頼できる情報源やツールが役立ちます。
公的機関・国際機関・NPO法人のガイドライン
厚生労働省や文部科学省、WHO、ユニセフなどは、子どもの発達段階に合わせた性教育ガイドラインを公表しています。また、性教育関連のNPO法人は、わかりやすい資料やQ&A、保護者向けのアドバイスを提供していることも多く、こうした公式情報は信頼性が高くwebでも見られるため参考にすると良いでしょう。
子ども向けの絵本や児童書
「子供 性 教育」向けに作られた絵本や図鑑、児童書は数多く出版されています。子どもと一緒に読むことで、自然と会話が生まれ、疑問をキャッチしやすくなります。図書館や書店で子どもに合いそうな本を探し、読み聞かせを通じて必要な知識を補っていきましょう。
専門家による講演やオンライン相談
教育専門家や性教育アドバイザーなどが行う講演やセミナーに参加することは、最新の情報や実践的なコツを得る良い機会です。オンラインの相談も手軽にできておすすめです。実際に質問もできるため、家庭でどう伝えるか迷った場合、プロのアドバイスを得られます。ソクたま相談室でも性教育のプロが登録しており、幼い子にどう伝えていいか分からないといった相談にも対応しています。
この記事を執筆した藤原美保さんに相談してみませんか?
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で藤原美保さんに子育ての悩みを相談できます。
藤原美保さんへの相談ページを見てみる
地域の子育て支援センター・保健センター
地域には、子育て中の保護者が集う場所があり、そこで情報交換をしたり専門スタッフに相談したりできます。他の保護者がどのように性教育を進めているのか、何に困っているのかを知ることで、自分なりの方法を見つけやすくなります。
保護者自身の学びなおしと心構え

日本では保護者自身が、性教育を受けてない場合がほとんどで、しかも性を恥ずかしい・隠したいと感じる文化の中で育ってきたりすると、子どもに教える際に難しさや抵抗を感じることは珍しくありません。
そのような場合、まずは信頼できる書籍やウェブサイトで情報を学び直し、自分自身が「性は隠すべきものではなく、自然なこと」と受け入れる努力をしてみてください。ウェブサイトで検索する際は「〇〇 医学」と「医学」のキーワードを入れて検索すると変なアダルトサイトに結びつく可能性が低くなり、しっかりとした科学的な説明のあるサイトに繋がるのでおススメです。
パートナーとも子どもにどのように性を伝えるか情報を共有することがおすすめです。性の内容は同性から伝えることが必要だからです。男の子のお子さんの場合は男性の保護者から伝えることが推奨されます。
また、子どもに完璧な説明をする必要はありません。特に「性」についての個人的価値観については個人差が大きく「正解」がないからです。
しかし、「性」に関しての価値観を教えられるのは子どもの養育責任がある保護者だけです。外部の人間が教えられるのは「正解・不正解」がある社会的価値観のみです。「ママ(パパ)はこう思っているけど他の人はまた違った考えを持っている人もいる」というスタンスで子どもに伝えてください。
日々のコミュニケーションを通じて子どもの心に安心感を育むことです。その積み重ねが、将来的に子どもが性や人間関係で迷ったとき、相談できる家庭であることが重要だと心得ましょう。
まとめ

性教育は、子どもが健やかに成長し、多様な価値観や人間関係の中で自分らしく生きるための重要な土台です。特別な日にまとめて「教える」ものではなく、日々の生活で生まれる疑問に丁寧に向き合い、少しずつ知識や理解を深めていくプロセスと言えます。
年齢に応じて、体や心、命やコミュニケーションに関する情報を的確に伝え、子どもの反応を見ながら無理のないペースで進めていきましょう。最近はwebでも色々な情報を得ることが出来、性教育はより身近な物になりつつあります。決して難しくありません。教えられてこなかった保護者自身も自分の「性」についてアイデンティティや指向について向き合ういい機会になるかもしれません。親子で対話しながら子どもの安心できる成長を支え、自他を尊重する人間性を育むことで、一緒に社会生活を営む力を高めましょう。
この記事を執筆した藤原美保さんに相談してみませんか?
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で藤原美保さんに子育ての悩みを相談できます。
藤原美保さんへの相談ページを見てみる
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

療育20年、放課後デイ10年運営のベテラン。子どもの「できない」に悩む親へ、行動の原因と対策に徹底的にサポート。幼少期にこそできる家庭内療育を提供。発達障害の子への性教育も。 これまでに、『発達障害の女の子のお母さんが、早めに知っておきたい「47のルール」』(エッセンシャル出版社)、『発達障害の女の子の「自立」のために親としてできること 』(PHP研究所)と2冊の本を執筆。現在も出版に向け本の執筆をつづけている中、子育てのポータルサイトにて発達障害の子の子育てコラムを連載中。



















































