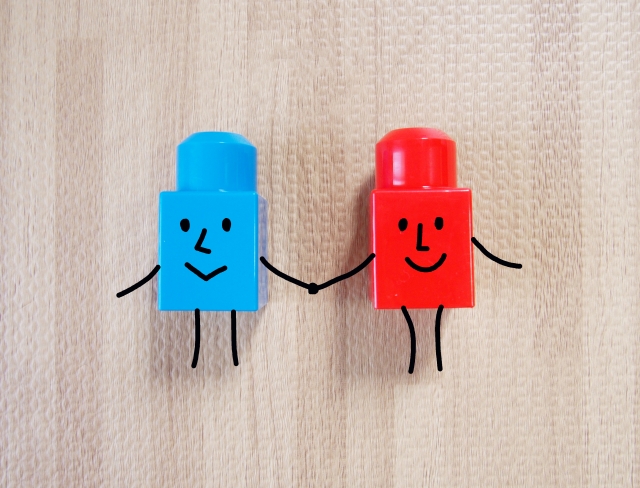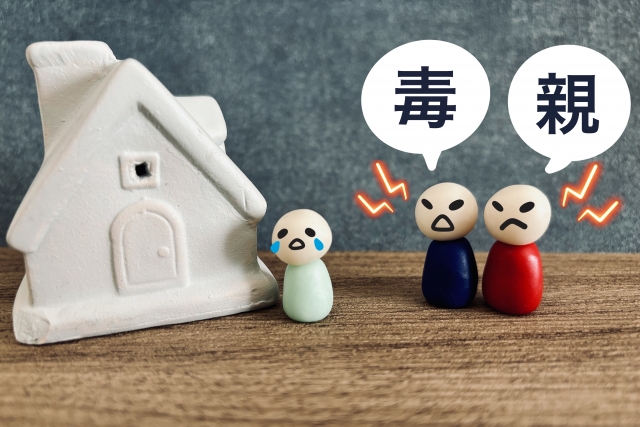くちゃくちゃ食べるわが子。癖?身体の問題?音の原因や改善方法
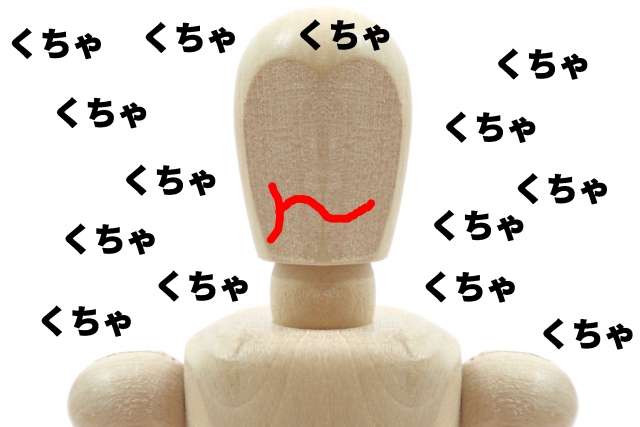
子どものちょっと困った癖のひとつ「くちゃくちゃ食べ」。クチャクチャと音を立てて食べる人、いわゆる「クチャラー」になるのは、単なる癖なのか、身体的な問題なのか…。子どもの発達支援に10年以上携わってきた羽野こはるさんが原因と対処法を解説します。
目次
咀嚼音だけじゃない!くちゃくちゃ食べがNGな理由

くちゃくちゃ食べを直すべき理由は、大きく3点あります。
くちゃくちゃ食べる音が不快
くちゃくちゃ食べの一番大きな問題は咀嚼(そしゃく)音です。人間は不規則で粘度のある音を不快に感じる傾向があります。海外のある調査では「犬の鳴き声や咳払いよりも、咀嚼音の方が人をイライラさせる」という報告もあります。音への過敏さは人によって違いますが、くちゃくちゃ食べの咀嚼音は多くの人が嫌うものだといえるでしょう。
口の中が見えることが不快
口の中で食べ物が崩れていく様子が見えるといった、視覚的な不快感を与える可能性もあります。唇を閉じずにくちゃくちゃと咀嚼すれば、口の中のものが周りに飛ぶこともあるでしょう。他人を不快にさせるだけでなく、テーブルや自分自身も汚れますよね。
マナー上の問題
食事のマナーに関しては国によって違いがありますが、日本では口を開けて食べるくちゃくちゃ食べはマナーが悪いといわれます。マナーは、人間関係や社会生活に大きく関わるものです。なぜなら、マナーを守れるかどうかは“場をわきまえた行動が取れるか”、“人の気持ちを考えられるか”といった人間性の判断ポイントにもなるからです。「自分は気にならないから直さない」というのは友達や異性関係、仕事の場においても通用しないでしょう。
くちゃくちゃ食べの多くは癖。子どものうちに直すべき

くちゃくちゃ食べは、ぜひ子どものうちに直しておきたいところ。なぜなら、くちゃくちゃ食べは周囲を不快にさせる癖ですが、大人になると他人は注意しにくいからです。誰にも注意されなくても、友人や異性が一緒に食事を取りたくないと離れていったり、上司からマナーを守らない人だと評価が下がってしまって困るのは本人です。
くちゃくちゃ食べは、無意識におこなっていることが多いようです。筆者が小学生の時、給食の時間にくちゃくちゃ食べをする友人が他の生徒に指摘されたことがありました。友人は自覚がなかったため驚いた様子で、「そんなこと誰にも言われたことがない」と反発していました。
食事は1日3回、毎日さまざまな人やシチュエーションで行われるもの。くちゃくちゃ食べの癖を自覚しないまま大人になって嫌な思いをするよりも、親が指摘できる子どものうちに直しておきたいですよね。
くちゃくちゃ食べるのが直らない6つの原因
くちゃくちゃ食べは単なる癖の場合もありますが、身体的な要素が原因になっている場合もあります。本章では、くちゃくちゃ食べの考えられる原因について解説しましょう。
- 幼少期からの癖
- 食べ方や姿勢に問題がある
- 嚙み合わせが悪い
- 口呼吸
- 口周辺の筋肉の弱さ
- 舌の動かし方に問題がある
それぞれの原因について詳しく見ていきます。
1.幼少期からの癖
幼少期から口を開けてくちゃくちゃとかむ習慣があり、直すきっかけがないまま残ってしまうことがあります。幼少期からの癖が残るパターンとしては、次のようなことが挙げられます。
- くちゃくちゃ食べをする家族がいて、それをまねて癖になる
- テレビをぼーっと見ながら食べる、喋りながら食べるといった習慣から癖になる
- 指しゃぶりの癖が長く続いたことで舌が正しい位置よりも低くなり、舌の動かし方が前後運動になりやすいため咀嚼音が出てしまう
- 口呼吸をする癖があると、食べるときに苦しく感じて口を開けてしまうことでくちゃくちゃ食べになる
筆者が支援していた子どもの中には、運動自体が苦手で口の動きや力が弱い子どもがいました。そういった子どものケースでは、必要以上に長い時間食べ物をかんだり、飲み込むのが苦手だったりします。特に魚のようなバラバラの食材を口の中でまとめたり、パンのような唾液と混ぜることで飲み込みやすくする食べ物が苦手でした。全体的に食べ方が幼く、くちゃくちゃという咀嚼音が目立ちました。
2.食べ方や姿勢に問題がある
食事中にくちゃくちゃと音を立ててしまう原因には、以下のような要因が隠れていることがあります。
- 一口の量が多くなかなか飲み込めない
- 焦って食べるため噛み方が雑になっている
- 食事のときの姿勢が悪い
- 奥歯ではなく前歯で噛む癖がある
一口の量が多くたくさんかまないと飲み込めない、焦って食べるためかみ方が雑といった食べ方も、くちゃくちゃ食べる原因になりやすいといえます。
また、食べるときの姿勢が悪く背中を丸めて首を前に出したままだと、食べ物が口の奥に運ばれにくくなります。奥歯でしっかりとかめず、手前の小臼歯でかむ癖が付くと、飲み込みやすい大きさまでかむことができません。その状態で次々と口に食べ物を運ぶと、口の中がいっぱいになり口を開けてくちゃくちゃ食べをしたり、口から食べ物がこぼれたりするのです。
運動発達の遅れや筋力不足で姿勢が崩れ、上記のような状態になることもあります。
<関連記事>

3.嚙み合わせが悪い
噛み合わせが悪く口を閉じることができないのも、くちゃくちゃ食べの原因になる場合があります。
歯並びや嚙み合わせが悪く上下の歯でバランス良くかめないと、かみやすいところに食べ物が当たるように歯をずらしてしまいます。その際に、咀嚼音が出やすくなります。
4.口呼吸
人間の本来の呼吸は鼻呼吸とされています。しかし、実際には子どもの約3割が「お口ぽかん」の状態、つまり口呼吸をしているという研究結果があるほど、口呼吸をしている子どもは多いようです。
幼少期からの癖や、鼻炎などが原因で口呼吸をしていると、食事中にも口を開けてしまうためくちゃくちゃ食べになります。
口呼吸をしていると唾液の分泌が少なくなり、食べ物をうまく溶かして飲み込めません。そのため必要以上の咀嚼が必要となり、咀嚼音が発生してしまいます。
5.口周辺の筋肉の弱さ
口の筋肉が弱く、口を閉じ続けていられないこともくちゃくちゃ食べる原因の一つ。
また、口の筋肉が弱いことでしっかりかめず、歯の使い方のバランスが悪くなり、歯並びや噛み合わせの悪化につながることもあります。
6.舌の動かし方に問題がある
舌を口の中で前後・左右・上下にうまく動かしながら食べ物を運べないと、口を閉じたまま咀嚼することが難しく口を開けることになってしまいます。
また、舌の付け根のひだ(舌小帯)が短く、舌の動きが制限されている場合もうまく動かすことができずにくちゃくちゃ食べになります。舌を伸ばすと中央が引っ張られてハート形になるほど舌小帯が短いと、食べ方や発音に支障が出る場合があります。
くちゃくちゃ食べる癖を直すには?
それでは、くちゃくちゃ食べの癖を直すにはどうしたら良いのでしょうか。本章では、身体的な原因とそうでない原因に分けて解説します。
くちゃくちゃ食べる原因が身体的な問題の場合
| 原因 | 直し方 |
|---|---|
| 歯並び・噛み合わせ | 歯科や口腔外科を受診し、必要に応じて歯科矯正などの治療を行う。 |
| 鼻炎による口呼吸 | 耳鼻科を受診し、必要に応じて鼻の通りを良くする薬などを服用する。 |
| 舌小帯が短い | 舌小帯が短いことで舌の動きが悪い場合は、レーザーなどでひだを切る治療がある。 |
| 口や舌の筋力の弱さ | 「口輪筋」という口周りの筋肉や舌の筋力が弱い場合は、口を大きく開け閉めする体操、舌を伸ばしたり上下左右に曲げたりする体操をする方法がある。 |
| 全身運動が苦手・筋力が弱い | 公園のアスレチックやプールなどで体を動かしたり、体操やダンスをしたりする。 |
全身運動が苦手、筋力が弱い子の場合は、まれに年齢に比べた運動発達の遅れや、身体面も含めた全体発達の遅れが原因になっている場合もあります。身体的な問題がくちゃくちゃ食べにつながっている場合は、保健センターや療育センターに相談するのが良いでしょう。
くちゃくちゃ食べる原因が身体的な問題以外の場合
身体面に原因がない場合は、食べ方や姿勢、意識を改善することでくちゃくちゃ食べの癖を直すことができます。
くちゃくちゃ食べていることと、それを直す必要があることを伝える
くちゃくちゃ食べは自覚していないことが多いため、子どもが分かりやすい言葉で指摘してあげましょう。鏡などを使ってくちゃくちゃ食べていることの自覚を促すのも◎。その上で、一緒に直していくことを本人に合意してもらいます。
くちゃくちゃ食べは、なぜ直す必要があるのかを一緒に考える
やみくもに「ダメ」と言っても、なかなか直りません。くちゃくちゃと食べる音が他の人に嫌な思いをさせること、マナーについて一緒に考えます。子どもが分かりやすいように「雨にぬれたら嫌だよね、ギーって音が嫌いだよね。それと同じだよ」といったように例を挙げて感覚を共有するのも良いでしょう。
くちゃくちゃ食べるのを直すメリットを伝える
メリットがなければ、子どもはなかなか自ら直そうとは思わないものです。例えば、好きな芸能人がきれいに食べている姿をテレビで見せながら「食べ方がきれいだと、見ていて気持ちがいいよね」とか「なりたい職業に就いたときにきれいに食べると褒められるよ」といったように憧れや理想と結び付けるのも効果的です。
くちゃくちゃ食べにならない方法を教える
子どもは「◯◯をしない」と注意されても、どうすべきか瞬時に分からないことが多いものです。例えば「走らないで」と言われても、“走らない=歩く”と連想できないのです。また、抽象的に注意されても具体的な方法を細分化して理解しないと改善されません。「ちゃんと座って」と言われても、“ちゃんと=背中を伸ばす・足を下ろす・前を向く”と言った行為につなげられない場合と同じです。したがって「くちゃくちゃさせないで」と注意するのではなく、初めは「背中を伸ばして」「少しずつ口に入れて」「口を閉じてかんで」という伝え方で教えていきます。
子どもの間に治すためには家族の協力が大切

他人に不快感を与えることの多いくちゃくちゃ食べの癖は、子どもの間に直しておきたいものです。自覚がないことが多いため、自然に直るのを待っていても学校や友人関係の中で指摘され嫌な思いをすることがあるかもしれません。
くちゃくちゃ食べの中には、身体的な問題が原因となっていることもあります。その場合は、適切な治療や運動をすることで解決することはあるでしょう。
また、身体面で問題がない場合には家族が協力し適切に教えていくことで、直せたという例も多くあります。何より心配なのは、くちゃくちゃ食べで周りに不快感を与えているのに嫌な思いをするまで誰も指摘・協力をしないこと。普段から一緒に食事を共にする家族が、指摘・協力し直してあげましょう。
親が直そうと試みてもなかなか直らない、身体的な問題なのか単なる癖なのかの判断がつかないといった場合は、保健センターや療育センターに相談してみましょう。くちゃくちゃ食べる癖が子どもの習慣として定着する前に、できるだけ早くアプローチすることも大切です。
<関連記事>子どもの食事や食育に関する記事はこちら
・体や心だけじゃない! 脳を育むこともできる食育とは?
・小学生のおやつ選び3つのルール、食べすぎ対策を食育のプロが解説!厳選おやつ10種も紹介
・中学生のダイエット、簡単に成功させる方法や注意点を親向けに解説
<参考>
『発達につまずきを持つこと身辺自立 ー基本の考え方と指導法』湯汲英史編、武藤英夫・田宮正子著(大揚社)
『子どもの“お口ぽかん”の有病率を明らかに -全国疫学調査からみえた現代の新たな疾病-』2021年 新潟大学
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

社会福祉士、保育士。児童発達支援管理責任、相談支援専門員の資格取得歴あり。子ども発達支援センター、療育機関、障害児学童、保育園などで子どもの発達支援を10年以上行う。200人以上の発達に不安のある子どもや保護者に関わり、現場の発達支援や相談支援、保護者支援プログラムの開催等を担う。プライベートでは、ほとんど年子3人の母として育児奮闘中。現在はフリーライターとして活動。webメディアやホームページ、SNSなどで、職歴や育児経験を活かした記事執筆、遊びやおもちゃの紹介などを行っている。ブログ: https://hanohouse.hatenablog.com/インスタグラム:hano.stagram