ネットリテラシー教育とは?必要な理由や親も知っておきたい対策方法

春は入学・進級の季節。お子さんがスマートフォンやタブレットを使い始めるタイミングとしても多い時期です。また、クラス替えや新しい友達との関係づくりなど、環境が大きく変わる中で、ネットを通じたやりとりが増えることもあります。
今では「SNSでつながること」が友達関係のスタートになることもあり、ネットの使い方ひとつで人間関係がうまくいくこともあれば、逆にトラブルの原因になることもあります。
「使いすぎが心配」「夜遅くまで見ているみたい…」「知らない人とつながっていないかな?」そんな心配を抱える保護者も多いはずです。
そこで今回は、ネットリテラシー教育の基本と、家庭でできる対策について、保護者の立場から一緒に考えていきたいと思います。
目次
ネットリテラシーってなに?

ネットリテラシーとは、「インターネットを上手に、安全に使う力」のことを指します。悪いことに巻き込まれない「防御」の力だけでなく、ネットの便利さを活かして学んだり情報を得たりする「活用」の力も含まれています。またネットリテラシーには、以下のような側面があります。
- 時間のコントロール:使いすぎない工夫、見たいものを見たら終わる習慣
- 目的の意識:連絡や調べものなど、使う目的を意識すること
- お金や課金の知識:必要な出費かどうか考える力
- 情報の見極め:ネット上の情報をうのみにせず、正しいかどうかを考える力
- SNSの活用:つながり方や発信の仕方、マナーや個人情報の扱いに注意すること
- 生成AIの活用:創造的に使いながらも、誤情報や悪用に注意し、自分や周りの幸せに役立てること
近年では、生成AIなどの新しい技術をどう活用するかという視点も、ネットリテラシーにおいて重要になってきました。生成AIは、文章や画像を作るなど子どもたちの学びや創造をサポートする強力なツールになる一方で、誤った情報を生み出す可能性もあります。だからこそ、「ネットをどう使えばよいか」を常に考える力が必要です。
また、SNSの投稿や個人情報の扱い方にも注意が必要です。写真や名前、住所、学校名などを安易に公開してしまうと、思わぬトラブルや犯罪に巻き込まれるリスクがあります。さらに、ネットに一度アップされた情報は完全に消えることはなく、「デジタルタトゥー」として将来に影響を及ぼすこともあります。
このように、ネットには多くの側面があるため、ネットリテラシーは「一度教えて終わり」ではありません。親子で一緒に考えながら、少しずつ身につけていく力です。
「危ないから使わせない」ではなく、「どうすれば安全に使えるか」「どんなことに気をつけるべきか」を対話しながら段階的に学んでいくことが、とても大切です。
スマホ依存を防ぐには?

自分でコントロールできる力を育てよう
「気づいたら1時間も見ていた」「なかなか止められない」――そんな声は、子どもだけでなく大人からもよく聞かれます。
特に動画やゲームには、私たちが夢中になるような仕組みや工夫がたくさん盛り込まれていて、つい長時間見続けてしまうように意図的に設計されているのです。
つまり、それにハマってしまうのは「意志が弱いから」ではありません。そうした仕組みによる影響なのです。
だからこそ、スマホやゲームとの付き合い方には、自分自身をコントロールする力=自己コントロール力を、意識的に育てていくことが大切なのです。
発達段階に合わせたサポートが大切
「自分で時間を守れるかどうか」は、年齢だけで判断できるものではありません。たとえば…
- 放課後に遊んだあと、約束の時間に帰ってこられるか
- お風呂や宿題など、毎日のルールを守れているか
こういった日常生活の中で時間を管理できていない場合、スマホだけを「自分でコントロールしてね」と言っても、うまくいかないことが多いのです。
まずはスマホ以外の生活リズムを整えることが、ネットリテラシーの第一歩になります。
スマホルールは「親の命令」ではなく「親子の約束」

「宿題が終わったら、YouTubeを30分だけ見てもOK」など、時間で管理するルールを取り入れている家庭も多いかと思います。
ただし、ルールを一方的に押し付けるのではなく、「どうしたら使いすぎを防げるか?」「どんな時間の使い方が、自分にとって心地いいか?」といったことを親子で一緒に考えて決めていくことが、何より大切です。
また、親自身がその姿勢を実際に見せることも、子どもにとって大きな学びになります。
たとえば
- 食事中はスマホを置いて、家族との会話を楽しむ
- 子どもが学習している間は、自分もスマホを控える
上記のような小さな行動でも、言葉以上に子どもの心に響くことがあります。
つい見すぎる…その影響って?
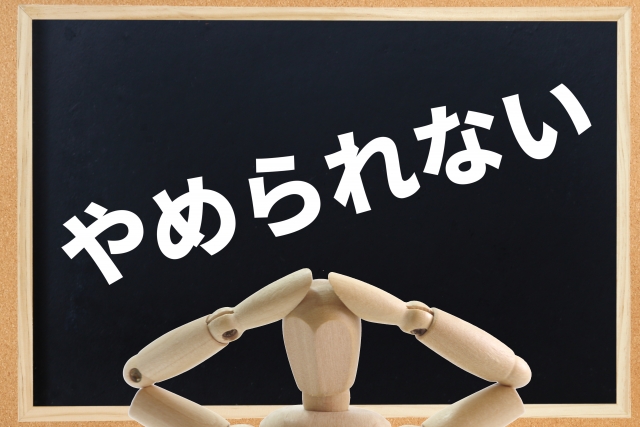
ネットゲームやさまざまなウェブサイトには、「つい長時間使ってしまう」「何度も見たくなる」ような仕組みがたくさんあります。
たとえば以下のようなことです。
- 次の動画が自動で再生される
- ログインボーナスがもらえる
- 「いいね」やコメントが気になる
こうした仕掛けは、子どもたちの注意を強く引きつけ、やめどきを見失わせてしまうことがあります。その結果、以下のような影響が現れることもあります。
①睡眠の質が下がる
寝る直前までスマホの画面を見ていると、脳が興奮状態のままになり、寝つきが悪くなったり、深く眠れなかったりすることがあります。
②イライラしやすくなる
ゲームがうまくいかなかったり、SNSで気になるコメントを見たりすると、気持ちが不安定になることもあります。
③人との会話が減る
スマホを見ながら食事をしたり、話している最中でも通知に気を取られたりすることで、家族や友人とのやりとりが少なくなってしまいます。
④学習への集中力が落ちる
一度スマホに気を取られると、元の勉強に戻るまでに時間がかかります。短時間でも何度もスマホを見る習慣は、集中力の低下につながります。
⑤家族のコミュニケーションが減る
同じ空間にいても、それぞれがスマホを見ていて会話がない――そんな状況は多くの家庭で見られます。気づかないうちに、子どもの小さな変化を見逃してしまうかもしれません。
このように、スマホの使いすぎは心や体、そして人間関係にも少しずつ影響を与えていきます。
親子での約束の例~ルールではなく、“一緒に考える約束”へ~

スマホやインターネットとの付き合い方について、「じゃあ、どんな約束をすればいいの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
つい「○○は禁止!」「○時以降は絶対使わない!」と一方的にルールを決めたくなりますが、本当に大切なのは、「どう使えばいいか」「どうすればお互い気持ちよく使えるか」を親子で一緒に考えることです。それが、ネットリテラシー教育の第一歩となります。
ここでは、家庭で取り入れやすい“約束の例”をご紹介します。お子さんの年齢や家庭のライフスタイルに合わせて、無理のない形で話し合ってみてくださいね。
1.時間に関する約束
- 平日は1日○分まで
- 寝る1時間前にはスマホを置く
- 勉強や宿題が終わってから使う
- 使った時間を記録して一緒に見直す
「見すぎた日はどんな気分だった?」「時間を決めて使えた日はどうだった?」など、使ったあとのふり返りも大切です。
2.使う場所に関する約束
- 食事中はスマホを置いて、会話を大切にする
- 寝室にはスマホを持ち込まない
- お風呂やトイレには持っていかない
スマホを使用する場所のルールがあると、「ながらスマホ」や「使いっぱなし」を防ぎやすくなります。
3.使うアプリに関する約束
- 新しくアプリを入れる前は、保護者と相談する
- 推奨年齢(レーティング)を確認してから使う
- 「みんなが使っている」ではなく、「自分に必要かどうか」で判断する
アプリの中には、大人向けの内容や、チャット機能など注意が必要なものもあります。使う前に中身を一緒に確認することが安心につながります。
また最近では、生成AIを活用したアプリも増えてきています。イラストを描いたり、文章を作ったりするのに役立つ反面、間違った情報を出してしまうこともあるため、使い方には注意が必要です。
- 「どんな目的で使うのか」
- 「人を傷つけるようなことに使っていないか」
- 「自分の力を高めるための使い方になっているか」
- 「自分の考えとして発表していい内容か(自らの考えを述べる場面でコピペをしていないか)」
といったことを親子で一緒に確認しながら使うことが大切です。「すごいから使わせる」ではなく、「どのように使えば自分や人のためになるか」を考える力を育てていきましょう。
4.知らない人とのやりとりに関する約束
- 知らない人とのやり取りには注意する
- もし怪しいメッセージが来たら、すぐに保護者に相談する
- ネット上でのやりとりは、顔の見えない相手であることを忘れない
- ネット上の情報を鵜呑みにしない
「ネットで出会った人=信頼できる人」と思い込んでしまう子どももいます。実在するかどうか分からないことや、プロフィールに嘘がある場合があることを繰り返し伝えましょう。
5.お金・課金に関する約束
- 課金をするときは必ず親に相談する
- 課金をする場合も、毎月のおこづかいの中でおさまるようにする
- 無料ゲームでも「広告」や「課金誘導」があることを知っておく
「勝ちたいから」「便利にしたいから」と軽い気持ちで課金してしまうこともあるものです。ゲームの仕組みやビジネスモデルについても、親子で話してみるのがおすすめです。
親子間の約束は、成長とともに“見直す”ことが大切
年齢や使う目的の変化に合わせて、親子間の約束は見直される必要があります。一度決めたら終わりではなく、「最近どう?」と定期的に振り返る時間を持つことで、お子さんも自分の使い方に自信が持てるようになります。
そしてなにより大切なのは、「親が一緒に考えてくれている」という安心感。スマホを持たせることは信頼の証であり、その信頼をどう育てていくかが鍵となります。
そもそもインターネットにはどんな危険があるの?
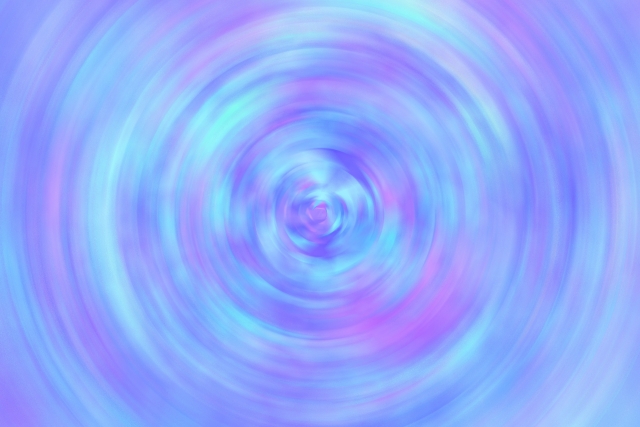
ここで、そもそもインターネットにはどんな危険があるのかについて考えてみましょう。
- 詐欺やなりすまし
- 個人情報の流出
- SNSでのトラブルや炎上
- デジタルタトゥー(投稿がずっと残ること)
- フィルターバブル(インターネット上で、自分の好みや考えに合った情報ばかりが表示される現象のこと)
- エコーチェンバー(同じ意見や価値観を持つ人たちの間で、情報が繰り返し共有・強調されていく環境のこと)
デジタルタトゥーとは、SNSに投稿した写真や日常の出来事が、数年後に思わぬかたちで問題になることを指します。たとえば、就職活動の際に企業がSNSをチェックすることがあり、昔の何気ない投稿が思わぬ影響を及ぼすこともあります。
だからこそ、インターネットの便利さと危険性の両方について、子どもとしっかり共有し、「どう使うべきか」を一緒に考えていくことが大切です。
デジタルタトゥー~将来の就職活動にも影響する、ネットの記録~

スマホやSNSは、日々の出来事を手軽に共有できる便利なツールですが、その一方で、「消したつもりでも消えない情報」があることをご存じでしょうか。こうしたネット上に残り続ける情報は、「デジタルタトゥー」と呼ばれています。このデジタルタトゥー、実は将来的に就職活動にも影響する可能性があります。
SNSの投稿が採用判断の材料になることも

大学で就職活動の指導をしていると、必ず伝えるのが「SNSの投稿には気をつけよう」ということです。
たとえば、授業中にスマホでこっそり写真や動画を撮り、それをSNSに投稿するといった“軽いノリ”の行動でも、企業からは「ルールを守れない人」と見なされてしまう可能性があります。
最近では、応募者のSNSアカウントを調査する企業も増えており、就職の最終段階でチェックされることも珍しくありません。
さらに投稿を削除したつもりでも、一度インターネット上に出た情報は、他人に保存されたり拡散されたりして、完全に消すことは難しいのです。
悪質な詐欺やトラブルにも要注意

さらに怖いのが、個人情報が詐欺や犯罪に使われるケースです。たとえば以下のようなことが挙げられます。
- SNS上で知り合った人に、住所や年齢、写真などを教えてしまった
- 「秘密のバイトがあるよ」「写真を送って」と言われてやりとりをした
- だまされて裸や体の一部の写真を送ってしまった
こうした行為が後になって、金銭を要求されたり、「画像を拡散する」と脅されたりするなど、大きな被害につながることもあります。しかもこれは、男女を問わず起きている深刻な問題です。
ネット上では、優しそうな言葉で近づき、子どもをだますケースも少なくありません。まるで「恋人のように」振る舞い、最初は親しげに見せかけながら、徐々に相手をコントロールしていくような手口が使われるのです。
ネットリテラシー教育は今すぐ始めよう

「ネットリテラシー教育って、いつから始めればいいんですか?」
そんな質問をよくいただきます。でも、答えはとてもシンプルで「気づいたときが、始めるとき」なのです。
もちろん、年齢に応じた声かけや指導の仕方はあります。でも大切なのは、「今からでも遅くない」ということ。
小学生でも、いや、もっと小さな子どもでも始めていい——それが、ネットリテラシー教育の基本的な考え方です。
小さな“気づき”からスタートを

「スマホやタブレットって便利だけど、危ないこともあるんだね」「大人でも騙される時代だから、子どもはもっと気をつけなきゃね」
こうした親子の何気ない会話こそが、ネットリテラシー教育の最初の一歩です。
まずは、スマホやタブレットの使い方、そして時間のコントロールから始めましょう。さらに、ネット上で実際に起こっているトラブルや事件について「知っておくこと」もとても大切です。
たとえば、信号を無視して交通事故にあった人の話を子どもと共有し、「だから青信号を待つんだよね」と話し合うように、ネットにも“安全な歩き方”があることを、一緒に学ぶ時間が必要です。
「学校まかせ」ではなく、みんなで見守る

保護者として気になるのは、「学校ではどんな指導をしているのか」という点かもしれません。でも、学校任せ・家庭任せでは、子どもを守ることはできません。
- 放課後や家庭で起きたトラブルが、学校に伝わっていない
- 学校では把握しきれないネットの利用が進んでいる
こうした現実があるからこそ、学校・家庭・地域が連携して、子どもを見守る体制づくりが大切なのです。
「こんなことが起きているらしいよ」「ちょっと気になるアプリが流行っているみたい」
そんな情報を保護者や先生のあいだで共有し合うことが、ネットトラブルの“予防線”になります。
小学生も中高生も、「免許なしで運転」しているようなもの
スマホやタブレットを持っている子どもたちの中には、「ネットを安全に使う力」を十分に身につけないまま、自由に操作している子もいます。それはまるで、運転免許を持たずに車を運転しているようなものです。
技術やサービスが進化し続ける一方で、ネットトラブルは年々、複雑化・巧妙化しています。だからこそ、ただルールを教えるだけでは不十分です。
- 「なぜそうするのか?」
- 「どうしたら自分や友達が困らないか?」
- 「ネットはどうすれば自分の幸せに役立てられるか?」
こうした問いを通して、“考える力”を育てるネットリテラシー教育が、今ますます重要になっています。
子どもの未来のために、「今」始めよう
子どもたちは、これからの社会をネットと共に生きてい世代です。だからこそ、今のうちから「安全な使い方」や「正しい付き合い方」を身につけていくことが、将来の安心につながります。
小さな一歩でもかまいません。まずは、「一緒に考えてみようか」というひと言から——。
ネットリテラシー教育を、家庭の会話の中から始めてみてはいかがでしょうか。
学校ではどのような指導がされているのか

スマホやインターネットの正しい使い方については、これまでも学校で「情報モラル教育」として学ぶ機会がありました。ネットの危険性に関する学びとして、警察や外部の専門家を招いた講話や、ビデオ教材を活用した授業などが、各地の学校で行われてきました。
最近では、「ネットは怖いから気をつけよう」という呼びかけにとどまらず、ネット社会の中で子どもたちがどう行動するか、自分の発信や言動に責任を持つことといった、より実生活に即した内容を扱う取り組みも増えています。
たとえば──
- SNSでの言葉づかい
- 相手を傷つけないための配慮
- 情報を鵜呑みにせず、正しく見極める力
といった視点から、“ネットの中でも思いやりをもって行動する”という考え方が、少しずつ広がってきているのです。
学校でどんなことを学んでいるのか、親も知ろう
「うちの子、学校でスマホの話とかしてるのかな…?」
そんなふうに気になった時は、ぜひお子さんとの会話や、学校の懇談・保護者会などを通じて、情報を集めてみてください。
たとえば──
- 「どんな授業だった?」
- 「どんな映像を見たの?」
- 「先生は何て言ってた?」
といったシンプルな質問でも、子どもの様子や考え方が見えてくることがあります。
また、学校から配布される通信や教育だよりに、授業内容や実際の指導事例が紹介されていることもあります。学校での取り組みを知ることで、家庭でもネットリテラシーについて話題にしやすくなります。
家庭教育もやっぱり重要
学校では全員に同じ内容を教えますが、以下のように子どもたちのネット環境は家庭によって大きく違います。
- 自分専用のスマホがある子
- 家族のスマホを使っている子
- タブレットはあるけれど通信制限がある家庭
- ゲーム機でネット接続している家庭 など
だからこそ、学校の教育に頼るだけでなく、それぞれの家庭での声かけやルールづくりが欠かせません。
学校と家庭がそれぞれの役割を持ち、連携しながら子どもたちを支えていくことで、より安全で前向きなネット利用の力が育っていきます。
まとめ:親子でネットの使い方を話し合おう

スマートフォンやインターネットは、もはや「特別な道具」ではなく、子どもたちの生活に欠かせない存在となっています。今やそれは、日常生活の一部です。
だからこそ大切なのは、お子さん自身が「上手に使える力」を育てること。
「使わせる or 使わせない」といった二択ではなく、どう使えばいいのかを一緒に考える関係が、これからのネット社会を生きるうえで重要です。
たとえば──
- 「どうやって使うといいかな?」
- 「ちょっと使いすぎかも…どうしよう?」
そんな日常のちょっとした会話が、ネットリテラシーを育てる第一歩になります。
大人の役割は「ただ命令すること」ではないのです。お子さんが安心してデジタル社会を生きていけるように、まずは家庭での小さな会話から始めてみませんか?
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

札幌国際大学・准教授。北海道・札幌市の公立小学校で20年間教諭を務め、2022年4月から、現職。ICT教育や道徳教育が専門。いろいろな子どもたちが前を向き、やる気だして頑張れるようにみんなが楽しい授業・分かる授業を展開。保護者や関係機関と連携を取りながら教育活動にあたってきた。NHKforSchoolでは、各種の道徳番組のほか、特別支援番組「u&i」「でこぼこポン」の監修も務め、発達障害やマイノリティの立場に寄り添った教育活動を考えている。


















































