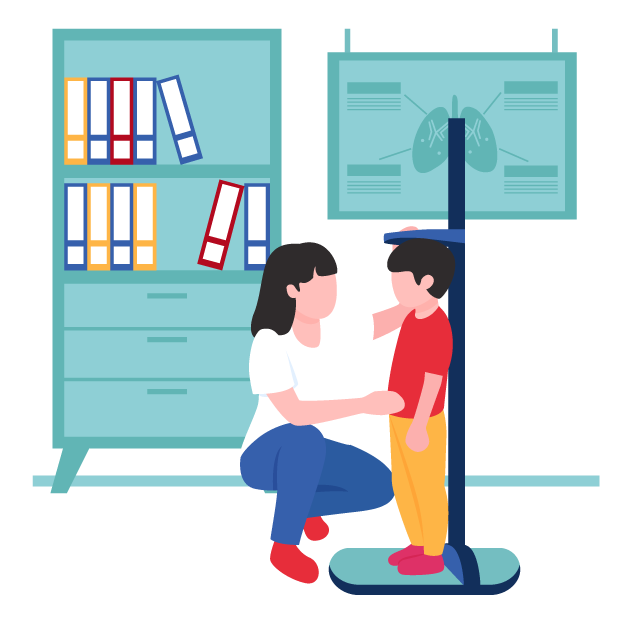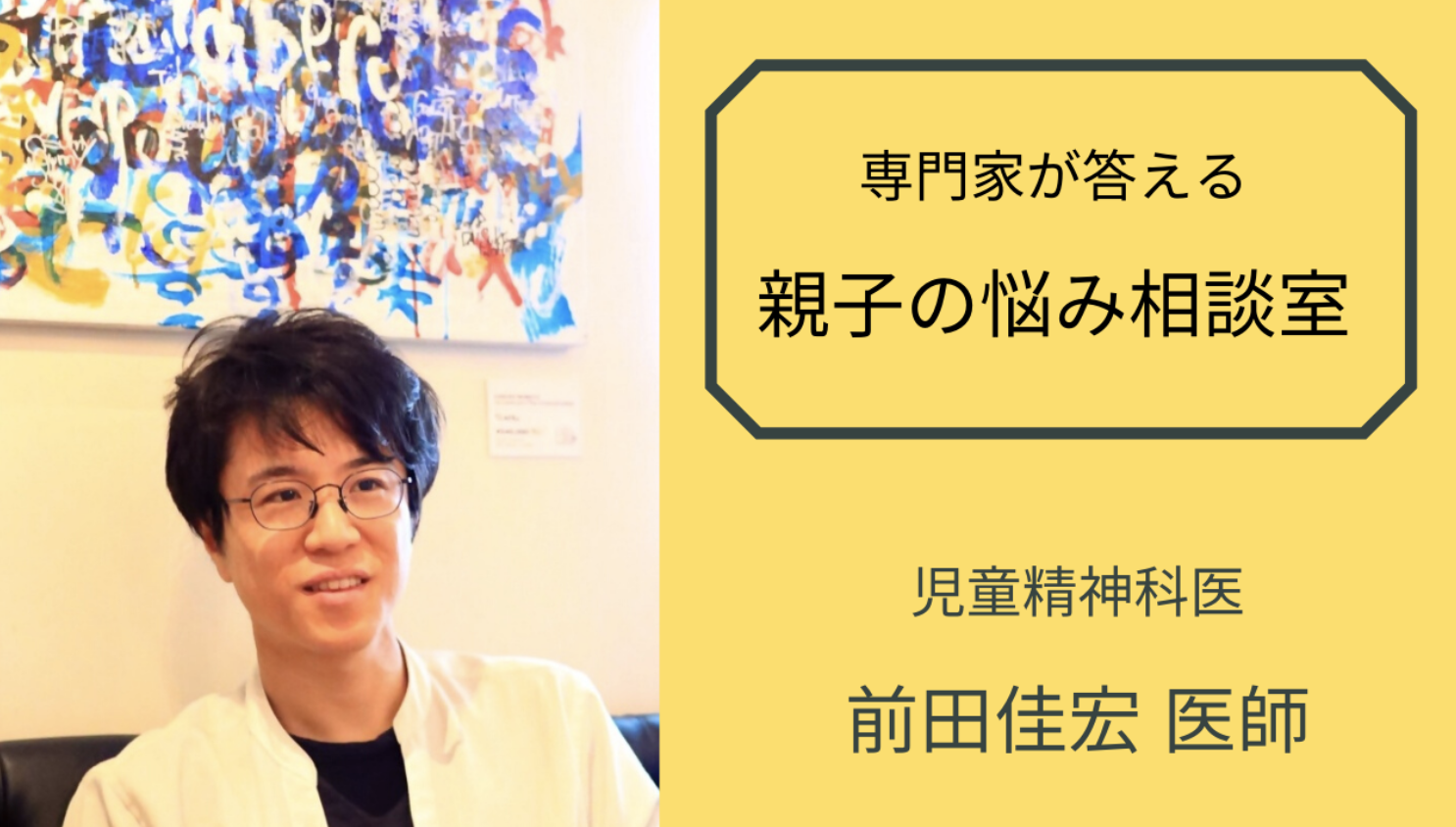中学生のお小遣い平均はいくらが相場?電子マネーで渡すメリット・デメリットをFPが解説

中学生のお小遣い。せっかく渡すなら無駄遣いしないだけでなく金銭感覚を身に付ける機会にしたいですよね。そこで、お金のプロであるFPの前佛朋子さんが一般的な相場や使い道を紹介するとともに、金銭感覚をつけるためには、月額制と必要なときに渡すのとどちらがいいか、将来のための電子マネーの導入の仕方などを解説します。
目次
中学生のお小遣いの相場は月2536円
「子どもにどれくらいのお小遣いをあげるのがいいのかしら?」
子どものいる家庭なら、とても気になりますね。特に小学生時代よりも行動範囲が広がる中学生の場合、お小遣いはいくらぐらいにするのがよいのでしょうか?
金融広報中央委員会が2015年に実施した「子どものくらしとお金に関する調査」によると、中学生の83.2%がお小遣いをもらっているとのこと。そして、相場は下記のような結果でした。
中学生のお小遣いの相場
| 最頻値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 1,000円 | 2,536円 | 2,000円 |
全体の平均値は2,536円ですが、最も回答の多かった額は1000円でした。また、全体の割合を見てみると、回答の多かった価格帯は以下の通りです。
中学生のお小遣いの割合
- 1,000円~2,000円未満:32.0%
- 2,000円~3,000円未満:20.5%
- 3,000円~4,000円未満:17.5%
中学生の子どもの約半数は、毎月1000~3000円程度のお小遣いをもらっていることがわかります。

お小遣いの使い道は「友達との外食やお茶代」
同調査では、中学生がお小遣いの使い道についても調べています。今回はその中から上位5つを紹介しましょう。
中学生のお小遣いの使い道
| 1位 | 友達との外食・軽食代 |
|---|---|
| 2位 | おやつなどの飲食物 |
| 3位 | 友達へのプレゼント |
| 4位 | 文房具 |
| 5位 | 家の人へのプレゼント |
1位が友達と外食・軽食代、3位が友達へのプレゼントという結果からも、友達付き合いにお金が必要であることが分かります。ほかにも、休日に友達と遊びに行くときの交通費やゲーム、小説や雑誌、まんが、映画代などにもお小遣いを使っているようです。
先ほどの相場と照らし合わせてみると中学生のお小遣いでは、まかなえないような気もしますが、私が子育てをしてきた経験からいうと現代の中学生は忙しく、部活動が活発だったり、高校進学のための塾通いが始まったり、遊びに行く機会は頻繁ではありません。
そのため、お金を使わなかった月の分を貯金したり、お年玉を活用したりしてやりくりできるようです。
月額制VS必要な時に渡す、どちらが正解?
では、金銭感覚を身に付けるためには渡し方はどのようにしたらよいのでしょうか? 毎月決まった金額を渡す月額制と欲しいものがある時にその都度渡す場合で考えてみましょう。
月額制お小遣いのポイント
中学生の子どもに月額でお小遣いを渡すなら、お金の使い道を計画する力を育てたいものです。そこで、お小遣いは毎月決まった日に渡すようにするとよいでしょう。
たとえば、毎月1日にする、あるいは、一家の大黒柱となる父親(母親)の給料日に渡すのもよいかもしれません。決まった日にお小遣いを渡すようにすれば、お小遣いをやりくりする期間が決まるので、計画的にお金を使いやすくなります。
また、お小遣い日を月初や給料日に設定しておけば、家計の予算立てもしやすくなるでしょう。
月額制お小遣いのメリット
おこづかいを月額制で渡す方法には、次のようなメリットがあります。
- 限りある範囲内で計画的にお金を使う力を育てることができる
- 高額で買えないものは貯金をして買うことを教えられる
- 自分で使い道を考えて使うことができる
- 将来、収入を得るようになったときのために、金銭管理能力を育てることができる
月額制の場合、おこづかいの範囲内で計画的にお金を使わないと、すぐにおこづかいが無くなってしまいます。失敗を重ねながらも、だんだんと上手なお金の使い方を身に付けていくのではないでしょうか。
月額制お小遣いのデメリット
ただし、いいことばかりではありません。お小遣いを月額制にすると、子どもにとってデメリットも出てきます。
- 欲しいものが欲しいときに買えない場合がある
- 時に我慢を強いられることがある
- 無計画にお金を使っていると、すぐにお小遣いがなくなってしまう
買いたいものが変えず子どもはたくさん我慢を強いられるかもしれません。しかし、欲しいものはお金を貯めて買うこと、計画を立ててお金を使うことは、大人になってから必要な力です。金銭管理をマスターするための試練と考えましょう。
月額制お小遣いに含まれるもの
子どものお小遣いに含まれるものは、食べ物や飲み物、本や雑誌など自分で欲しいものを買うためのお金や、友達と遊びに行くときに使うお金が一般的です。自分で使い方を考え、やりくりする範囲内の物事に使うお金として渡すのがよいのではないでしょうか。

必要に応じてお小遣いを渡す場合のポイント
お小遣いを子どもが欲しい時に渡す方法ですが、注意しないと必要以上のお金を渡してしまいがちです。いわれるままにお金を渡していると、家計に影響が出るおそれもあり、子どもの金銭管理能力も育ちません。
子どものお金を管理する力を育てるためには、まず使う目的を聞くことです。そのうえで、何にいくらくらいのお金を使う予定なのか、予算を立てさせます。
そして、親は子どもが予算を立てた額を渡すのがよいでしょう。こうすることで、子どもに計画性のあるお金の使い方を考えるきっかけを与えることができ、やりくりする力を育てることもできます。
欲しいときにお小遣いを渡すメリット
子どもがお小遣いを欲しいと言ってきたときに渡す方法には、次のようなメリットがあります。
- お小遣いが必要なときにもらえるので、不自由な思いをしなくてもいい
- 必要なときしか渡さないので、普段の無駄遣いを防げる
お小遣いが欲しいときに親に言えばお金をもらえるので、子どもは「お金がない」という不自由な思いをせずに生活できます。子どもにとっては好都合な方法かもしれません。また、子どもが嘘をつかない前提ですが、子どものお金を使い道を親が把握しやすくなります。もしかしたら、親にとってもお金について細かく考えなくてもいいので、楽に感じるかもしれませんね。
欲しいときにお小遣いを渡すデメリット
お小遣いを子どもが欲しいときに渡す方法は楽かもしれませんが、次のようなデメリットもあります。
- 子どもは親に言えばお金をもらえるものと勘違いしてしまう
- 決まった期間におこづかいの範囲内でお金を使うという計画性が養われない
- お金を貯めて物を買う機会がなくなるので、将来、金銭管理が苦手になる可能性がある
お小遣いは、子どもにお金の管理方法を教える絶好の機会です。また、欲しいからといっても際限なく渡せるものでもありません。欲しいときにお小遣いを渡す方法では、肝心なお金の管理能力を育てることができない点は留意したほうがよいでしょう。
欲しいときに渡す場合の注意点
お小遣いは、社会に出て収入を得られるようになったときに、限りある範囲内でお金をやりくりするための訓練という面があります。
大人になってから、お金の管理方法がわからずに生活が行き詰まってしまわないよう、子どものうちから、計画的にお金を使えるようにしておく必要があるのです。
そこで、子どもが欲しいときにお小遣いを渡す方法にする場合は、用途とおおよその金額を申告することをルールにして、目的を持ってお金を使えるよう根気よく教えていきましょう。
この記事を書いた前佛 朋子さんに相談してみませんか?
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で前佛さんに子育ての悩みを相談できます。
前佛 朋子さんへの相談ページを見てみる

お小遣いを電子マネー(QRコード決済)にするのはありかなしか
ゼネラルリサーチ株式会社が2020年1月に実施した「キャッシュレス決済」に関する調査によると、82.8%の人がキャッシュレス決済を利用していると答えています。中でも、スマートフォンを使ったQRコード決済は手軽に利用できて便利ですね。
また、キャッシュレス決済を利用しているのは大人だけではありません。10代にもキャッシュレス決済は普及してきています。
NECソリューションズ株式会社が一般消費者におけるキャッシュレス利用実態調査を行ったところ、15歳~19歳が利用している決済方法とその割合として、次のような結果が出ています。(※回答は複数選択)
15~19歳の決済方法の割合
- 現金:97.2%
- ICカードの電子マネー決済:44.5%
- スマホ決済(QRコード型):33.5%
- スマホ決済(タッチ型):14.2%
- クレジットカード:15.6%
- デビットカード:12.4%
- プリペイドカード:11.9%
この結果によると、よく利用する決済方法は現金ですが、これと並行して、4割強がICカードの電子マネー決済を、3割強がQRコード決済を利用していることがわかります。
中でもICカードの電子マネー決済、プリペイドカードにチャージして使う方法、QRコード決済などは、中学生でも利用できるキャッシュレス決済です。
いちいち子どもの持つカードにチャージするのが面倒と思う人もいるかもしれません。けれども、QRコード決済の中には、年齢制限のないものであれば、利用条件を満たせば中学生でも利用できるものもあります。次に紹介する2つのアプリは中学生でも利用できます。

中学生におすすめのスマホ決済アプリ
早速、それぞれの特徴をご紹介しましょう。
LINE Pay
LINE Payには年齢制限がなく、LINEアカウントがあれば誰もが利用できるQRコード決済なので、中学生でも利用しやすいでしょう。
便利な点は、友達同士であれば手数料なしで送金や受け取りができるところ。そこで、親がLINE内で友だちになっておけば、おこづかいを子どもに送金することができます。
PayPay
PayPayは法定代理人(親権者)の同意があれば、未成年でも利用することができます。親の同意があれば、中学生でも利用できるのでおすすめです。また、利用登録する際も、銀行口座やクレジットカードを紐づけしなくても、セブン銀行ATMからのチャージや親からの送金で利用でき、送金時も受け取り時も手数料は無料です。PayPayは比較的利用できる店舗が多いので、便利に使えるでしょう。

お小遣いを電子マネー(QRコード決済)にするメリット
お小遣いを、電子マネーやQRコード決済を利用してチャージや送金といった形で子どもに渡すと、決まった金額の範囲内でやりくりしなければいけなくなるので、計画性が身に付きます。
また、QRコード決済では送金機能を使えば、簡単にお小遣いを渡すことができるので、親にとっても非常に便利です。
それに、電子マネーやQRコード決済を利用したら、ポイントが貯まっていくのがうれしいところ。ポイントを貯めれば、買い物にも利用できます。
さらに、連携できるモバイルアプリを活用すれば利用履歴が確認できるので、お小遣い帳代わりにもなります。利用したら使いっぱなしにしないで、利用履歴を確認する習慣を付けさせましょう。
どのようなことにいくらお金を使ったのかを確認することで、無駄遣いをしないように気を付けることができますし、お金のやりくり力も身に付きます。

お小遣いを電子マネー(QRコード決済)にするデメリット
お小遣いを電子マネーやQRコード決済にすると便利ですが、デメリットになる面もあります。
ICカードの電子マネーの場合、紛失しないように気を付けなければなりません。下手をすれば、拾った人に使われてしまう可能性もあります。
そんな場合に備えて、SuicaやPASMOなどの交通系ICカードは記名して使いましょう。記名すれば再発行が可能です。記名はICカードを購入時に券売機で操作します。nanacoやWAONなどの流通系の電子マネーは必ず会員登録をしましょう。登録をしてあれば、紛失時に利用停止ができ、再発行してもらえます。
また、QRコード決済はLINE PayもPayPayも個人間で送金できる点は便利なのですが、中学生でも簡単に送金できる点は注意したいです。なぜなら、友達間で送金のやりとりをすることで、トラブルに巻き込まれることがあるかもしれないからです。
そんな心配を解消するには、友達間の送金に上限額を設定するとよいでしょう。また、設定次第で親の送金は受け取れても、子どもから誰かに送金することはできないようにする方法もあります。
さらに、電子マネーは現金のようにお金を使っていると意識しづらい点があるので、気軽に使ってしまいがちです。特に中学生ならスタンプなどのアイテムを買ったり、ゲームで課金したりと、お金を使い過ぎてしまう心配があります。しかし、課金を絡めたお金管理もこれからの時代に必要なことかもしれません。
もし、どうしても心配ならば、毎月チャージ額や送金額を決めて、決めた金額以上のお金を渡さないようにすることで金額的な損失は最小限に抑えられます。

中学生の金銭感覚を育てる3つのポイント
中学生のうちに金銭感覚を育てておくことは、とても大事です。正しいお金の使い方や管理のしかたを教えておけば、大人になり収入を得るようになったときに、しっかりとお金を管理できるようになります。では、どのようにして中学生に金銭感覚を身に付けさせればいいのでしょうか?それには3つのポイントがあります。
【ポイント1】お金は計画的に使うことを教える
お小遣いには限りがあります。その中で、上手にやりくりして使っていかないと、おこづかいはすぐになくなってしまいます。毎月お小遣いを渡すときに、使い道を決めて計画的に使うように使えましょう。
【ポイント2】お金を使った記録を確認する習慣を身に付けさせる
お金を使ったら、それで終わりではありません。何にいくらお金を使ったのかを見直すことも大事です。そのためには、使ったお金を記録するよう伝えましょう。スマートフォンのお小遣い帳アプリを使えば、楽しく記録ができます。電子マネーやQRコード決済を使っているなら、毎月、利用履歴を確認させましょう。
【ポイント3】本当に必要なものだけを買う
よく考えず、衝動的に買い物をした時に限って、後から後悔することが多いです。買い物の失敗はお金の無駄遣い。買い物をするときは、よく考えて、本当に必要なものだけを買うよう伝えましょう。必要なもの・不要なものを見極める眼を育てることができたら、大人になっても無駄のない安定した暮らしを送れるようになるでしょう。
いかがでしたか?中学生の子どもにお小遣いを渡すことは、金銭管理能力を育む絶好の機会です。毎月決まった日に決めた金額を渡し、その範囲内できちんとやりくりさせるのがよいでしょう。
また、QRコード決済など電子マネーでお小遣いを渡す場合は、利用履歴と残金を確認する習慣を付けさせれば、大事にお金を使うようになります。重要なのは、使えるお金には限りがあることです。どうお金を使えば無駄がなくなるか、中学生のうちから考えるきっかけを作ってあげるのも、親の役目なのではないでしょうか。
この記事を書いた前佛 朋子さんに相談してみませんか?
ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で前佛さんに子育ての悩みを相談できます。
前佛 朋子さんへの相談ページを見てみる
<参考サイト>
「キャッシュレス決済」に関する調査/ゼネラルリサーチ株式会社(PR Times)
2020年版 一般消費者におけるキャッシュレス利用実態調査レポート(NECソリューションイノベーター)
家庭における青少年の携帯電話・スマートフォン等の利用等に関する調査(東京都)
スマホ決済は危険なの?セキュリティ面を解説
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

ファイナンシャル・プランナー CFP®、整理収納アドバイザー1級。家計コンサルティング ZEN代表。15年超ライターとしてメルマガやWebコラムなどを執筆。自分の専門分野を持とうとファイナンシャル・プランナーの資格を取得。お金とモノの持ち方にはつながりがあることに気づき、整理収納アドバイザー1級を取得。お金だけでなく暮らし全体の整え方を伝授するべく活動中。 家計見直しと暮らしの整え方を伝える相談室 https://kakeizen.com/