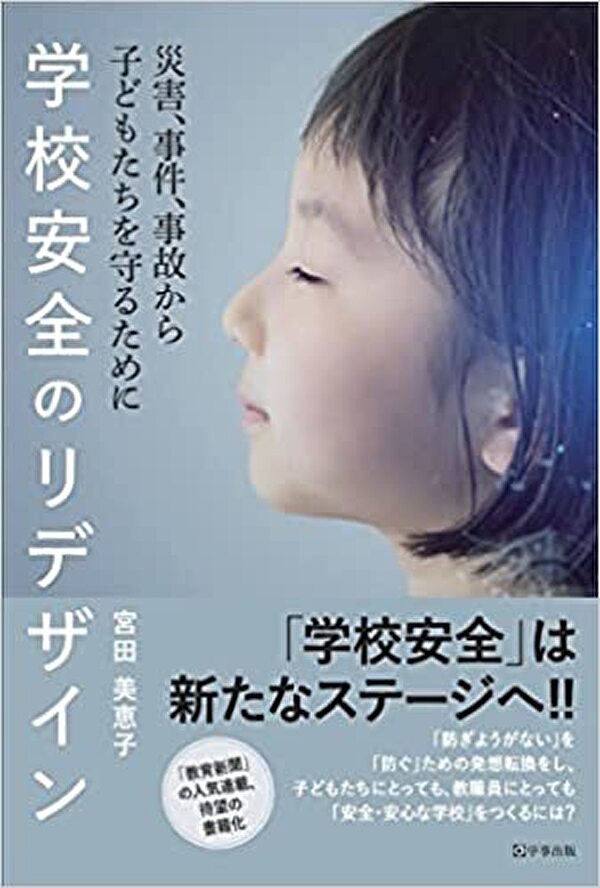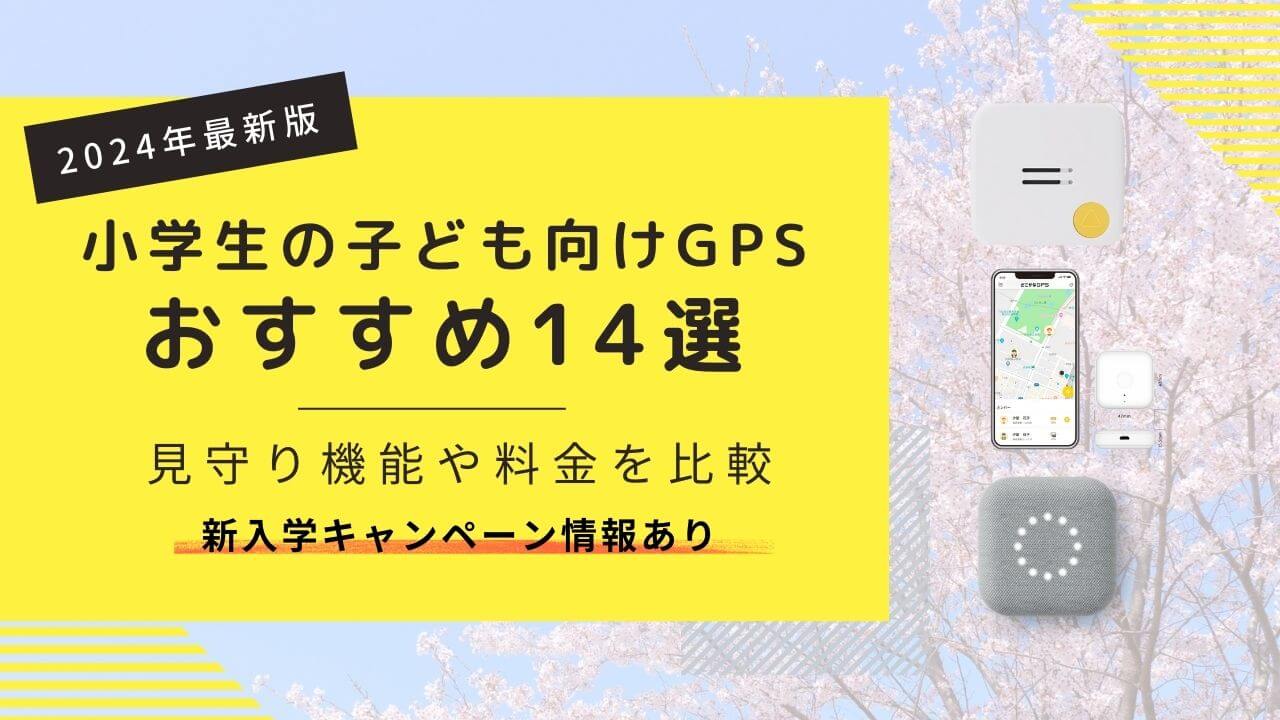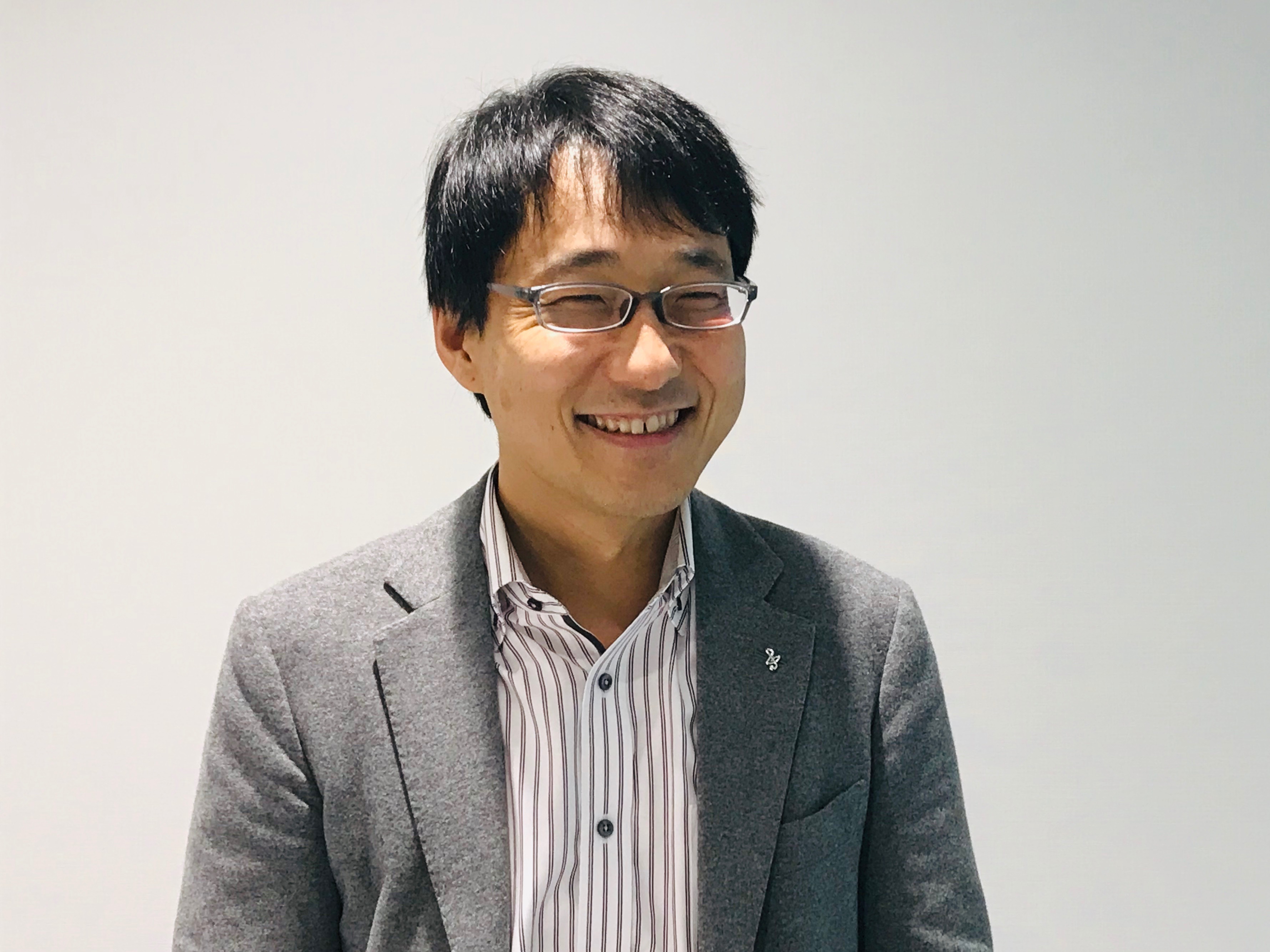バス車内置き去り事故、子どもの行方不明事件…私たち大人は「悲痛な出来事」を、どう防ぐのか?

子どもたちが被害者となった痛ましい事故・事件が相次ぐ昨今。一児の母として、また子どもたちの命を預かる教員として、ニュースを見ることすら辛く、目を背けたくなる時期もありました。しかし、そんな世の中を嘆いているだけでは現状は変わりません。教員・保護者・地域が一丸となり、子どもたちを守る必要があるのです。
子どもたちの命を守れるのは、誰?
子どもたちが被害者となった事件の数々。ここ数か月でも、複数の事件が頭をよぎります。特に、学校の現場で話題になったのが、静岡県のバス車内置き去り事故。1年ほど前に、他県で同様の事故が起きたのにも関わらず、なぜまた起きてしまったのか。園や学校での危機管理体制について、今一度見直す必要があることを痛感しました。
事件や自然災害、交通事故など、子どもたちの身に起きうる危険。その発生場所や時間帯は予測不可能。
登下校中や放課後など、教職員の目が届かないところは、保護者の方・地域の方の協力を仰がなければなりません。子どもたちが安全に過ごせる学校・地域社会になるよう、我々大人が意識的に改革していく必要があります。
では、何から始めたらよいのでしょうか。
「子どもたちの命を守りたい」
「自分にできることは?」
そんな思いを抱く大人必携の1冊が、『学校安全のリデザイン 災害、事件、事故から子どもたちを守るために』(学事出版株式会社)です。
著者は、宮田美恵子さん。日本こどもの安全教育総合研究所を設立し、子どもにまつわる事件や事故、災害の分析を行ってきました。新聞・テレビ・ラジオなどにも、安全教育の第一人者として出演。そんな著者が、「安全・安心な学校」をつくるための考え方・対応策・安全教育の基本をまとめています。
教職員が知っておきたい学校内の安全にまつわる話題はもちろんのこと、地域安全・交通安全などの話題も豊富で、子どもに関わる全ての大人たちに読んでもらいたい1冊です。
「あ、危ない!」子どもたちの身の回りに潜む危険性
子どもたちの身に起きる嘆かわしい事故や事件。
「運が悪かった」
「かわいそうな事件」
と捉えているだけでは、現状は変わりません。未然に、“万が一”が起きるリスクを想定し、防止策を練るのが危機管理の第一です。
この本では、“安全”を3領域に分け、それぞれについて、校内で見直すべきポイントや子どもたちに指導する内容を解説しています。
- 生活安全:犯罪から身を守る
- 交通安全:事故から身を守る
- 災害安全:自然災害から身を守る
自分の身を守る方法を学ぶ「安全教育」の考え方
いつ起こるかわからない事件や事故、災害。子どもたち自身が、自分で考えて行動することも大切です。
適切な行動判断ができるよう、学校やご家庭で正しい知識を身につける必要があります。自分の命を守る“安全教育”も現代では注目を集めています。文部科学省も「学校安全資料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」を発行し、その重要性を唱えています。
この本では、子どもたちにどのような内容を教える必要があるのか、またその理由について明らかにしています。学校で実践しやすいよう、あそびを通して防犯スキルを学ぶ指導方法も掲載されています。
また、近年ではスマートフォンやインターネットを介して事件に巻き込まれる事案も増えています。そういった類の犯罪の防止策についても、教師として、親として知っておきたい項目の1つです。

「子は社会の宝」という言葉もあります。
子どもたちが、安心・安全に過ごせる地域社会を!
“万が一”の出来事は、あなたの身の回りにいるお子さんに降りかかるかもしれません。今一度、子どもたちの身の回りに潜む危険性に目を向け、未然に防ぐ手立てを考えてみましょう。
<参考資料>
・学事出版株式会社 安全教育の専門家が提案する「新たな」基本書。『クローズアップ現代+』『視点・論点』他出演多数の宮田 美恵子著の新刊『学校安全のリデザイン』を刊行!(PR TIMES)
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

国立大学教育学部卒業。専門教科の国語を愛し、教科担当制の私立小学校にて勤務。好きな教材は「おにたのぼうし」。好きな文法は品詞分類。学級担任として、多くの子ども・保護者と関わる。現在は教員業の傍ら、教材執筆者・ライターとしても活動中。プライベートでは1児の母。