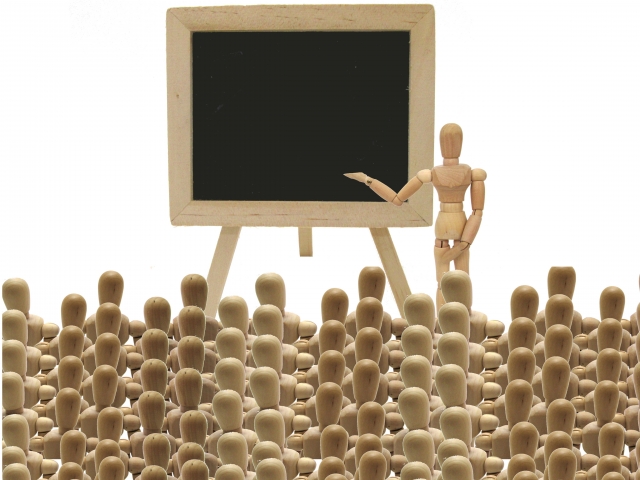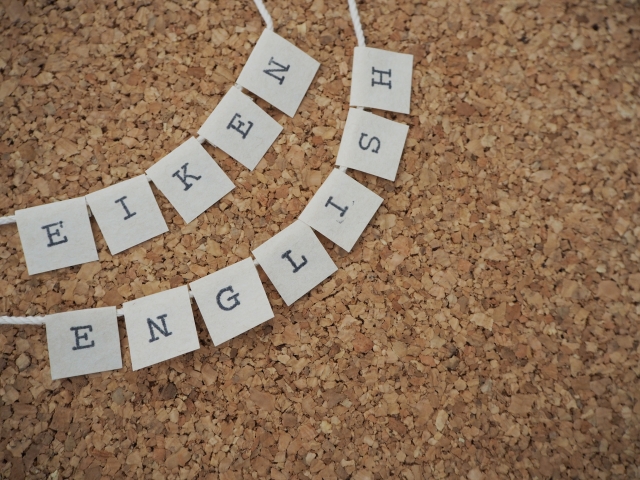怒ってばかりの子育てを変える!怒りの仕分けを始めよう/アンガーマネジメント【第8回】
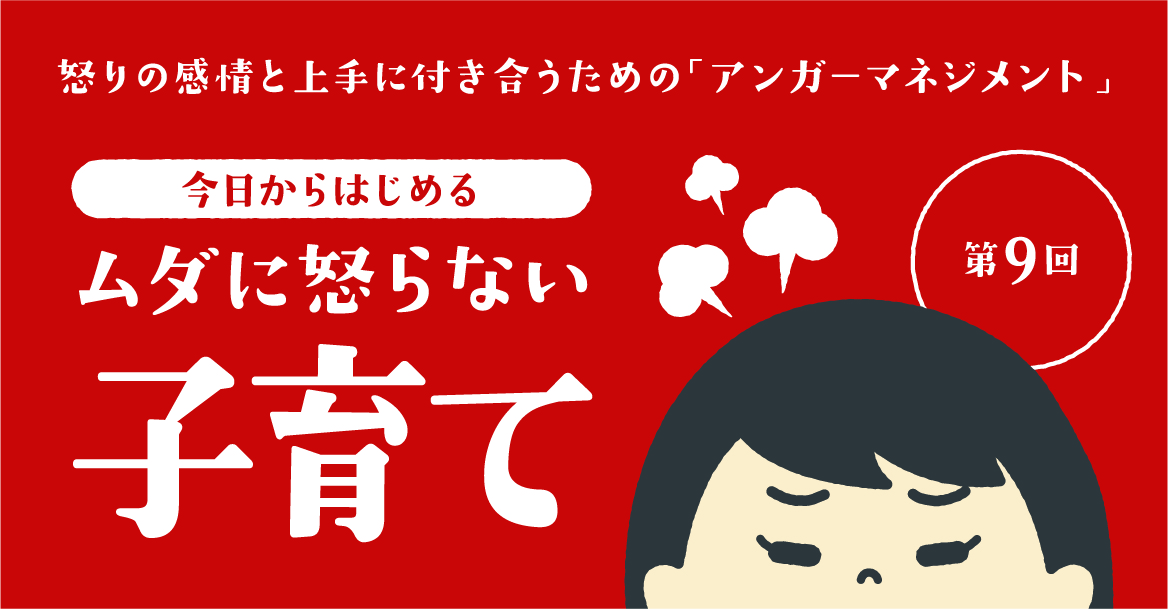
アンガーマネジメントのトレーニングを続けていらっしゃいますか?前回の記事【アンガーマネジメント8】では、怒りのクセやタイプがわかる“アンガーマネジメント診断”について紹介しました。今日は、自分のイライラについて、そもそも怒る意味があることかどうか仕分けするコツを紹介していきたいと思います。
怒る意味があることなのか考えよう
アンガーマネジメントは怒らなくなる方法を身につけるスキルではありません。怒る必要のあることは怒ってもよいのです。ただし、闇雲に怒るのではなく、まずは怒る必要のあることとないことを区別することが大切です。
※“怒る必要の有無を線引きしてムダに怒らないコツ”については、こちらの記事で紹介しています。
さらに、怒る必要があることでも“怒る意味”があるかどうかは別問題。怒る必要があると思っても、怒っても変えられないものならば怒る意味はありません。怒っても何も解決しないことに対して時間とエネルギーを費やしたくないものです。
“怒る=受け入れられない何かが起きている”ということです。アンガーマネジメントは原因追及より問題解決を目的としていることもあり、イライラにふりまわされず効率よく解決したいですよね。
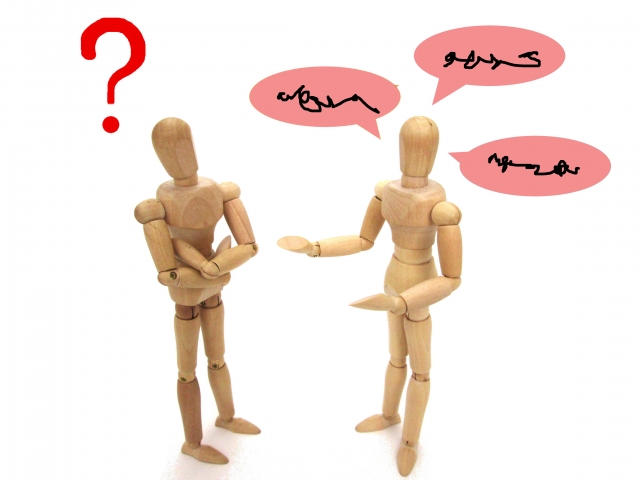
怒る意味はあるのか4つのカテゴリーに分類しよう
それでは、まず、怒る意味があるか否かを
①自分で状況を変えられるか、変えられないか。
②重要なことなのか、そこまでではないことか。
この2つを軸にして、下記の4つのカテゴリに分類してみましょう。
A~Dのどこに入れるのが正解・不正解ということではありません。どこに分類するのかは人によって違います。自分がどう感じるかで仕分けをし、選んだ結果でその場合ならどう行動すればよいのか決まります。
カテゴリーA
自分で状況を変えることができ、重要なこと。
<行動>今すぐ解決に向けて動く(いつまでにどの程度変わればいいか具体的に考えて動く)。
カテゴリーB
自分で状況を変えられないが、重要なこと。
<行動>現状を受け入れて別な方法をとってみる。
カテゴリーC
自分で状況を変えられるが、重要ではないこと。
<行動>余裕があるときに取り組む(重要ではないため、今すぐどうにかしなくてもよい)。
カテゴリーD
自分で状況を変えられないし、重要でもないこと。
<行動>放っておく(イライラするだけムダ)。
次からは、具体的にどんな風に分類し、行動に移せばよいのかを例を挙げて考えてみましょう。

分類の仕方と行動を具体的に紹介
【ケース1】子どもが靴のかかとを踏んで履いていて見る度に腹が立つ。
【A】に分類
子どもがかかとを踏まないようになるために、親としてできることがある、そう感じるなら【A】の分類になるはずです。
<行動例>
1週間後には靴のかかとを踏まないようになって欲しい。そのための具体的な方法を考えます。
プラン1:玄関の見えるところに「靴のかかとをふまない」と紙に書いて貼っておく
プラン2:靴の上に「かかとを踏まない」と紙を置いておく
プラン3:かかとを踏んでいないことがわかったら「できているじゃない」と声をかける
など。
ここで気をつけないといけないことがいくつかあります。まず現実的で具体的な方法をとるということ。そして、自分は“今すぐ”行動を起こしても、相手には“今すぐ”を求めないということです。でも多くの人はやり方や関わり方を変えることなく「いつも注意しているよね」「言われたらすぐになおしなさい」と具体的な方法をとらずイライラして時間とエネルギーを浪費してしまっているのです。
解決に向けての具体的な方法は一つだけとは限りません。特に靴のかかとを踏むクセのように習慣化されてしまっている問題の場合、すぐに変わることは望めませんので、改善に向けていくつかの打開策を持っているとよいですよ。ここでは3種類のプランを提示しています。
【ケース2】子どもの発表会に行くのに事故で電車が動かずイライラ…
【B】に分類
発表会は重要なことだけれども、願っても祈っても電車がすぐに動くわけではありません。「今日に限って何で?」と電車が動かないことに対して怒ったところで何も変わらない。それなら【B】の仕分けとなります。
<行動>
状況を受け入れて別な方法を模索しましょう。
プラン1:自家用車やタクシーを利用する
プラン2:バスなどの別の交通機関を考える
プラン3:発表会をキャンセルする
など。
中には電車が動かないことに腹を立て、駅で駅員さんに「どうしてくれるの!」と食ってかかる人もいます。重要なことでも自分で状況を変えられないことについて怒ったところで何も解決しません。ムダにゴネるよりも状況を受け入れてさっさと他の方法に切り替えた方が得策です。意味もなく誰かを責めたり、ずっと機嫌が悪いままだったりということが減れば、不意の出来事に対してイライラせずにスムーズな対策が取れるためリスクマネジメントにも役立ちます。
【ケース3】子どもが持って帰るプリントの折り方が気にくわない。
【C】に分類
気になることではあるけれど、今すぐ何とかして欲しいわけではないし、グチャグチャになっているわけでもない。それなら【C】に分類します。
<行動>
このことよりも重要なことについて優先的に関わろう。
【ケース4】ママ友のうわさ話が気になる。
【D】に分類
自分がどうこう言ったところで変わらないだろうし、よく考えたら重要でもないし、うわさ話が好きな人もいる。
<行動>
放っておいて気にしないでおこう。
このように怒る意味があることか否かを仕分けして、本当に怒る必要があることに対して効率よく時間とエネルギーを使って怒りをコントロールできるといいですね。
今日からできることを少しずつトレーニング。アンガーマネジメントにレッツトライ!
子育てのお悩みを
専門家にオンライン相談できます!
「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪
ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会(東京)アンガーマネジメントファシリテーター。子育てや教育・福祉・司法関係において、心に触れる実践的なアンガーマネジメントを伝え、一人一人が大切にされる教育社会を目指して怒りの連鎖を断ち切るために活動を続けている。著書に「マンガでわかる怒らない子育て」(永岡書店)「イラスト版子どものアンガーマネジメント~怒りをコントロールする43のスキル」(合同出版)などがある。 https://www.angermanagement.co.jp/